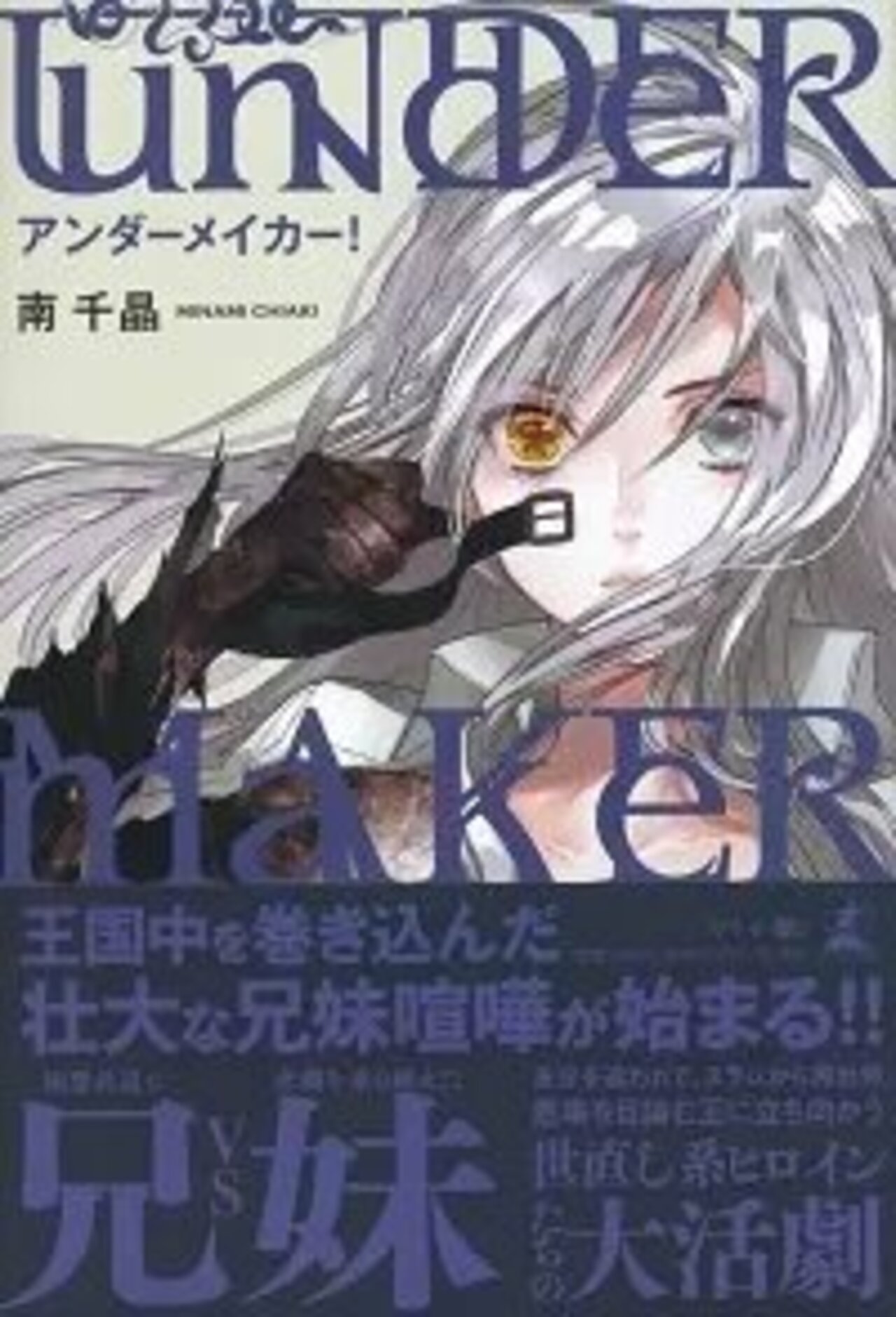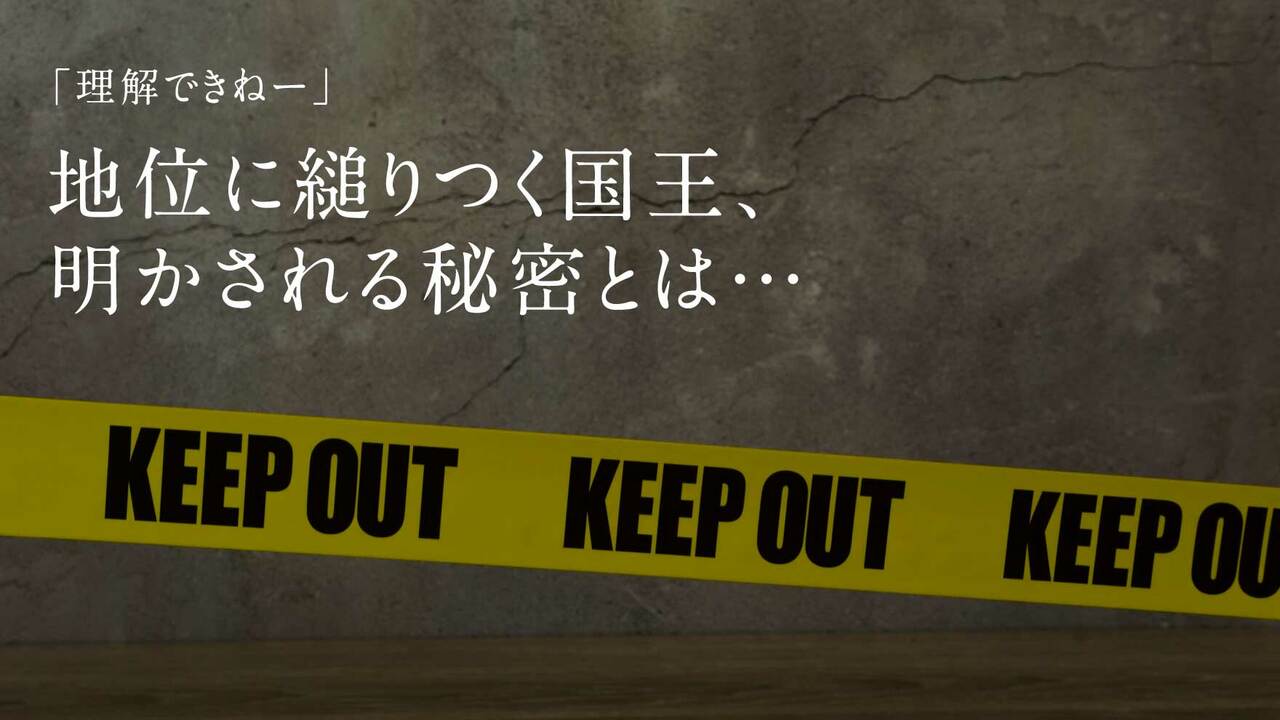「親族内で遺産相続でもめとるんじゃよ」
「アンタの遺産か?」
「うむ、もうすぐ死ぬからと、皆勝手に親族会議なんぞも開いておるわい」
「まだ生きてるってのに残酷な奴らだな」
「金銀財宝など、いくらでもくれてやろうて。だが、孫だけは……浩輔だけが気がかりでのぉ」
「その親族に追いやられて居場所をなくしそうなのか?」
「簡単に言うとそういう事じゃ。海川家現当主はワシじゃ。じゃが、次の当主はワシの娘。育て方を間違えたのか、どうにも強欲な性格になってしもぉての。あの様子じゃ、子である浩輔すら捨てる気じゃろうて」
暫し、沈黙が訪れる。彼女はそういった立場の人間に何を言えばいいのか分からなかった、というのが本音だろう。ただ川の流れを視界に入れ、穏やかな時間だけが過ぎていく。
「……じーさん、いつもここに?」
「うむ、ここは浩輔の帰り道なのじゃ」
「溺愛も度が過ぎると鬱陶しがられるだけじゃねーの? 反抗期とかあるしよ」
「いや、あの子だけはいつも駆け足で笑いながら寄ってきよるよ。ワシが育てたようなものじゃしの。ふぉっふぉっふぉ」
そしてまだ十六歳にも満たない彼女はゆっくりと立ち上がり、一枚の名刺を渡した。
「じーさんの弔いは俺がしてやるよ。話し相手が欲しいなら、ここにもまた来る」
名刺には簡潔な住所と『葬儀屋~UNDERMAKER~』という名前だけが刷られている。
「人を殺すのが俺の仕事なんだ」
老人はただ、珍しそうな表情で彼女を見上げている。
「じーさんの魂は俺が貰う。いいか?」
「噂でしか聞いた事がなかったのじゃが、本当に存在しておったのじゃな。〝姿を見せない救世主〟は」
「おう、その気になれば貴族世界だろうが華族世界だろうが、どこにでも駆けつけるぜ」
にかっと笑い、眼帯に少しだけ手を触れてから背中を見せた。そしてそのまま、従者である栗栖の背中を叩き、ゆっくりとその姿は消えていく。
老人にとっては不思議な出会いだった事だろう。だが、証拠として名刺が両手の中に収まっている。電話番号は記載されていなかったが、きっと不思議な力で駆けつけてくれるのだろう―そう思った。
「じっちゃんは、この名刺をいつも大事そうに持っていたんだ。穴が開きそうなほど、いつも見てた」
前菜を下げ、メインディッシュが出てくる頃には浩輔は落ち着きを取り戻していた。懐から出したのは、彼女が二年前に出会った老人に渡した、ここの名刺だ。その真相も知らない彼は、それを懐かしむように見つめる。
「へぇ、そりゃありがたいこって」
「その馬鹿にしたような態度、やめろ」
「馬鹿になんてしてねーよ。ありがたいお客様だったからな」
「お客、様……だった?」
「おっと、口が滑った。しまったしまった」
全然反省のない表情でメインディッシュのパスタをフォークで持ち上げ、口に運ぶ。そのままズゾゾと音を立てれば、隣でそれを見守る執事から注意された。