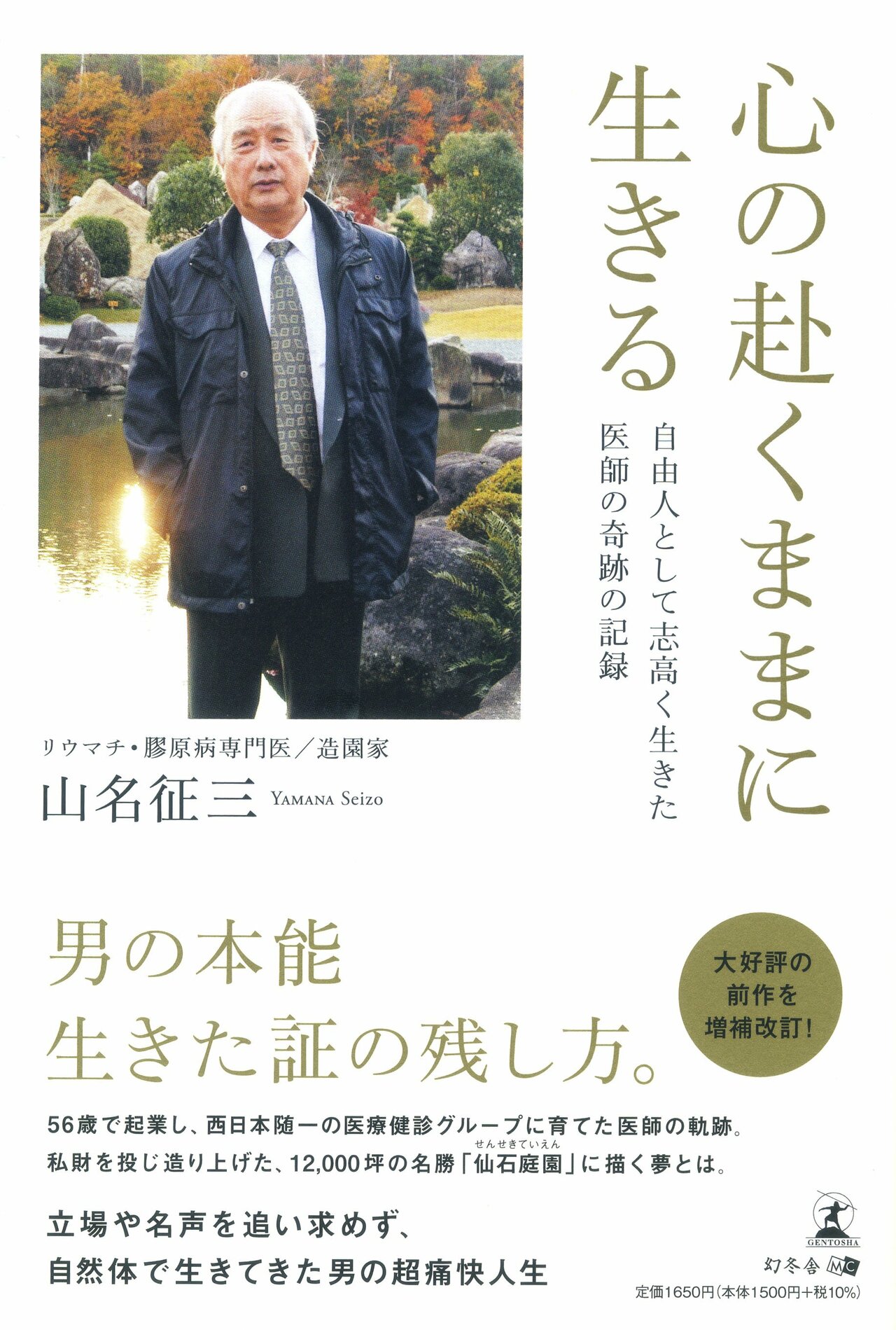【前回の記事を読む】日本と豪州の板挟み…キャリア決定に伴う大きな葛藤とは
帰国の決断とその後の交流
私の心は日本に帰れと言っている。日本でポジションがなければ生活に支障を来す。オーストラリアではネイルン教授、ジェニファーにずいぶんお世話になった。そのことは心より感謝している。
私はオーストラリアでプロとしての仕事を続けるには語学のハンディが大きすぎる。Ph.D.の論文を完成させたことは事実であるので、Ph.D.の証書を授与されなくても仕方がない。決めたら気持ちが楽になり、春休みで誰もいない教室の私の机の上に簡単な詫びの手紙を残して、3月末メルボルンを離れた。
半年間音沙汰がなかったがその年の9月、ネイルン教授よりPh.D.の認定証書と論文の原本が送られてきた。このわがままな日本人に吾が恩師ネイルン教授が温情を示し、許してくれたのである。帰国後は訪豪してお会いし、退官後英国に帰られてからも師弟の交わりを続けた。
以来、ネイルン教授とジェニファーとの付き合いは続き、名誉教授ネイルンを日本にご招待し、京都にお連れしたことを懐かしく思い出す。ジェニファーは度々日本に来て日本の生活を楽しんでいた。今は年に一度のクリスマスカードでお互いの消息を確認している。長らく会っていない。私も80歳を過ぎた。身体の動くうちに一度は会いたいと考えお互い連絡を取っている。楽しみだ。
現代の浦島太郎
3年ぶり、正確には2年9か月ぶりに日本に帰国し、昔の職場に復帰した。そこで見たものは浦島太郎が竜宮城から故郷に帰り、玉手箱を開けた時の状況はかくありなんと思わせるものであった。教室は3年前に出た時の、あの薄暗い汚れた戦前の木造建築のままで、天井には蜘蛛の巣が張り、床はミシミシ音がし、今にも穴が空きそうであった。まさに3年前の姿がそのままあったのである。
メルボルンでの研究環境から360度回って、さらに180度回ったくらいの変化に驚き、奈落の底に突き落とされたような思いであった。人間は3年ほど素晴らしい環境で生活し、仕事をしていると、その間に自分の古巣の研究環境もよくなっているに違いないと勝手に夢想するものである。少なくとも私はそうであった。臨床の教室で研究を主たる目的にしていない施設とはいえ、あまりにもお粗末な現実がそこにあった。私の気持ちから研究意欲が急速になえていくのを感じた。