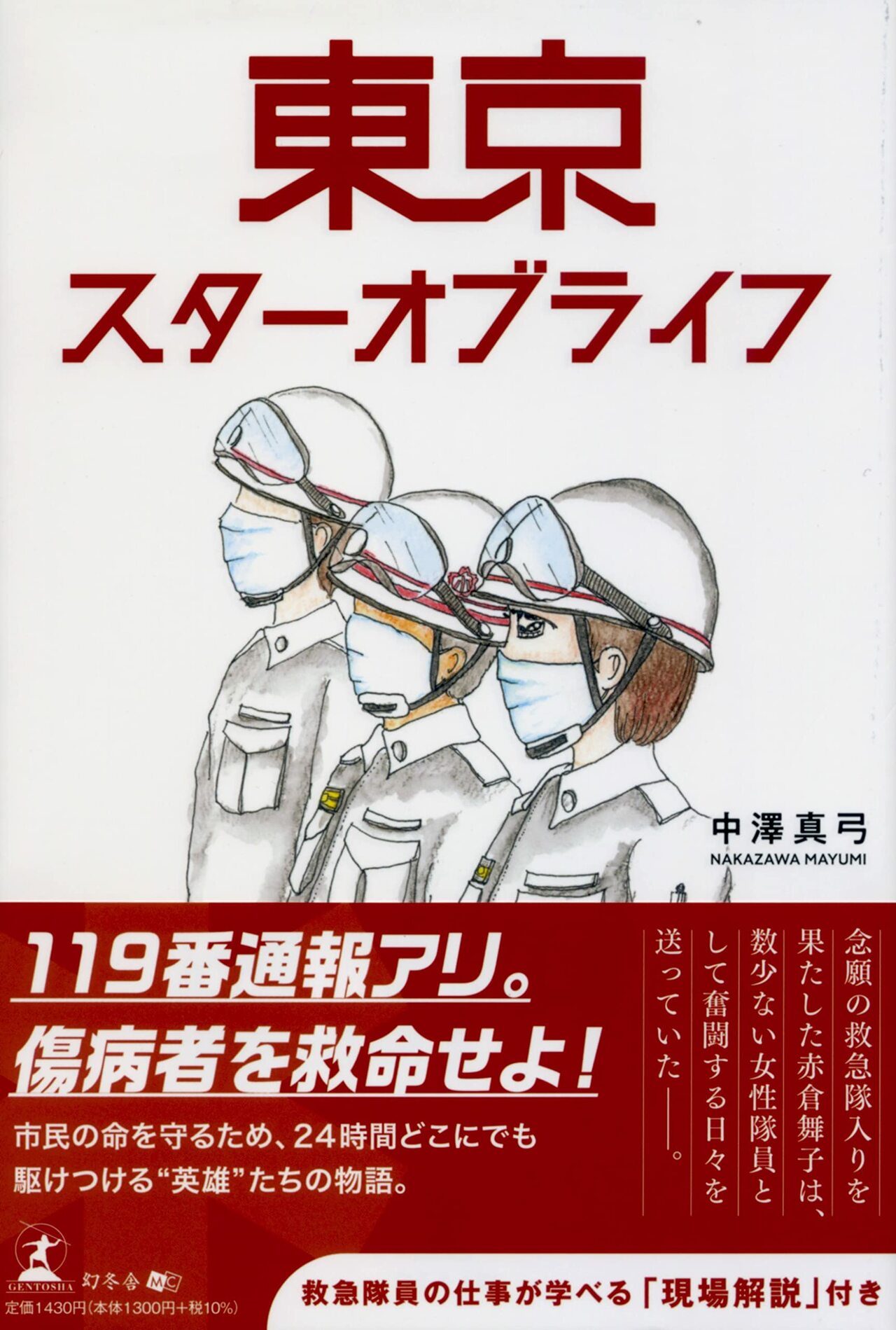【前回の記事を読む】救急隊は男性多数…「女性だからできないと感じたことはない」
ピット・フォール
救急活動の奥深さの一つに、自分たちが活動するフィールドが無限大に広がっているということがある。
「病院の医師は、救急隊が搬送してきた傷病者を診察し、治療を行うが、その舞台は病院だ。初療室や手術室、病室、レントゲン室やCT室、いろいろな場で治療を行っても、基本的に働いている場所は病院や診療所という、自分たちの『城』だ。しかし、救急隊が活動する『現場』というのは、数えきれないほどバラエティに富んでいるんだ」
一般住宅、会社、駅、路上、公園、学校……。それ以外にも、この仕事でなければ足を踏み入れることもなかったような場所で活動することが多々あると、菅平は続けた。
「その『現場』で、傷病者に何が起こっているのか。教科書や試験問題に書いてある想定ばかりではない。それでも、人体の解剖生理と目の前で起こっている病態を結び付けられるようになれば、どんな現場でも対応できるようになるんだ」
「お顔を、イーッってしてみてください」
右の口角が下がっている。
「次に、目をつぶって、手のひらを上に向けて、このまま動かないでください」
左腕が、だらんと下がる。
「『今日は、いい天気ですね』って言ってみてください」
「おうは、いいれんきれすね……」
呂律が回っていない。言語障害だ。
「隊長、CPSS(Cincinnati Prehospital Stroke Scale:シンシナティ病院前脳卒中スケール)で、顔面と上肢の麻痺、言語障害の三項目ともポジティブです。脳外科選定でいいでしょうか」
菅平から返ってきた答えは、舞子の判断とは違ったものであった。
「……いや、血糖測定をしてみよう」
「さっきの、低血糖傷病者の件ですが……」
帰署途上の救急車内で、舞子は後部座席から助手席の菅平に尋ねた。医療機関からの引き揚げ時は、活動を振り返る会話が展開されることが多い。
「糖尿病の既往もなく、手足が麻痺して動けないっていう通報だったので、てっきり脳血管障害かと思いました」
傷病者は六十五歳。自宅で四肢麻痺と言語障害を発症し、救急要請となった。既往歴は特になし。妻が友人と二泊三日の旅行から帰ってきたところ、自宅のリビングで動けなくなっていたという。
血糖測定の結果は四十五mg/dl。低血糖と判断し、現場でブドウ糖溶液の投与を行った。
「傷病者は、完全に奥さんに管理されているんだろうな……」
菅平の目に留まったのは、キッチンに捨てられていた酒の瓶とビールの空き缶だった。
「おそらく三日間、ろくに栄養のあるものも食べずに、奥さんが旅行で留守にしているのをいいことに酒びたりになっていたんだろう」
アルコールか……確かに、アルコール多飲は肝臓の働きを抑制し低血糖になると、教科書にも書いてあった。低血糖により脳のブドウ糖が不足し、脳血管障害と同じ症状が起こることも、大学の講義で教わっていたのに、舞子はそれに気づくことが出来なかった。