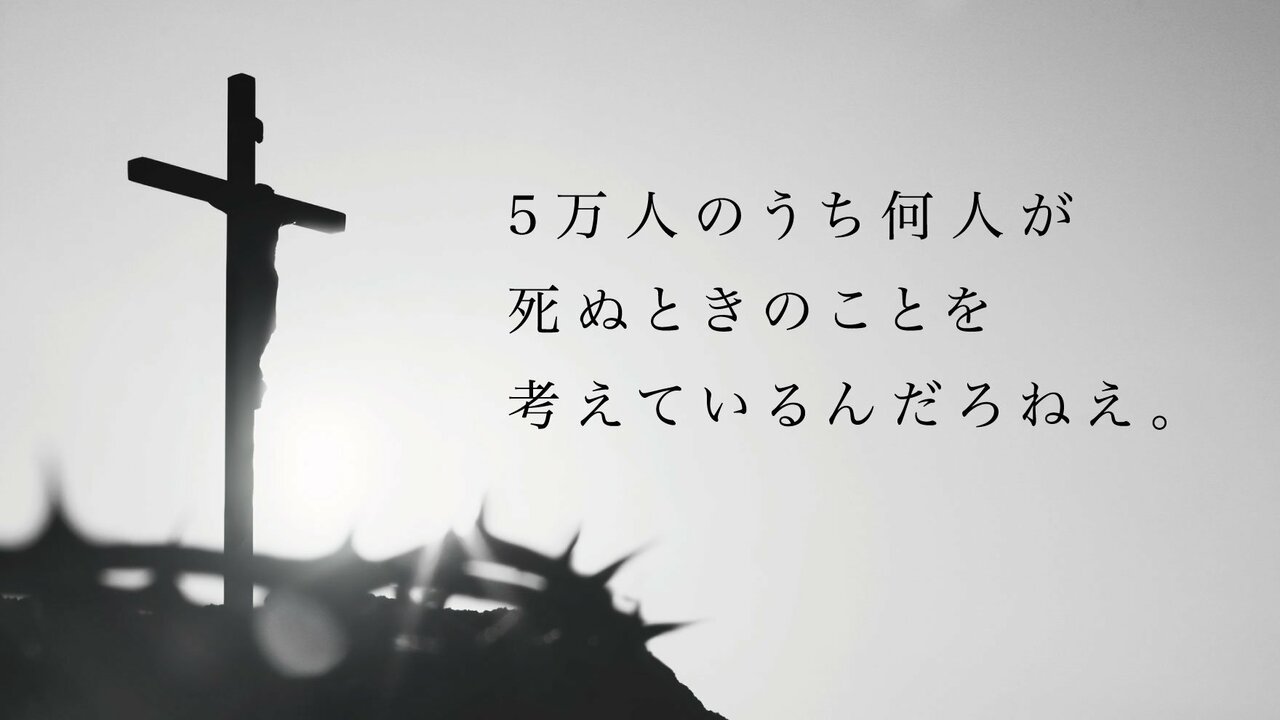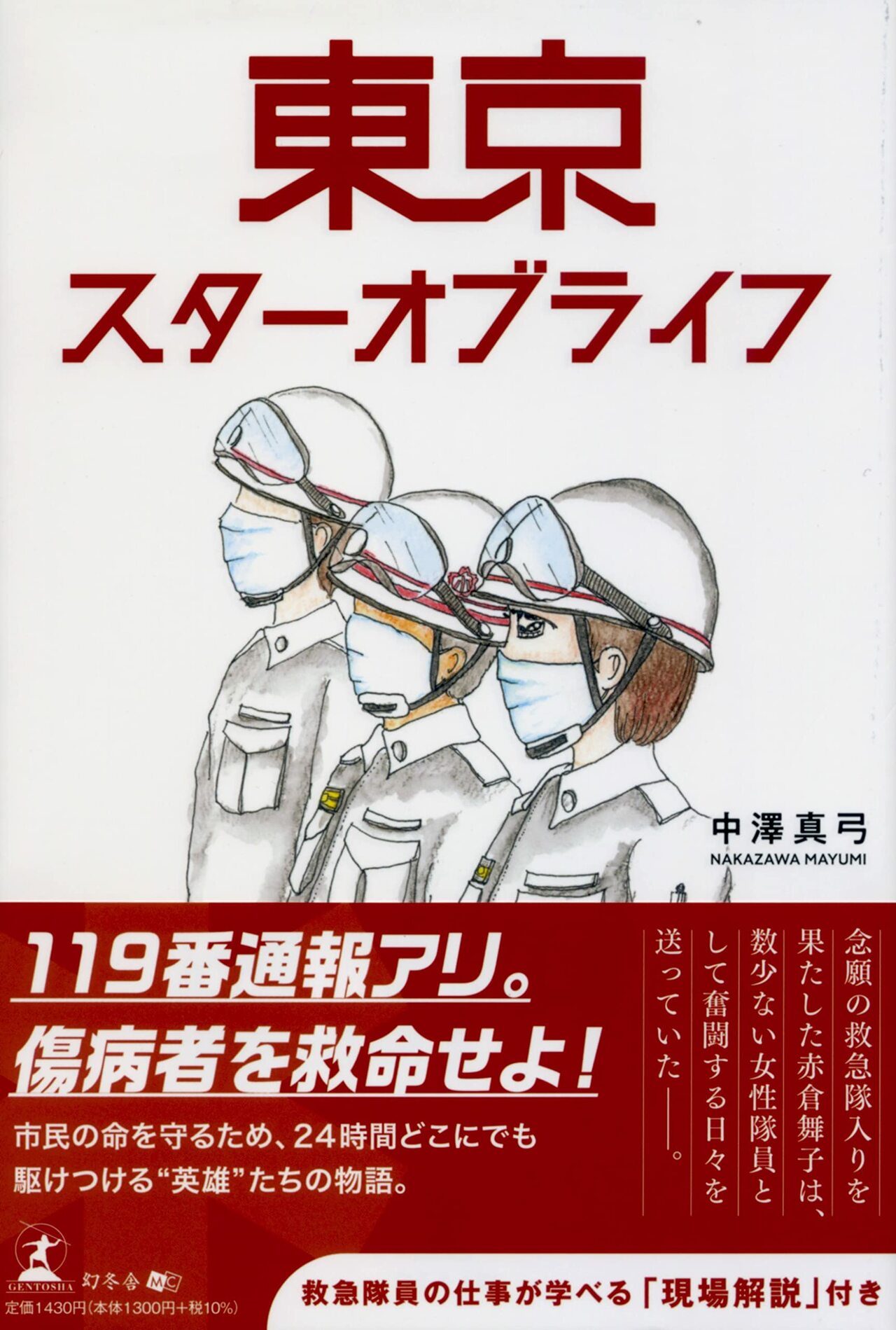【前回の記事を読む】【小説】非番中、新人隊員との野球観戦…先輩の真の目的とは
心肺蘇生
「あ、勘違いしないでもらいたいんだけど、俺らは救急活動に全力も尽くしているし、一生懸命やってるよ」
岩原は既にビールのカップを半分まで空けて、頬が赤くなっている。伝統の一戦、七回裏の攻撃が始まる。読売巨人軍応援歌「闘魂こめて」が流れ始めた。
「いま、ここにいる約五万人の大観衆のうち、何人が『自分が死ぬとき』『家族が死ぬとき』のことを真剣に考えているんだろうねえ」
菅平の声は、大観衆の歓声のなかでも、舞子の耳にはっきりと聞こえた。
「いざ、心臓が止まってから……初めてその家を訪れた救急隊が、現場で感じる雰囲気っていうか、第六感というか洞察というか……。規則やプロトコールにすべてがあてはまるものじゃないから、難しいし、やりがいもある。今、バッターボックスに立っている若き四番バッターの彼も、プロにしかわからない現場学があるんだろうね」
「お義父さんはいま、呼吸も脈拍も感じられない状態です。私は、救急救命士です。今から医師の指示を受け、口の中にチューブを通して空気の通り道を作ったり、腕から点滴をとって、心臓を動かすための薬を入れたりしたいと思います。よろしいですね?」
菅平が、第一発見者である傷病者の息子の嫁に説明している。
目の前では、活動支援に来ているポンプ隊員が傷病者に胸骨圧迫をしている。……二十八、二十九、三十。舞子は、胸骨圧迫が三十回を数えた時点で右手に持った人工呼吸器のバッグを握り、傷病者の胸が膨らむまで、空気を入れる。
傷病者は、八十歳男性。自宅居室で意識がなくなっているのを、朝、起こしに来た息子の嫁が発見。最後に会話をしたのは、昨日の晩だという。
先日は八十九歳のCPA傷病者を扱ったばかりだというのに、二当番連続で、高齢者の心肺停止の事案か。