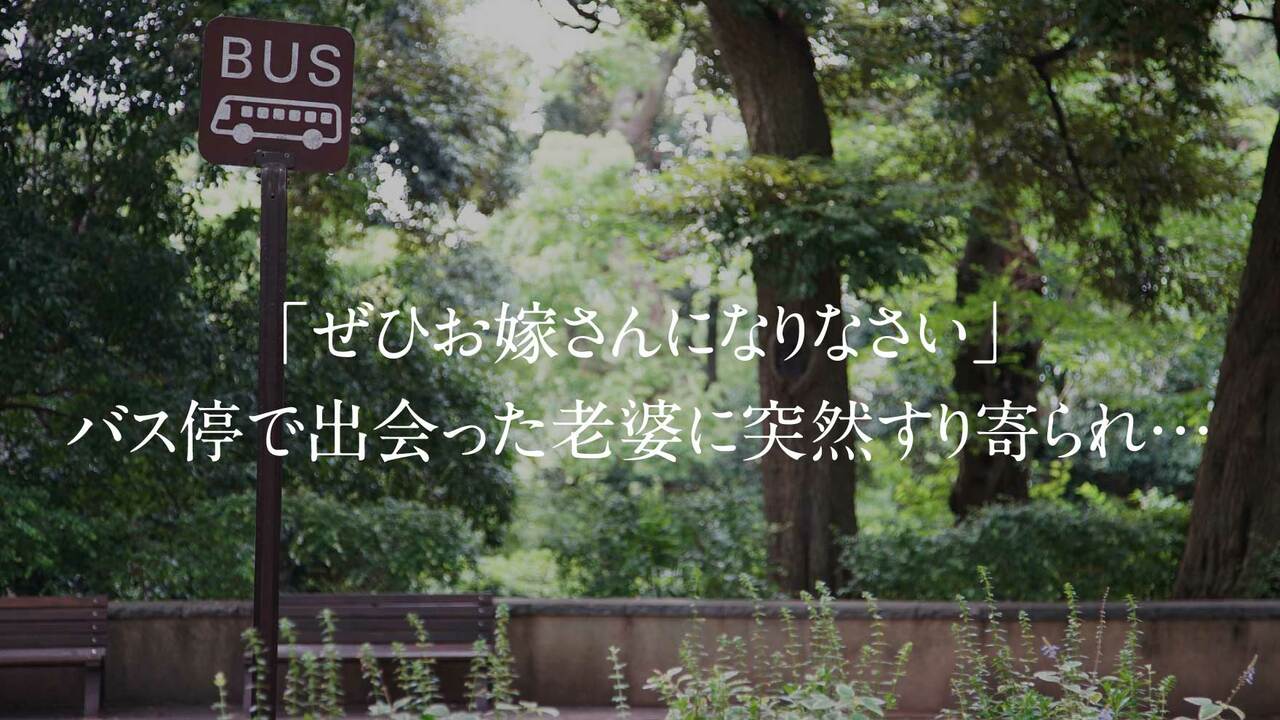ビニールに覆われた茶色の小包を受け取り、私たちは帰り道を急いだ。
でも今度は、セーターが見たくて見たくて我慢できなくなり、私たちは途中の水小屋に入った。私は座り込んで、指で何度も小包をつついたが、なかなか開けられなかった。そして……同時に「うわぁ~」という歓声を上げた。
破れた穴の間から、今まで見たこともないような青や黄色や緑色の編み込み模様の赤いセーターが顔をのぞかせたのだから。その日私たちは有頂天になっていた。
用事もないのにお揃いのセーターを着て、いとこの家に出かけたり、村の中を歩いたりした。村の人に出会うと、わざとフランネルの防寒着を開けてみせたりして、幸せ気分を満喫した。
妹の満面の笑み。得意満々の私。
そして夜になると、今度はそのセーターを枕元にたたんで並べ、眠りについた。私はなぜかこの幸せな記憶を思い出すと、三好達治の『三好達治詩集』より『乳母車』の詩と、室井犀星の小説『あにいもうと』が連鎖的に浮かんでくる。
『乳母車』
母よー
淡くかなしくもののふるなり
紫陽花いろのもののふるなり
はてしなき並樹のかげを
そうそうと風のふくなり(後略)
後に室生犀星という人も、ペンネームは故郷金沢の犀川から取ったことを知った。そしてあまりにも複雑で、哀しい生い立ちを背負った人であること。アランは「詩とは救われている幼心だ」と言ったそうだが、特に美しかった生みの母親への思慕の想いが強かったのだろうか。詩人、小説家として大成した人生を想像すると、悲しみはむしろ飛翔され人間の魂の不思議さを思わずにはいられない。