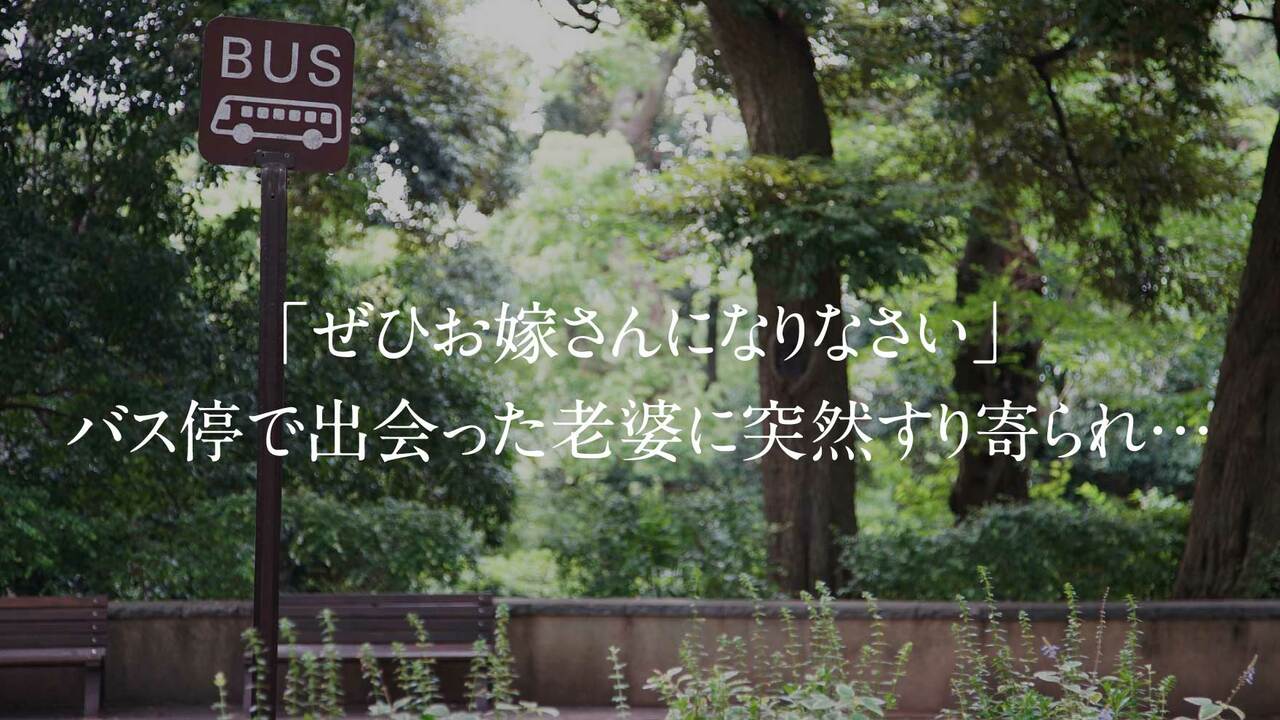あの頃、私の中には阿弥陀如来の他にアマテラスがいたし、神様もギリシャの神々もいた。そして不思議・魔法が大好きだった。我が家にはテレビもなく空想好きの私は、兄弟や従姉妹にそれぞれ役を演じさせて遊んでいたのだからたまったものじゃない。みんな犠牲者で、姉はいまでも(女王様ばかりやって)と嘆く。
現実の世界は、私にとって非現実の世界でもあり、この感動を誰にも話さなかったし、家族は私が本を読んでいることも知らなかったと思う。家の中で本を読むのではなく、私には秘密の場所があった。
橋を渡ると、小高い丘のような「たかゆう山」と呼ばれている小さな山があった。奥に雑木林が広がっていて、その一角に柔らかい草が生い茂っている私だけの秘密の基地があった。その草むらに寝転んで本を読むのが一番幸せな時間だった。揺れる木の葉のざわめき。白つめ草や夏の入道雲。雷。秋には野あざみ、桔梗、おみなえしが風に揺れていた。周囲は山に囲まれた私の一番大切な場所だった。
今頃になって思う。困難なことが起こっても、帰って行ける場所を持っていたことは何と幸せなことだったのだろうと。たとえその場所がなくなったとしても、人はもう一つ思い出(記憶)というかけがえのない宝物を持っていると、記憶の大切さを思うことがある。
ある秋の日、いつもの草むらに寝転んでいると、目の前をスーッと赤い何かが通り過ぎていった。咄嗟に「火の車輪だ!」と思い感激して涙ぐんだのだから、私はまったくおかしな子どもであった。今思うと赤トンボだったような気がするのだが、そういった思い込みの激しい所もあった。
また、ペルシャという国を思い浮かべると、いつも胸キュンになっていた。それは、『アリババと四十人の盗賊』や『アラジンと魔法のランプ』などの影響だと思われるのだが、大人になってからも、この国には私を魅了する特別な教えがあるような気がしていた。
後になってスーフィ教を知った時、「これだ!」といった喜びが湧き上がった。後に様々な人に出会うことによって、子どもの頃から、直観と想像力が一番大切なおかしな子どもだったことが納得できた。
スーフィ教。つまりスーフィズムとは、イスラム教の神秘主義である。初期のイスラム思想家たちが、虚飾を廃した印として、粗末な羊毛(スーフィ)の衣を身にまとったことでスーフィ教と呼ばれたこと。初期のスーフィたちは、人里離れた隠遁生活をしつつ、忘我の悦惚の中で神との合一を果たすため、禁欲的で厳しい修業を行い、神秘体験に導かれるのである。
後に、ルーマニア出身の宗教学者、ミルチア・エリアーデを少し読むようになって、世界には様々な宗教が存在することに驚かされた。