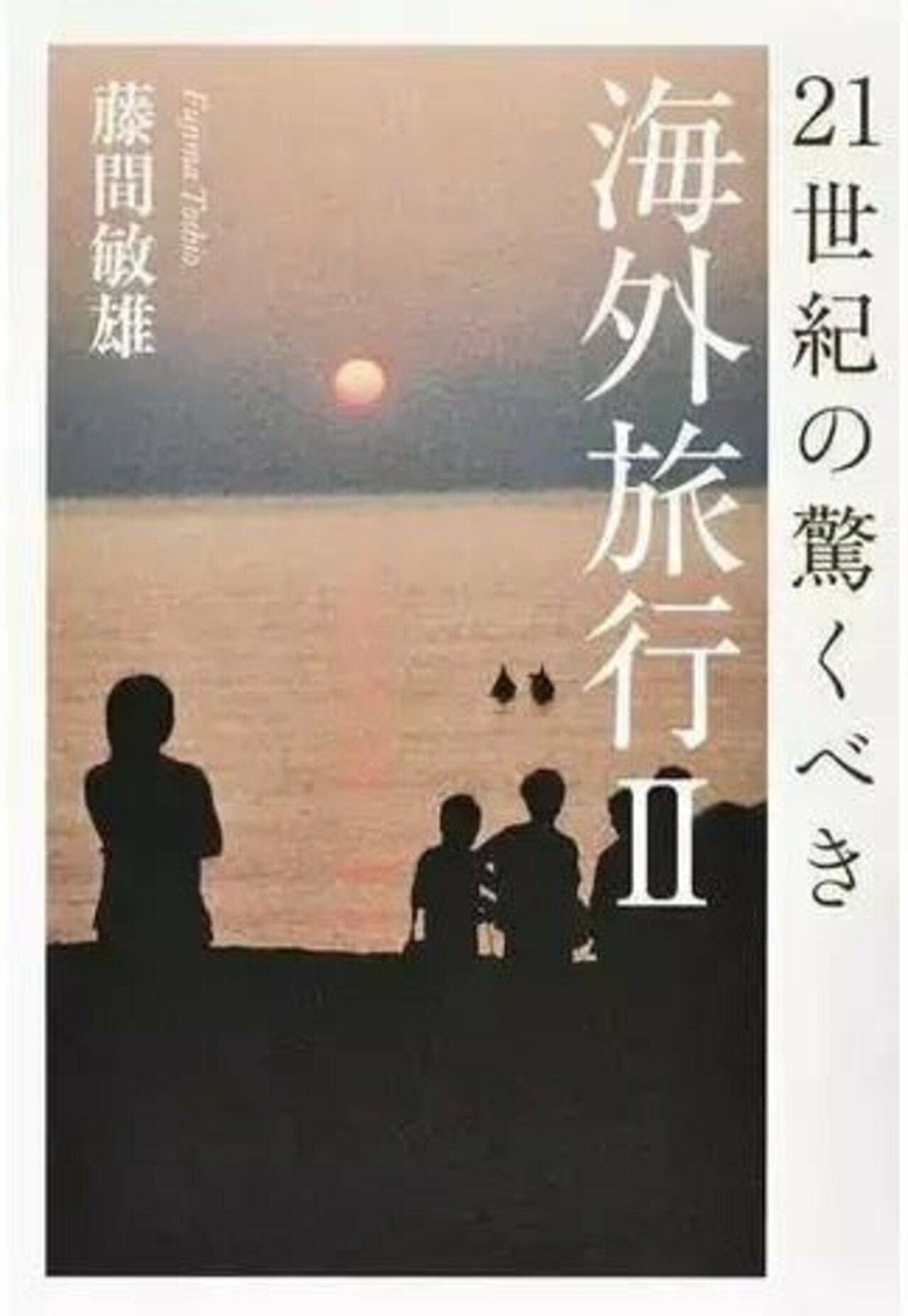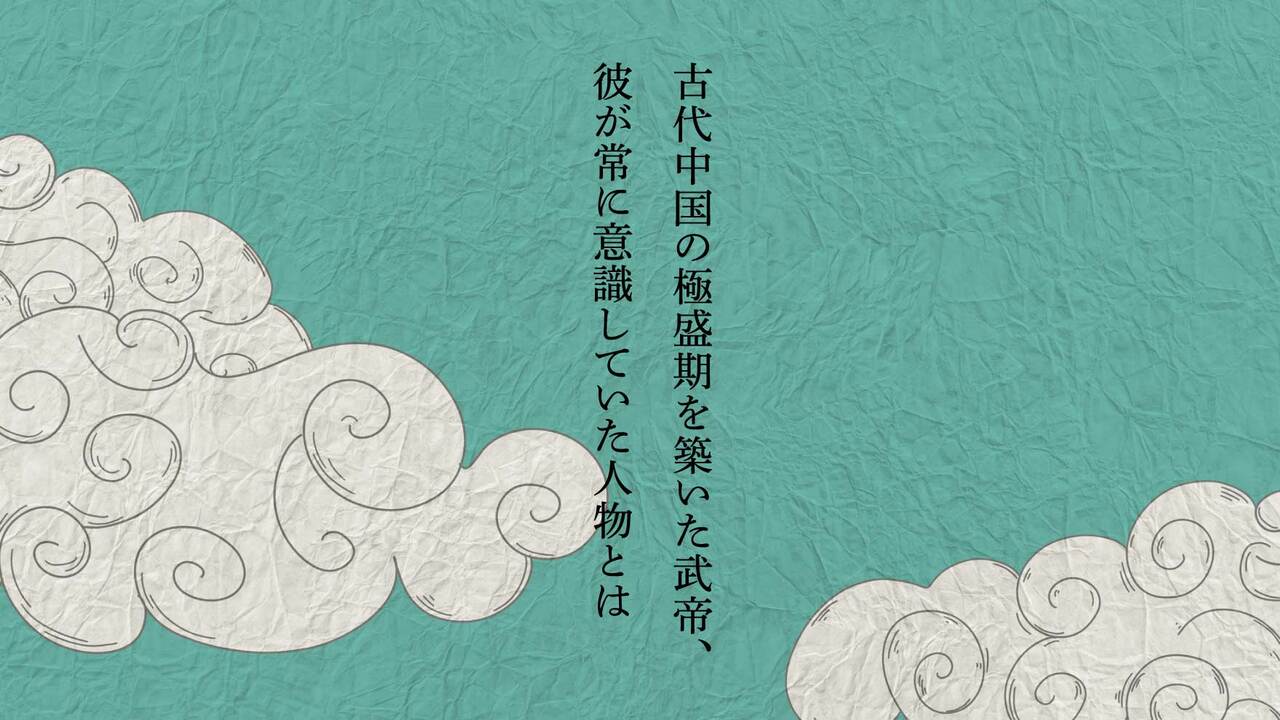異端者も信仰者
オリーブ、糸杉の丘の道、アッシジの街を東に通り抜けるとピンクの大理石で造られた可愛い教会がある。これは美貌の聖女キアラに捧げられたものである。フランチェスコの女弟子として、彼の後半生を彩ったキアラとの関係は、信仰だけに結ばれたプラトニックな愛情と解釈する人が多い。これはまさに越後の雪深い里での良寛と貞心尼の愛を思い出させる。
フランチェスコ派を考えると、同じカトリックでも正統と異なる教義をもった諸派が存在することがわかる。これを広い意味で異端と捉えるとキリスト教は正統と異端の激しい戦いの歴史だった。中沢新一の『宗教入門』(マドラ出版刊、この人はニュー・アカデミズムの旗手として、七〇年安保世代を代表する面白い宗教学者だと思う)によると、キリスト教はいつもグラついているところを持っている。自分と少しでも意見の違うものを異端と見なしたら、それを徹底的に追い込み、絶滅させるくらいのことをやっている。
これは信仰の核心に「キリストは神の子である」という命題(先ほどは、これをウソと表現した)が座っているために、そこから膨大な倫理的可能性が発生した。そのため神学者たちは、大変な努力を重ねて「正統」を創出してきた。だから、苛酷な異端審問を行わなければならなかった。反面、その戦いを通じて、正統の巨木をヨーロッパ文明のど真ん中にそそり立て、そこから豊かな文明を作り上げてきた。
この中沢氏の解釈によれば、ヨーロッパは異端者の死臭があたりに漂っている地というわけである。処刑された異端者にも親族、友人もいたろう。彼らの怨念は常に正統派を脅かしていた。一九世紀に至りフランス革命を機に、正統は根本的にグラついた。ニーチェは「(正統派の)神は死んだ」と言い、ドストエフスキーは『カラマーゾフの兄弟』の中で、正統派の権力悪を徹底的に批判した。異端者の中にも真の信仰者はいたことがわかってくるにつけ、キリスト教論議は益々世界思想に影響を及ぼしているのが現状である。正統派すなわち例えば法王庁もじっとしていられない。