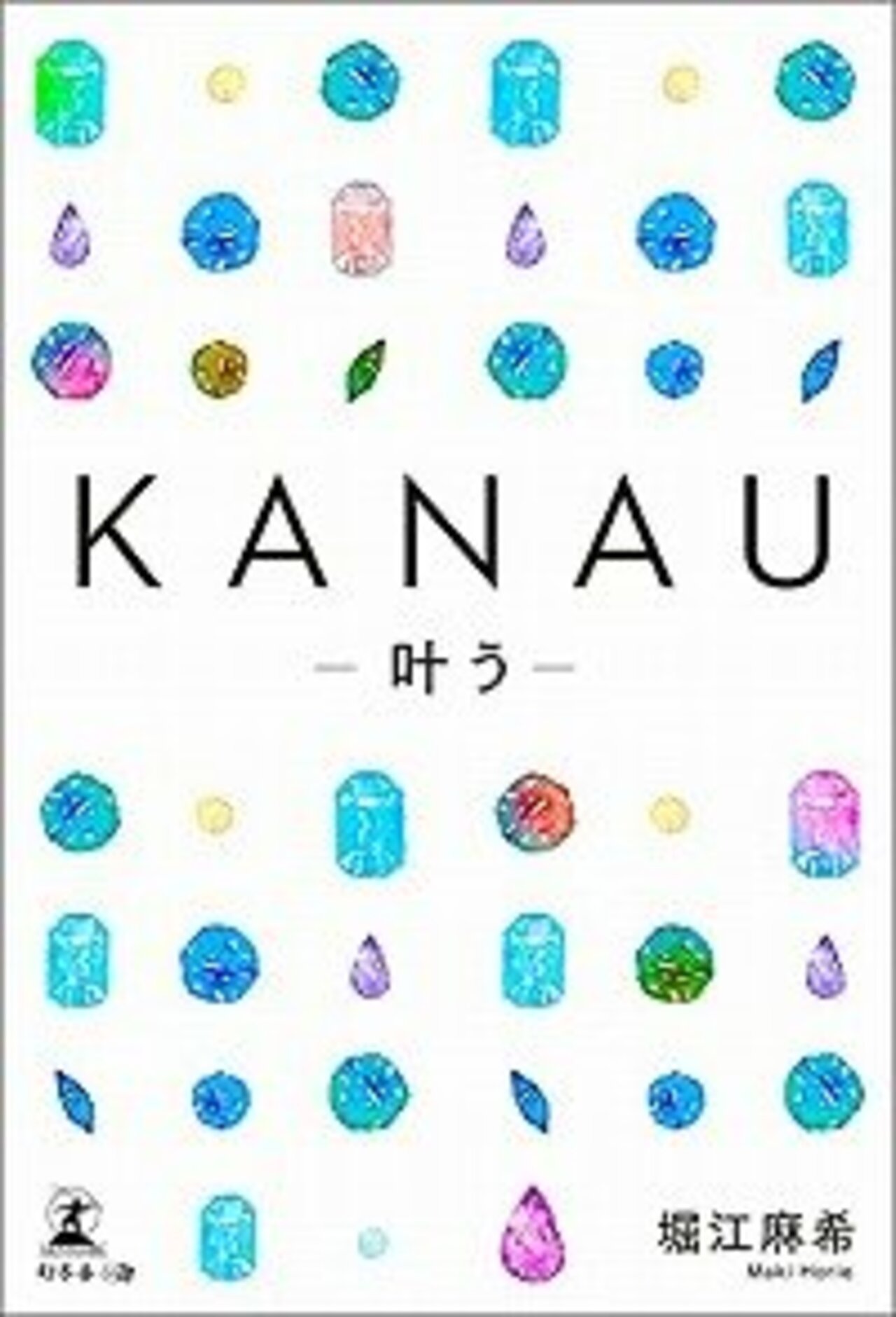「あなたに会う資格」を作り直した。望風の作曲に武士が詩を書きかえて、武士が曲としてアレンジした。武士は曲のアレンジ力のレベルが高い。ボーカルは大地で、望風がピアノ、武士と大地でギターを鳴らして、優理がドラムをたたく。
この曲はそのスタイルでいくことに決めた。力強い大地のボーカル、望風の繊細でメロディアスなピアノの表現、武士の緻密で巧みなギター技術の才能、優理の安定したリズム感がバンドを動かす。
四人それぞれのセンスが一曲を作り出す。そしてそれぞれがバンド内の役目をシフトしたり、自由自在に曲を操ることが出来る。役目を固定しないことで、曲の仕上がりが毎回新鮮で、一曲を四人の思い通りに極めることができる。この四人は、才能あふれる次世代的なバンドであると言える。
快晴だった日の夕暮れは、なんとなく奏多へ足が向く。目の前の真っ青な青空は、元気をくれる。なにもかも信じていいんだよと誘惑されているような、そんな気にさせてくれる。でも、快晴が豪華に見える分、水平線に吸い込まれていく太陽だけが、なんだか独りよがりのようだ。望風は、沈む夕日とそれを受け入れる海を見ていた。
遠くで大地の声がして、我に返った。
「もーかー」
「おーい」
だんだんその声が近くなってきて、聞こえる声をたどって大地を探した。水着姿でマウンテンバイクに乗っている。優理も武士も一緒だった。
「やっぱりここにいたな」
大地はそう言って、マウンテンバイクを望風のそばに停めて海へ走っていった。望風が元気だなあと思いながら見ていると、優理も、着ている服を脱ぎ始めている。脱いだTシャツを望風に投げかけて、はしゃいだ声で叫びながら海に飛び込んでいった。男の子の無防備さを羨んだ。
望風は、その行動にやっぱりねと思いながら、優理が脱ぎ捨てたTシャツをたたんで、サンダルを並べた。無邪気にはしゃいでいる二人を見て、笑った。このままでもいいかなとさえ思ってしまう。
望風は、四人でデビューすることを望んでいた。望風は、すべての人、すべての出来事を癒せるような歌い手になりたいと思っていた。でも四人でいると幸せで、このままでもいいかなとも思ってしまう。時が止まる魔法があれば……、そんな詩も書いてみたいななんて思った。
もしこのまま夢が叶わずに時が流れるとして、いつまでも四人で笑いながら演奏して……。大人になってもたまに集まって……。そんな場面を想像してみると、意外にもそれでも幸せだと思った。あきらめた方が楽しいかもしれない。それでも叶えたいと心の底から思っているから、そのベクトルで動いてしまう。
悲しげな表情で過ごしてもさみしげな表情で過ごしても、夢は消えない。あきらめたくて落ち込んで投げ出したくても、消えない。進むしか手立てはなかった。大地も武士も優理も、きっと似たような思いを持っているから、望風を守ろうとする。武士がマウンテンバイクをとめて、望風の隣に座った。