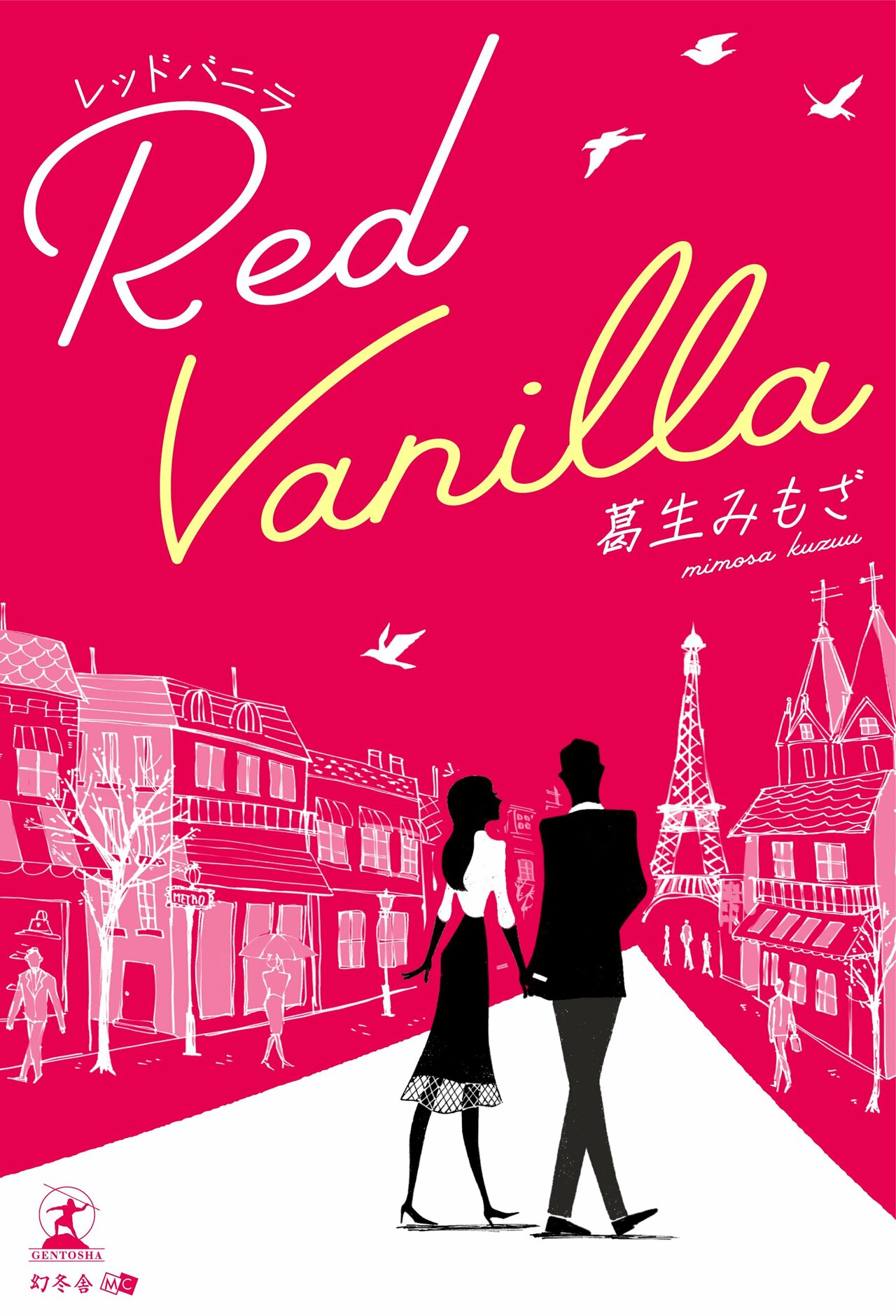Ⅴ 彷徨カルチェ・ラタン
土産が増えてしまったので、バゲッジに入れようと一度ホテルへ戻る。フロントで「荷物を入れたいので、バゲッジをここで開けてもいいか」と尋ねると、「かまわないよ」とすぐに許可してくれた。このホテルはとにかくエントランスが狭く、受付はあるがロビーがない。最初、エレベーターもあるのかどうかさえ、わからなかったほどだ。フロントに客が来ないうちに、手早く荷物を納めてまた外に出た。
ショッピングをしながら私は彼の店が開く昼の十二時を待つ。しかしそのときはまだ決定的なことを知らないでいた。それは、このあとどれだけの悲しみを抱えなければならないかということを意味した。つまり、パリでは月曜日はホリデーであり、たいていの店はクローズが習慣となっていることを、日本人である私は知らなかった。
正午になって、彼のレストランに行くと閉まっている。誰もいないし、オープンの準備をしている気配もない。おかしいとすぐに気づいた。他の店も、いつもならオープンで活気が出ている街であるのに、今日は街自体が日常ではない。いつもやっているスーパーのレジで聞くと、月曜日はホリデーだと教えてくれた。私は茫然とした。
ふらふらと歩いていたかもしれない。彼は連絡をくれないし、こちらからもその手段はない。彼は私をどのように考えていたのか。一日目は、あんなに仲良く過ごしたのに、風のように消えてしまった。
セーヌ川のほとりを散歩しながら芸術橋を半分まで渡るも引き返す。右岸に渡っても行く当てなどない。帰りのタクシーは午後五時だ。まだ五時間もある。エッフェル塔や凱旋門を観光する余裕は十分あるので、パリ観光に行こうかとも思ったが却下した。こんな気持ちで人込みに出かけたら、スリに狙われるのが関の山だ。
それから私はセーヌ河畔に腰をおろし、ただ黙って対岸を見つめていた。晩秋のパリで彼ときちんと別れが言えなかったのは残念だけれど、仕方がない。冬がそこまで来ているパリの冷たい風に吹かれながら、私はしばらくセーヌ川と一緒にいた。
ここからはノートルダム大聖堂が近い。私は慣れた道を歩くことしかできなかった。ノートルダムの前では、ギター弾きが切なくも「アランフェス協奏曲」をつま弾いている。聞いている男女はみな仲睦まじく、男性が女の子の頭にキスをしているカップルもいた。
ふいに彼とサン・ジェルマン・デ・プレの夜を歩いたデートがよみがえった。私もあんなふうに歩いていたはず。涙がこみ上げてきたのは、ギターの音色のせいなのか、それとも一人ぼっちのせいなのか、もう何が何だかわからなくなっていた。
冬が来る鐘をやさしく待つ川に