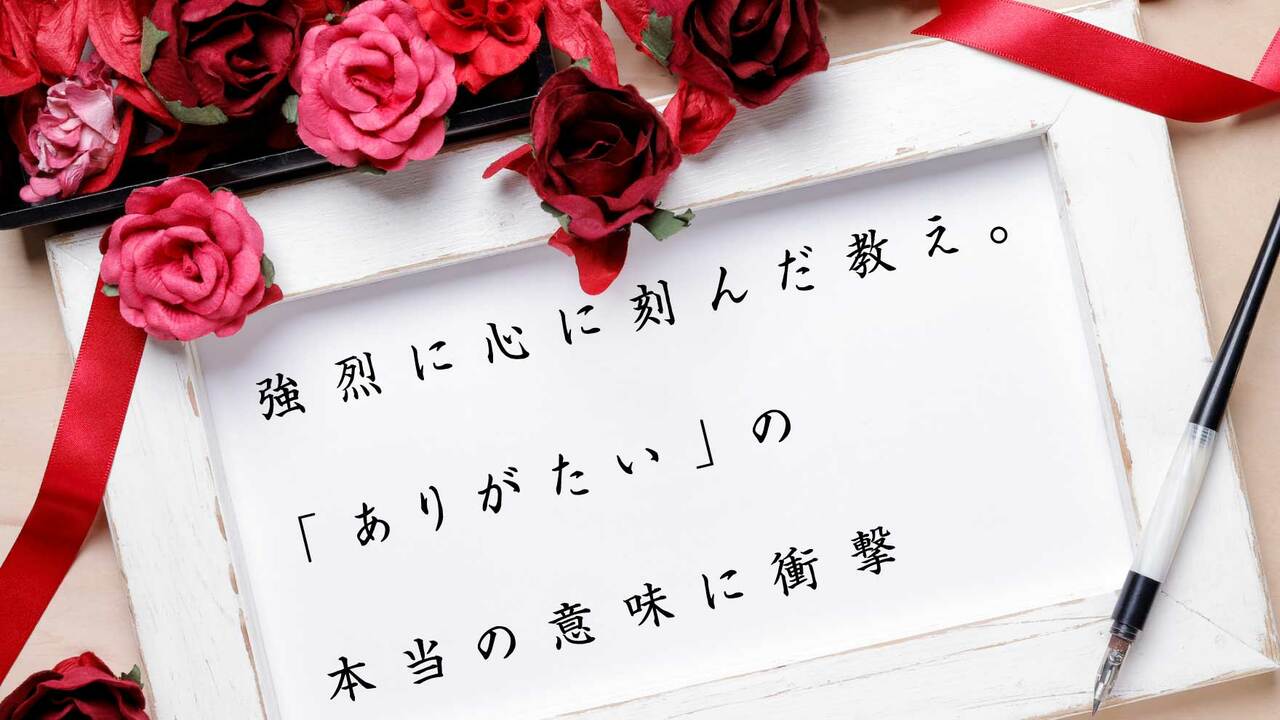魂が聴いた「母の説法」
魂で聞いたからこそ母の語った様々な説法をいまもよく覚えているのだ。毎夜の食卓で繰り広げられた母の説法、このことこそが私の「聴聞」だった。
寺や教会では僧侶や神父、牧師が、神様の教えの話をする。それを聞くことを「聴聞」というが、私は週に一回とか月に一回の聴聞でなく、毎日毎晩の聴聞をしていたのである。これで神様の求めるものが何なのかを多少とも理解できなかったとしたら、私は相当の馬鹿者だろう。
江戸時代の寺子屋では論語の素読が盛んに行われていたという。戦前の日本でも論語はよく読まれていたそうだが、そのほとんどは素読である。素読というのはただ論語の言葉を師の声に従って読むだけである。
「子、曰く……」という論語の言葉の意味を子供たちが理解したとは思えないが、この論語を何十回、何百回、素読するという経験が現在他国には見られないほど道徳心を持った日本人を作ったと考えている人は多い。
何故なら、何回も何年も繰り返し声に出して、また、それを耳で聞く論語の言葉は子供たちの体にも心にも染みこんでいる。そして、子供たちが人生の経験を重ね、様々な体験をするとき、いつの間にかその言葉の意味が自ずと腑に落ちてくる。
孔子が論語のなかで一番重視していた徳目は「仁」だという。思いやりとか、広く愛の心である。こうした内容をわからないながらシャワーのように浴びていくとき、それは聴聞そのものだったのだろう。その教えはいつの間にかその人のものになっていく。江戸の町人たちの教養や道徳心の高さがこうした寺子屋の教育に在ったのは間違いないだろうと感じる。
悪の教えもまた同じだと思うと怖いのだ。どんな言葉を聞くのか、誰の言葉を聞くのか、それが重要なのだろう。「話を聞き続ける」ということは重要な意味を持っていたと思う。
母の話は母が自ら多くの宗教書や哲学の本を読み、いくつもの勉強会へ出かけ、また高僧たちの説法を聴いて学んだことを伝えてくれたものだった。自らは決して神の教えも法も求めることのないアホ娘を持って、その娘の回心を実現させるという魂の約束のために母は一生自らが神の法、神理を学び続けたのである。
それはまた、もちろん母自身のためでもあったはずだ。そんな母に首根っこを摑つかまえられながら、いやいや、渋々私は話を聞き続けることになったのだ。私が天の存在を信じ、その教えをありがたいこととして受け入れ、神を敬う心を持つことができたのはまさに母の説法を聴聞したお蔭なのである。
私の回心への道はあの幼い日に聴いた母の唄う「誰が風を見たでしょう……」からすでに始まっていたのだ。