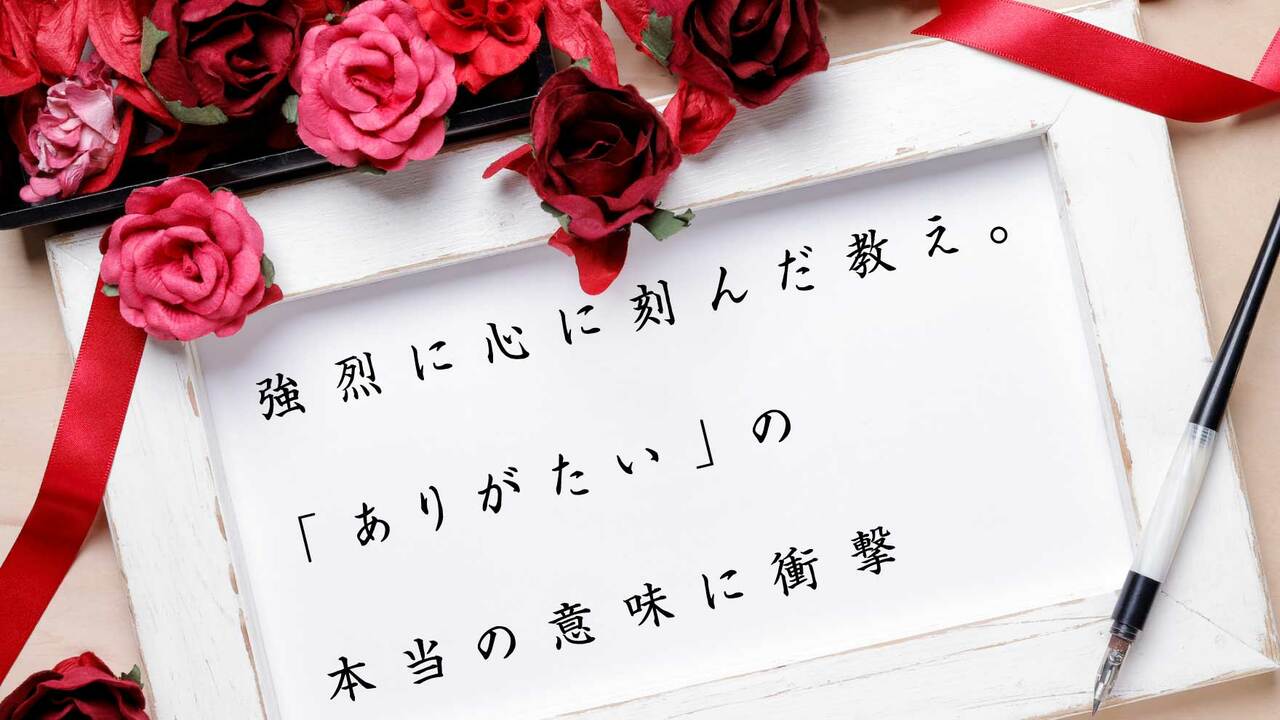【前回の記事を読む】ふと脳裏に浮かぶ「エミリー・ディキンスンの詩」の本当の凄さ
魂が実るとき外見の飾りは不要に
春から夏にかけて緑や草花の美しい色彩に彩られていた庭が秋になり冬が近づいてくるとき、瑞々しかった緑の葉や美しかった花々は散り落ちて、みすぼらしい褐色の世界になる。だが、よく見るとみすぼらしく見える木々のあちこちに固い毬に包まれて種や実が成熟しているのがわかる。
エミリー・ディキンスンのこの詩を読むとき、私が感じるのは次の新しい命を生む大事な種や果実が実るとき華やかで美しい花や瑞々しい緑の葉といった、木々を彩る美しい装飾はもういらないのだとしみじみと感じている彼女の感性である。
そう、庭の草花や木々だけでなく、人の魂が実るときも美しい黒髪も華やかなバラ色の肌や元気な肉体はもうなくなっているのだとつくづくと感じさせてくれる。それでいいのだと感じさせてくれるのだ。
老人の肉体がいくらみすぼらしかろうと、そのなかにある心や魂が無事に成熟していたとしたら、きっとそれで人としての本当の目的や役目は果たされているのだろう。長い年月を様々な経験を積み、様々な思いを感じながら生きていく先に、人も植物たちと同じように内部に実らせていくものがあるはずだと思うとき、こうしてただ生きてきただけで、大きなことや立派なことは何もできなかったと思えるこの人生も素晴らしいと思っていいのだと感じられる。
一生を家族に囲まれて、もしかしたら少々病弱で、多くの経験もせず亡くなった女流詩人を、私は多少不幸な生涯と感じていた節があった。現代的な感覚で言ったら、まるで隠者のようにひっそりと人生を送った寂しい人と見える。
だがこの詩の意味をしみじみと感じたとき彼女は決して弱くもなく、もちろん不幸でもなく、日々の生活のなかでの深い観照によって自分の人生の意味を理解し、おだやかに受容した賢い人だったのだろうと感じるようになった。
ひっそりと社会の片隅にいるように見えて、その実、人生の約束である魂の成熟を無事に完成させた人だったのではないだろうかと感じた。決して声高でない彼女の詩の美しさはそうでなければ決して表現されるものではないだろう。
そして発表されることも誰かに読まれることもなく、もちろん評価されることもない詩を千七百篇も書き続けていた人だと思うとき、なんと勁つよい、己を信じた人だったのかと畏敬の念を覚える。
それに実際のところ、彼女は生涯、戦いの中で死んでいくことを決意していたという。いまは、エミリー・ディキンスンは自分の人生の意味をよく理解した素晴らしい知性であり、とても幸せな人だったのだろうと思うようになっている。