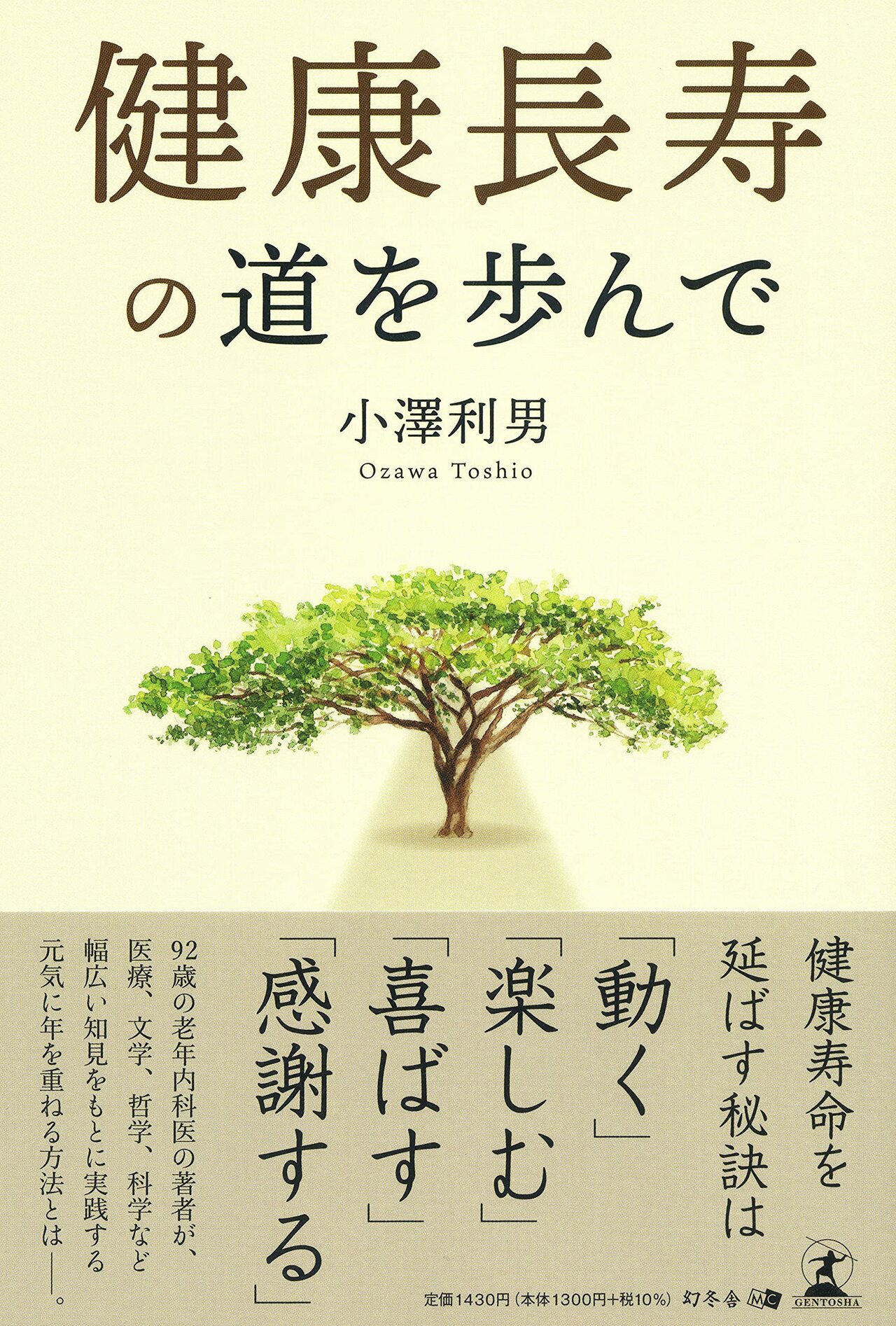・剖検重視。亡くなった後、剖検を行うことは、死因を明らかにして臨床を反省することになります。画像診断が全くなかった当時、先生は徹底して剖検にこだわり、どんなに忙しいときでも剖検に立ち会うようにしました。先生の在任中の剖検率は、平均八十六パーセントでしたが、これは世界的に見ても高率でした。
・東大病院は内科が第一、第二、第三、物療内科と四つありましたが、先生はこれを統一して臓器別専門化を図ろうとされました。だが時期尚早で実現せず、第三内科のみで専門化を図りました。
・医学部学生が卒業までに患者を診る機会のないのを憂え、ベッドサイドティーチングを取り入れて、学生が直接、患者を診るシステムを導入されました。
・在任中に、神経内科学と老年病学の講座を新設しました。神経内科は、それまで精神神経科として精神科に入れられていました。一方、外国では早くから独立して実績を上げていました。先生は我が国における神経科の独立を広く訴え、神経内科の学会を創設しました。これは臨床医学において大変画期的な実績でした。
・先生は内科医の能力向上のため、内科学専門医の資格を主張されました。これは後に内科専門医、認定医という学会の資格導入に発展しました。
・学会発表では、症例報告でも必ず予行をさせてきびしく評価しました。春の学会シーズンでは、内科講堂を借り切ってすべての発表の予行を行い、先生ご自身も内科学会の一般演題で発表されました。
・先生のライフワークとなる研究は、恩師である呉健教授の衣鉢を継ぐ自律神経であり、専門分化が進む各研究室でも、自律神経の研究を奨励されました。やがてその業績は学士院賞恩賜賞につながり、文化勲章を授与されることになりました。
・先生の最終講義は、八百二十四回目の臨床講義となっています。その表題は「内科臨床と剖検による批判」というもので、大変含蓄があり感銘を受けました。そのなかで先生は、十六年間在職中の誤診率は十四パーセントだと言われました。これが一般に知られることとなり、医師はその低いのに感嘆しましたが、患者の方はその高いのに驚いたそうです。
先生は最期に「書かれた医学は過去の医学であり、目前に悩む患者の中に明日の医学の教科書の中味がある」という名言を述べられました。
六十歳で定年となり、以後虎の門病院院長に就任されました。
ここに勤務する内科医師はほとんどが第三内科出身で、医療レベルは最高でした。
先生はさらに川崎溝の口に「回復期・慢性疾患治療センター」を設立されました。
そこでは外来は行わず、本院で治療を受け、回復途上期にある患者、リハビリテーション訓練を要するものなどが対象となります。
急性期と慢性期とをこうして分けて医療の一貫性を図ったことは、将来を見据えた画期的な体制でした。