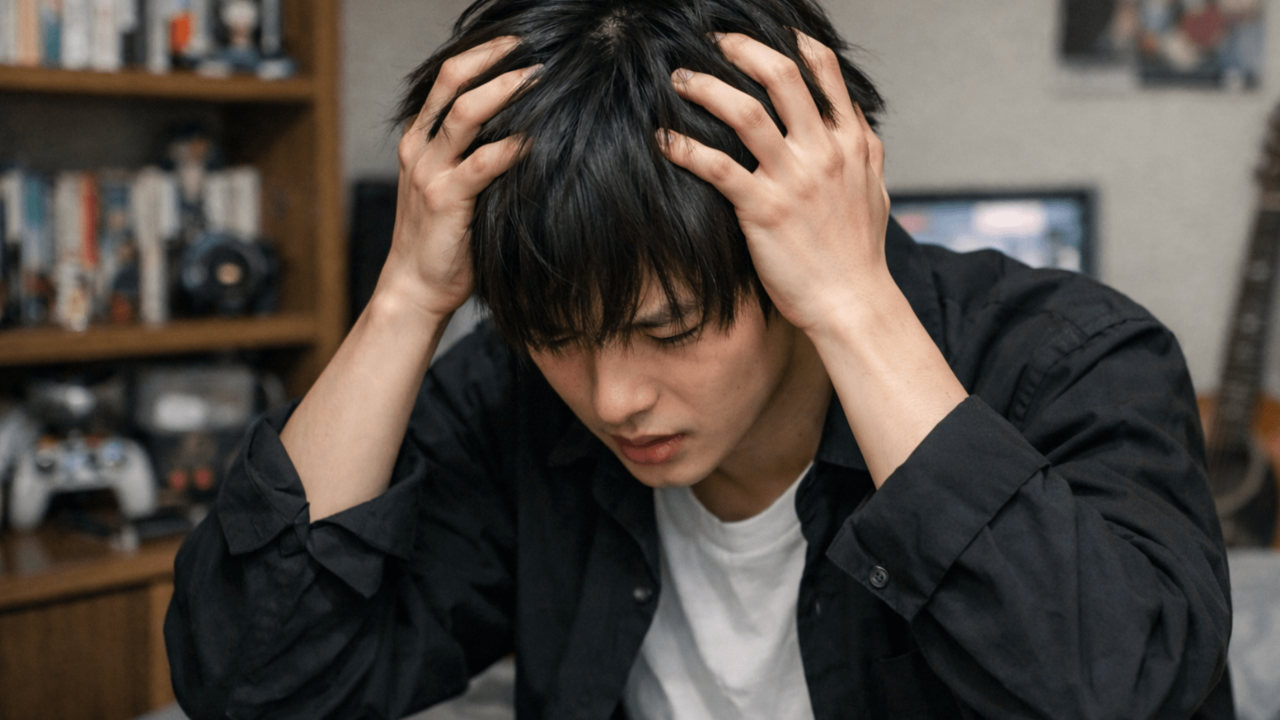「怪我の治療で離脱した先輩は、そのままもう、コートにはもどってこなかった。バレー部の人たちは、けっこう説得したらしいけど……もう気持ちが離れてしまったからって、どうしても首を縦に振らなかったみたい。それで、バレー部の人たちもあきらめた」
「だから……怪我の原因をつくった満田さんを恨んで、こんなことしたっていうの?」
やっと出てきた声は、どうしようもないほどにかすれ、震えていた。
「復讐っていったら、それしかないじゃない」
「先輩は、だれかを恨んで復讐なんかしないよ! それに、おかしいよ! 怪我で部をやめたのは、去年のことなんでしょ!? なんで、今ごろになって復讐なんかするの!?」
「そんなの、わからないよ……」
「信じないよ。わたし、ぜったいに……。マオ、今のこと、直接先輩からきいたの?」
「いや……そうじゃないけど」
「マオも! マオも……信じてるの? 先輩がそんなことしたって!」
うつむいたマオの唇が、そんなこときかないでよ、と動いたのがわかった。マオは、それ以上もう、なにも言わなかった。
わたしのまわりからすべての音が消えた。クラスメイトたちが、声をかけながら、わたしたちの横を通りすぎていく。その声も、教室のざわめきも、なにひとつ聞こえない。
どのくらい、そうしていたのだろう。なにかをぽつんと言って、マオが離れていった。
クラスの全員が、整然と自分の席につきはじめている。ようやくわたしは、ホームルームの開始を告げるチャイムが鳴ったのだということに気づいた。