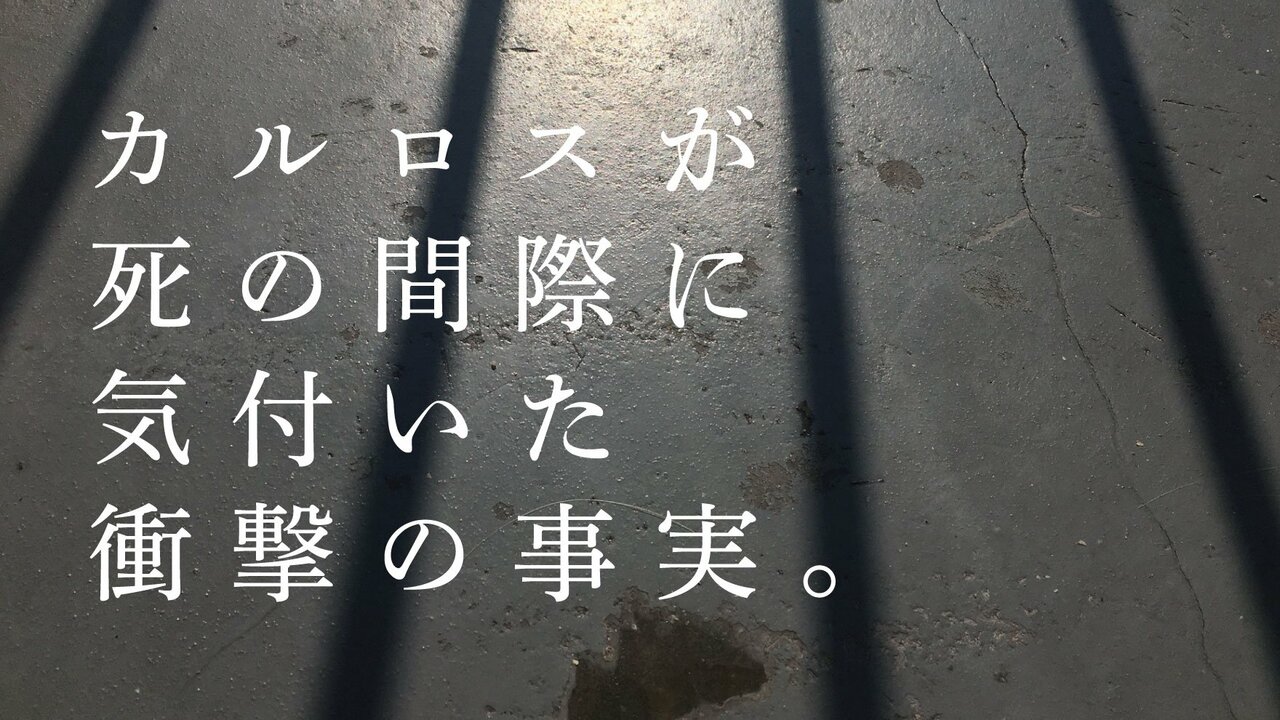第4章 フィオリーナからへロイーナへ
第二話 五ひきの子犬
半年前のことである。アメリカ合衆国(がっしゅうこく)のフロリダ空港に、ケージに入った五ひきの子犬が到着した。空港の貨物係の青年が口笛を吹くと、五ひきの犬はいっせいにワンワンと元気よく答えた。
「かわいい犬だなあ。国際ドッグショー会場行き……か。そうか、お前たちはドッグショーに出るのか。どうりでみんなきれいな毛並みをしていると思った」
青年は犬好きらしく、犬の顔や体つきを一ぴきずつていねいにながめたり、鼻先をなでたりした。しかし、青年は五ひきの犬のおなかに大きな手術のあとが残っていることには、気が付かなかった。そればかりでなく、犬たちが本当は、ドッグショーへ行くのではないことや、この後、犬たちに残酷(ざんこく)な運命が待っていることも知らない。
「おーい。南アメリカから来た荷物はよく調べろよ。コカインやヘロイン(15)が入っていることが多いからな」
仲間が声をかけた。
「だいじょうぶだ。これは生きた子犬だ。まちがっても麻薬は入ってないよ」
青年は笑いながら答えた。その日の夕方、空港の貨物受け取り所に一人の男が現れ、五ひきの犬を受け取った。男は一時間ほどして、郊外にポツンと建つ一軒家(いっけんや)の前に車を止めた。家の中では、数人の男が五ひきの到着を待っているところだった。
「早く、犬を見せろ」
男たちは犬のおなかの傷を見て大喜び、いっせいに口笛や歓声(かんせい)がわき起こった。
「こんなに簡単にうまくいくとはなあ。この前、大金をやって女に飲み込ませたのに、もう少しというところで失敗(しっぱい)したからな。あの女、飛行機の中で気分が悪くなって大事なブツを吐きやがったんだ。人間を使うより、犬を使った方がよっぽど簡単だな」
リーダーらしい男はそう言うと、少年のような顔をした若い男の方をふり向いた。
「さあ、やってこい」
若い男は、のろのろした動きで五つのケージをとなりの部屋に運び入れた。
「ぐずぐずするな。早くしろ」
どなられた若い男は、あわてて銃とナイフを手に、となりの部屋に消え、しばらくして、黒い液体の入った五個の袋を持って戻ってきた。ワッと歓声があがる。男たちは袋をかわるがわる手にとっては大喜びだった。その中で、若い男の顔だけが、血の気がなく、引きつった表情を浮(う)かべていた。
「犬の死骸(しがい)は絶対見つからないように、深く掘(ほ)って埋めとけよ」
リーダーがその青ざめた顔に向かって言った。黒い液体はヘロインという麻薬を水に溶(と)かしたものだった。カルロスに手術をさせた男たちはこの時の成功に味をしめ、その後半年にわたり、この残酷な密輸(みつゆ)をくり返すことになった。その黒い液体の入った袋はその日のうちにほかの州に運ばれ、その州の麻薬の売人がそれを買った。
麻薬を密輸したグループは多額の代金(だいきん)を手に入れ、それを仲間の銀行に預けた。その銀行に預けたお金は、麻薬ギャングのボスがぜいたくな生活をしたり、人を殺すための武器を買うのに使われる。ボスの中には、一つの国と同じぐらいの財産を持つ者までいるといううわさだった。