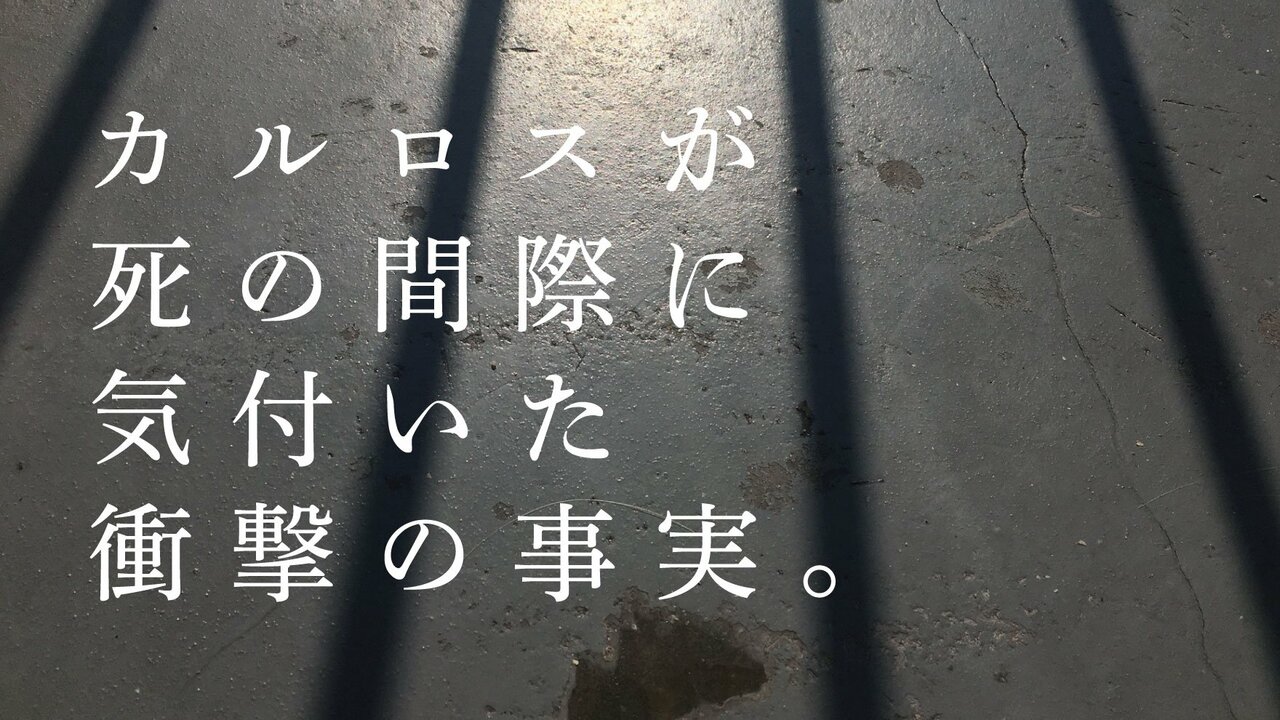第一章 二人の少年
第一話 農園の少年
「フランシスコ。もうすぐ、子犬が産まれるよ。母さんを呼んできて」
父のあわてたような太い声が聞こえた。フランシスコ・ミランダは、大急ぎで家へ走っていき、母親の手を引いて納屋(なや)に戻(もど)った。
明かり取りを閉めて暗くした納屋には、黒っぽい色の大きな母犬が横たわっていた。父の大きな手が、ゆっくりと母犬のおなかをさすっている。
「さあ。産まれるぞ」
父の声に合わせたように、最初の子犬がすべるように落ちてきた。フランシスコは、少し離はなれた所から身動(みうご)きもせず、初めての犬の出産に見入っている。
信(しん)じられないほど小さな子犬が、とても弱々しく、愛(あい)らしく、大切なものに思えた。一ぴき、また一ぴき、子犬は次々と産まれた。
産まれた子犬は、八歳になったフランシスコが世話をさせてもらえる約束だった。子犬は全部で七ひき産まれた。
翌日、子犬にさわってもよいと言われたフランシスコは、子犬たちが平等に母乳を飲めるよう、せわしなく場所を変えて、母のマリアに注意された。
「フランシスコ、そんなに子犬を動かすものじゃないのよ」
お乳は二列にきれいに並んでいたが、フランシスコにはどう見ても、頭に近いお乳の方がたくさん出そうに見えたのだ。
フランシスコのやり方がそれほどまちがっていなかったのか、子犬はどれも同じ大きさに育った。フランシスコの母マリアは、小柄(こがら)でふくよかだったが、腕(うで)などは、さわるとはね返されそうに固かった。
おだやかな性格で、感情をむき出しにするようなことは決してなく、叱(しか)るときにも分かりやすい言葉で、叱る理由を説明してくれた。
フランシスコは、そんな母から叱られるのが、少しもいやではなかった。父のロレンソは大学で植物学(しょくぶつがく)を学び、生まれ育ったこのコーヒー農園に戻ってきたが、本当は大学に残って研究者になりたかった。
コーヒーを栽培(さいばい)するよりも、研究する方が向いていた。フランシスコは一言(ひとこと)で言えば、性格は母親似、顔は父親似だった。色白(いろじろ)で、興奮すると、ほほがピンクに色づいた。
子犬が産まれて二カ月がたったころ、マリアが言った。
「フランシスコ。七ひきのうち一ぴきを、親戚(しんせき)にあげてもいい? その家には、フランシスコより少し小さい男の子がいて、子犬をほしがっているのよ」
「その家、どこにあるの?」
「遠い所だけど、会いたいときは会いに行けるわ。だからね、その子にあげる子犬を、フランシスコに選んでほしいの」
フランシスコは、その男の子に、自分が一番気に入っている子犬をあげることに決めた。その子犬は茶色と黒の境目がはっきりしていて、目鼻立ちがかわいかった。
子犬が三カ月になったある日、ミランダ一家は留守を使用人頭(しようにんがしら)に任せ、ロレンソの運転する車で、コーヒー農園の中の家を出発した。めざすのは、南東の方角にあるガルシア牧場だった。ガルシア家は、マリアの親戚にあたる。