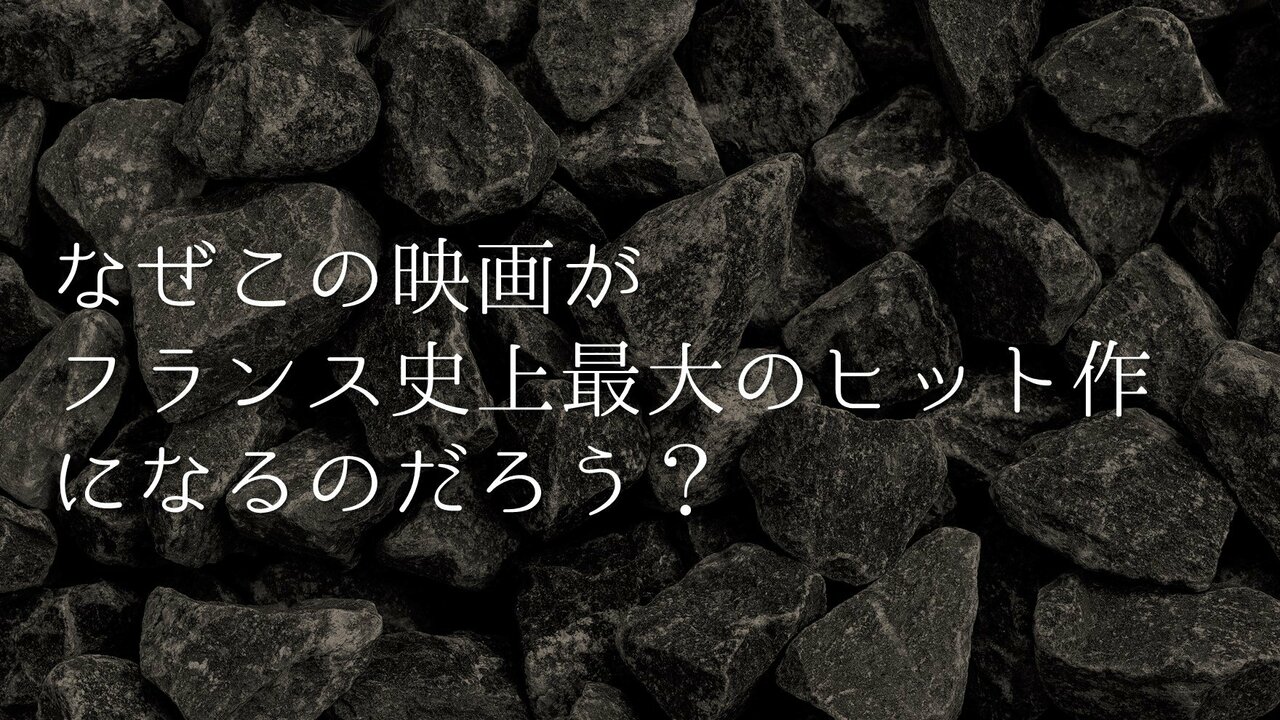2007年
もっと働き、もっと稼げ
フランス文学者の鹿島茂氏は『フランス歳時記』の九月の章でこう書いている。九月のフランスでは、ヴァカンスでリフレッシュした爽やかな顔よりも、これから長い冬(労働の季節)に向かっていかなければならない憂欝な顔のほうに多く出くわす。同じくボードレールの『秋の歌』にはこうある。
「私の身うちに還って来ようとする、冬のすべて―怒り、憎しみ、慄(おのの)き、恐怖、無理強いされるつらい仕事。そして、地獄とばかり北極にとじこめられた太陽さながら、私の心はもはや、赤く凍った塊りでしかないだろう」
フランス人にとって、仕事とはかならずや「無理強いされるつらい仕事」なのである。ワーカホリックの日本人の対蹠点(たいせきてん)に彼らはいる。ほんとうにそうだろうか。
フランスの法定労働時間は週三十五時間で先進国の中でも突出して短いと言われている。二〇〇〇年の社会党内閣時に週三十九時間から短縮した。約十日ある祝日を引くと年間所定労働時間は千六百時間である。
日本の企業はおそらく千八百時間の半ばから後半だろうから圧倒的な短さである。当時十%を超えていた失業率を改善するために、ワークシェアリング的考え方で導入したが、企業は雇用を増やすより生産性を改善することで対応したため失業率改善にはあまり効果がなかったと言われている。
フランスは月給制の社員がほとんどで、三十五時間の移行に際し、労働組合からの抵抗でほとんどの会社が給料を下げられずに労働時間だけ短縮した。つまり実質十%を超える賃上げと同じ負担を会社側は強いられたのである。
政府は企業負担増大の代償措置として①政府からの補助金を出した②労働時間の弾力的運用を認めた③その後数年間賃上げをしないとする労使間の協定を認めた、ということだ。結果的にこの三十五時間制によって多くの労働者は余暇や時間的ゆとりを得たという。それだけ見れば良いことに思えるが……。
ところで週三十五時間を超えて残業させる場合である。法定の最高労働時間は一日十時間、週四十八時間、年間二百二十時間だ。このいずれかを超えて残業させてはならない。
この範囲での残業に対する割増率は週三十六時間から四十三時間まで(残業の算定は週単位)は二十五%、それを超えて四十四時間からは五十%である。もし残業合計が暦年で年間二百二十時間(月平均すれば十八時間ちょっと)を超えた場合は、手当に加えて同じ時間の補償休暇(つまり後で休ませる)を与える義務がある(二〇〇七年当時)。
このように残業させると企業のコストが高くつくせいもあって労務費コストに占める残業手当の割合は少ない。つまり残業そのものが少ない。従って、日本のようにリストラの第一段階が残業削減という手法は成り立たない。
いつも忙しくて決算期日が間に合わないとあたふたしている経理の部長に「それなら残業させて間に合わせればいいではないか」というと「ミネギシさん、残業させるくらいなら派遣社員を雇ったほうが安いよ」という返事。
あれだけ忙しい忙しいと騒いでおきながら、午後五時になると皆一斉に職場を後にする。“ア・ドゥマン、ボン・ソワネ(またあした、よい晩を)”と言ってさっさと家路につく。日本人の私からするとあきれる程見事な光景である。