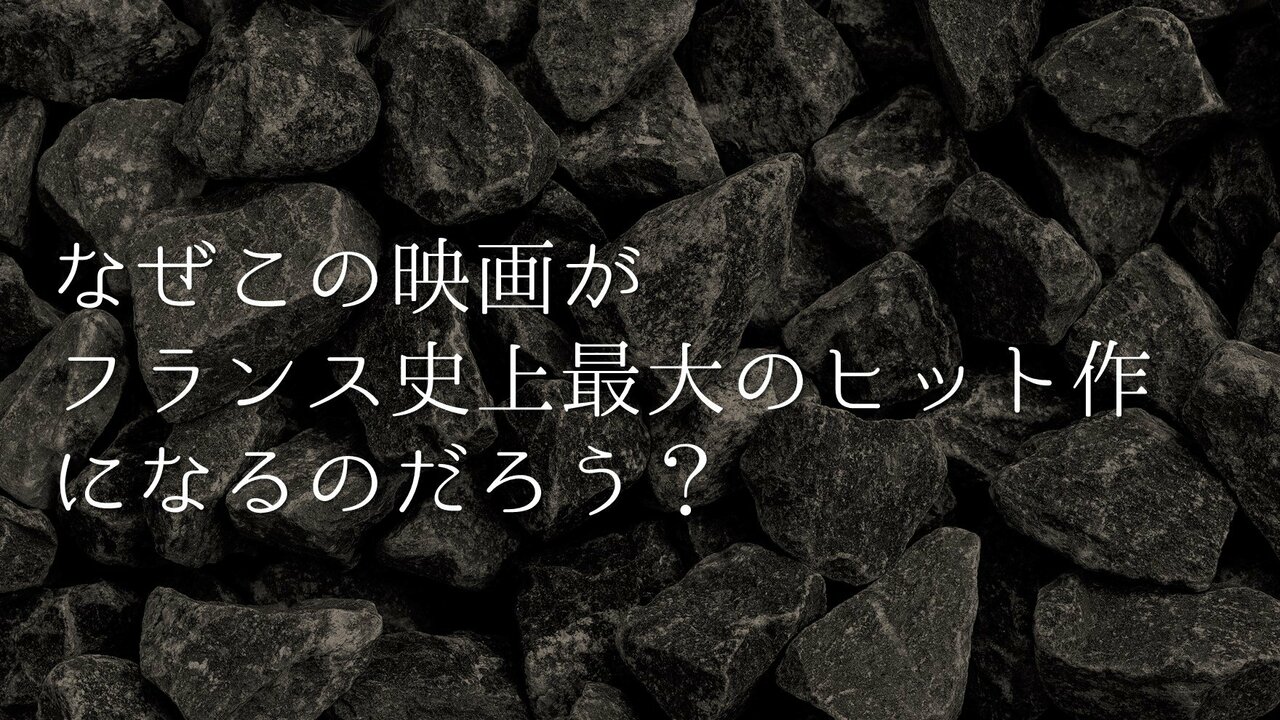2008年
『Bienvenue chez les Ch’tis ようこそ、シュティの国へ』
映画のストーリーは、南フランスのプロヴァンスの郵便局員が転勤を命じられ、北フランスのある村へいやいや赴任して、そこでどたばた人情喜劇が展開するというもの。いつものようにパリ発行の日本語新聞『OVNI』の助けを借りると、
ダニー・ブーンが監督主演した映画作品『Bienvenue chez les Ch’tis ようこそ、シュティの国へ』が、フランス全国封切り一週間で観客動員数三百五十万を超えるという、史上最大のヒットとなった。ch’tis(シュティ)あるいはch’timi(シュティミ)は、フランス北部ノール県やパ・ド・カレー県に住む人、あるいはその人たちが話している方言を指す。
ということだ。ch’tisというのはかなり強烈な方言らしく、マリー=アニックも「私にも何を言っているのか良くわからない言葉があったわ」というくらい。もっともフランス語そのものがわからない私にとっては方言も標準語もいっしょだが。
そして映画を観終わった私の感想は、「なかなか愉快な映画ではあるけれど、なぜこの映画がフランス史上最大のヒット作になるのだろう?」というものだ。この映画の背景について『OVNI』はこう続けている。
この地方は以前は炭鉱で栄え、ポーランドやイタリアなどから多くの移民がやって来て辛い仕事に従事していたところだ。ところが最近は炭鉱が閉鎖され、フランス人が「ch’tis」と聞いて頭に思い浮かべるのは、ボタ山、灰色の街、貧困、アル中、雨、風、寒さ、とネガティブな面が多かった。ch’tisのひとり、ダニー・ブーンはシナリオも担当し、この地方に生きている人たちのユーモアや厚い人情に光をあてることに成功した。
映画を観た翌日、会社の食堂で経理のカトリーヌに「『Bienvenue chez les Ch’tis』という映画観た?」と聞くと「うん、観たよ」という返事。そうかみんな観ているのか。「私も観たけど、フランス語がわからないから内容もよくわからなかった」と言うと「うん、そうでしょうね」と、しょうがないわよねえという表情。
別の日の食堂、経営企画のジャン=フランソワに同じ質問をすると「うん、僕も観たよ、面白かった。上映二週間経つけど観客の動員は衰えないようだよ」と言う。「ふ〜ん、私も観たけど、あの映画のどこがフランス人に受けるのかなあ」と聞いたら、彼は次のように説明してくれた。
「まずフランス人はああいったコメディが好きだね、それに南フランスと北フランスをうまく対比している」
「ふむふむ」
「あの映画の舞台の北フランスは昔、鉱山の街で、炭で真っ黒くなって働く人々のイメージがあった。そして近年は鉱山の閉鎖などで失業者があふれている、暗いイメージがあるんだよ。そしてあの地域の方言には強烈なアクセントがある。僕は通りすぎただけで住んだことはないけど」
「テレビのニュースで、ベルギーでもこの映画は大ヒットしていると報じていたけど」と私。
「うんそうだよ、ベルギー人の多くはフランス語を話すし、あの映画の舞台のすぐ隣はベルギーだからね、皆、親近感を持つだろう」
「ああ、そうかあ」
「あの映画は二つの“泣く”を描いていると思う。まず転勤を命じられたときに、行きたくない地方だと言って泣く、そして赴任して、また戻るときになったらその人情に触れて離れたくないといって泣く」
「へえ〜、ところで、あの村は本当にあるの?」
「あるよ。あの村の名前は海の後ろという意味だけど、他にスラングで“きらい”という意味もある。それは転勤で行きたくないということを含意していて面白い」
「ほう」
そして彼はこうしめくくった。
「それにほら、フランスはいま明るい話題がないだろう? サルコジの人気は低下の一途だし、物価の値上がりもひどいし、フランスだけではないけれど信用不安で株も暴落。だからこそフランス人はせめて明るい映画を観たいと思ったのではないかなあ」
う〜ん、なかなかうがった見方だ。テレビではこの映画のヒットにあやかった商売も出現していると報じていた。ch’tisの文字をあしらったTシャツ、ch’tis語とフランス語を対比した辞典などだ。
レンヌの市内でそれらのグッズを探してみたが、まだそこまで流行していないようで見つからなかった。