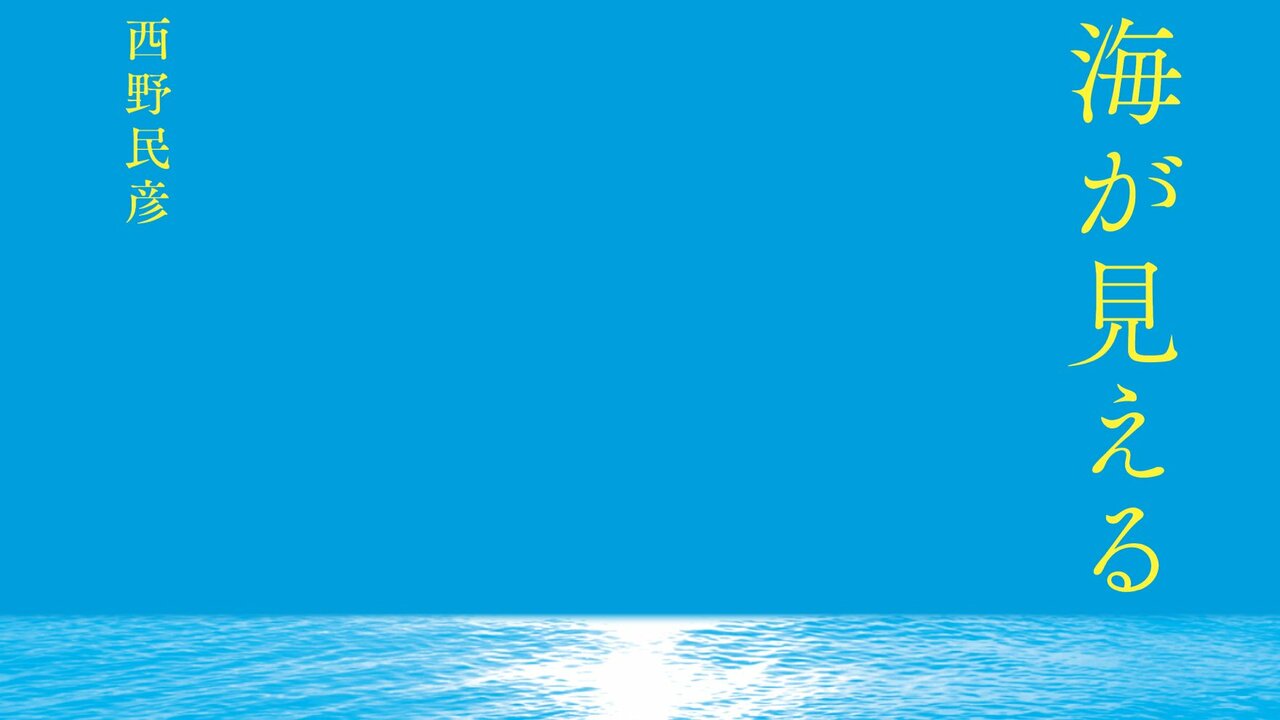第一章 3人の出会い
昭和60年、勉はこの春から公立高校に通っている。
望んで入った高校ではないが、こんな世の中で、たとえ二流か三流でも高校に行かないという勇気もないので、贅沢なことかもしれないが、やむを得ず通っているというのが正直なところだ。
この高校は各学年約400人全校生徒1200人ほどで男女共学である。残念ながら学校は予想通りだった。校舎は貧相で、威厳も風格も伝統のカケラも感じられず、中身はこれに正比例していた。
通学路には、わりと桜の木が多く、満開の時期は過ぎてはいたものの、花はまだ咲き誇っていて、風がそよぐと花びらが散って降りかかってきた。
大体のところ、勉は桜が好きではなかった。勉には桜の花が咲くころに、幼少期からろくなことがなかったからである。
入学したての落ち込んでいる奴に、誇らしげに咲かせた花を見せつけ、おまけに、パッパラパッパラと花びらまで降り掛けるアホ桜めが!
俺は”遠山の金さん”とちゃうぞ!と思ったが、桜を恨んでみても仕方がなかった。しかし、桜の花が目に入ると、勉は無性に気分が悪かった。
入学式の翌日、新入生の全体集会で、学年主任の水田という古文担当教師が、学校生活について訓示したことがあったが、その時に言ったことに勉は怒りを覚えた。
「お前たちには優れた者は誰もいない。せめて集団で優れたものになれ!」
言われなくても、優れた者でないことぐらいは、こちとらにも分かっているが、こうもはっきり侮辱するように言われると、勉も心底から腹が立った。
勉は思うのだった。そもそも、入学したての生徒に向かって、誰も優れた者はいないと言うとは何事だ。優れていない生徒であっても、励まし教え育てるのが教師じゃないか。
百歩譲って、新入生に活を入れるために言ったのだとくみ取っても、”優れた者は誰もいない”と言うのは侮辱以外の何ものでもないと思うのだ。
水田の言う優れた者とは、試験の成績の良い生徒のことなのだろう。その優れた者はいないと言うが、中学校で勉強しなかっただけのことで、実は頭脳明晰という奴がいても不思議じゃないだろう。
もちろん、勉強しなかったのは、ほめられたものではない。しかし、頭の良い奴と試験の成績が良い奴を単純に混同していると勉は思った。
しかも、学年全体約400人という多人数の集団の全員がバカということはまずないだろう。それを「誰も優れた者はいない」と断じるとは何事だ。