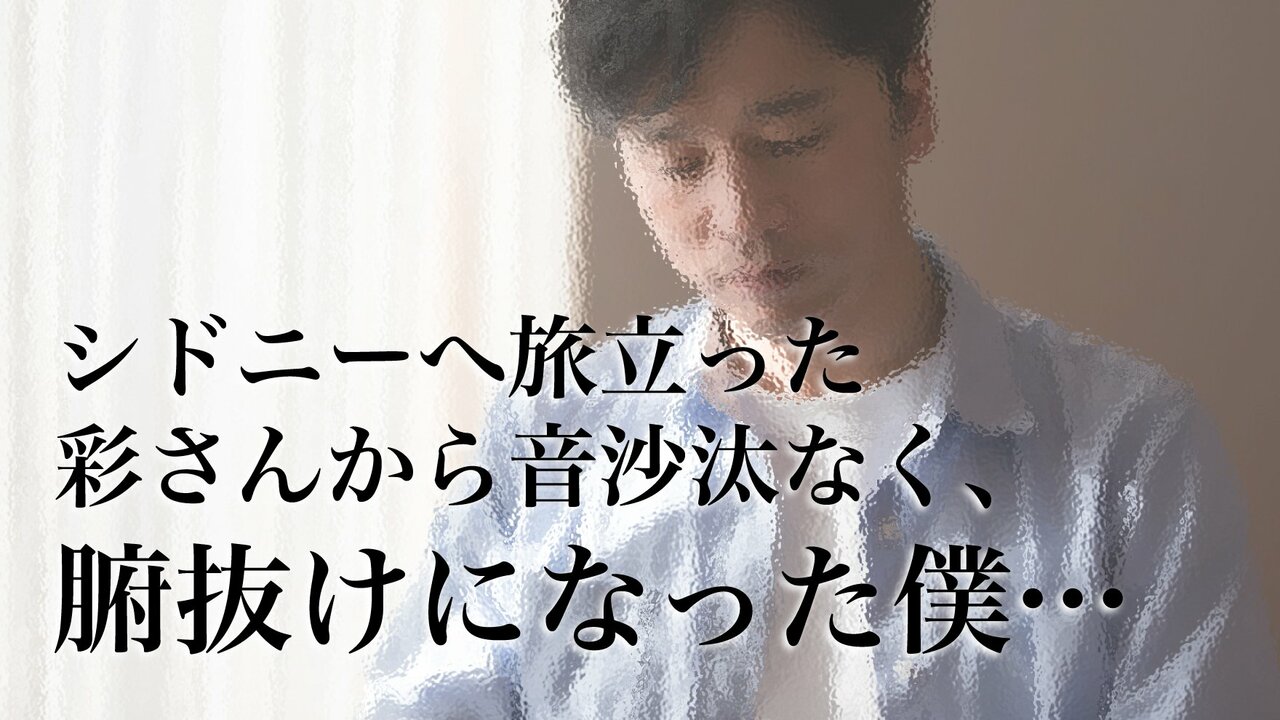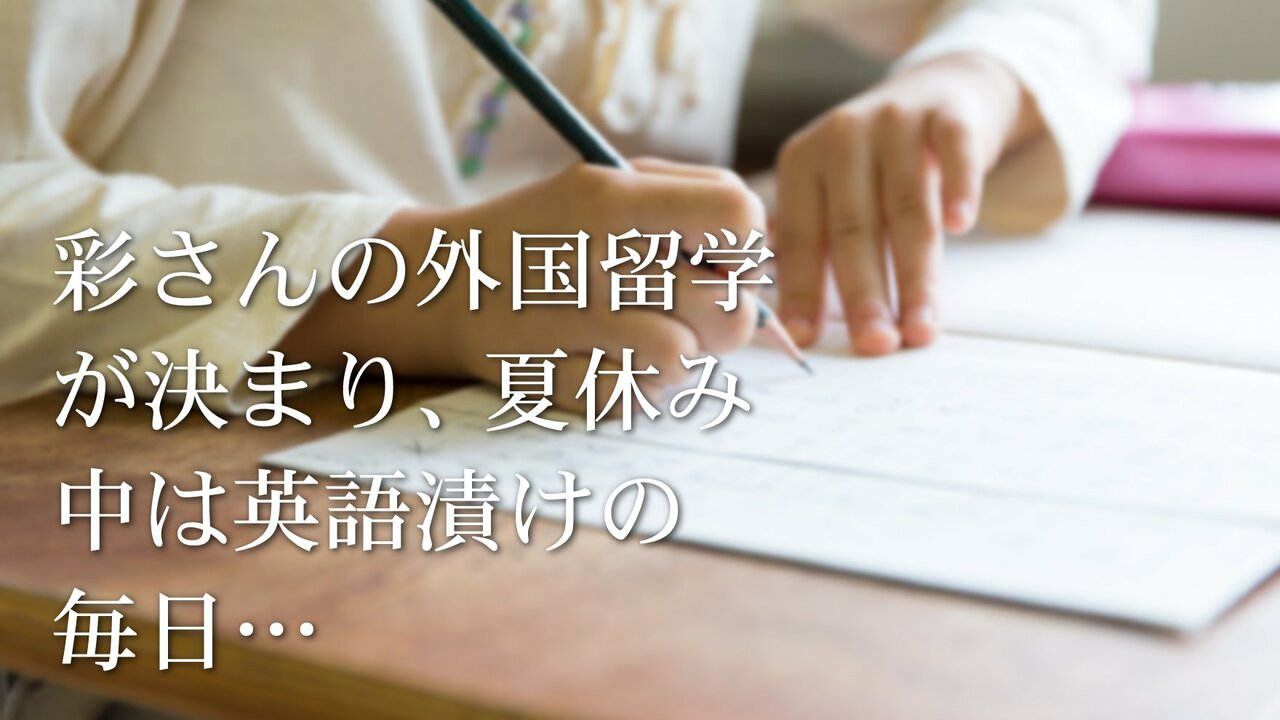さっきとはうってかわって、彩さんは妙に遠慮がちな声になった。外の雨はすっかりあがったのか、部屋は静寂に包まれている。
ただ、さきほどの思いがけない情事によって立ち昇った熱気が僕の体の芯を熱くしていた。自分の意に反して僕はしばし興奮状態にあった。
「彩さんと間違いを犯したら、僕は家庭教師を辞めなくちゃいけなくなるんだ。それどころか、下手したら警察に捕まっちゃうかもしれない。だから、本当にもう、セックスしたいとか言わないでよ」
しかし僕の言葉は暗闇に吸い込まれていき、彩さんには届かなかった。
「……彩さん?」
返事はない。耳を澄ますと、かすかな寝息が聞こえてきた。セックスはしないとなったら彩さんはすぐに寝入ってしまったようだ。
「マジか。本当に子どもみたいだな」
僕は苦笑しながら両手を頭の下に置いて、薄暗い天井を見上げていた。そしてぼんやり彩さんのことを考えていた。
彼女のことが気になっているのは確かだが、まだ中学生だ。冷静に考えれば、恋仲になるなんて非常識である。ただ、心の奥底にあるくすぶった感情の存在を思うと、どうしていいかわからなくなる。
そんなことを考えているうちに結局、僕もいつしか、自然に寝入ったみたいだ。目を開けると、朝日がカーテンの隙間から幾重にも細い光となって差し込んでいた。昨夜の嵐みたいな風雨は、嘘のように衰滅していた。
僕は彩さんに気づかれないようにそっと起きた。コンビニに行き朝食を買ってきて、ダイニングルームのテーブルの上に用意した。なんか慌ただしい土曜日だった。
でも、これで何とか僕は自分の責任を果たせたような気がした。安堵感すら覚えた。致命的な落ち度もないと思うから、後ろめたさはなかった。
続く…