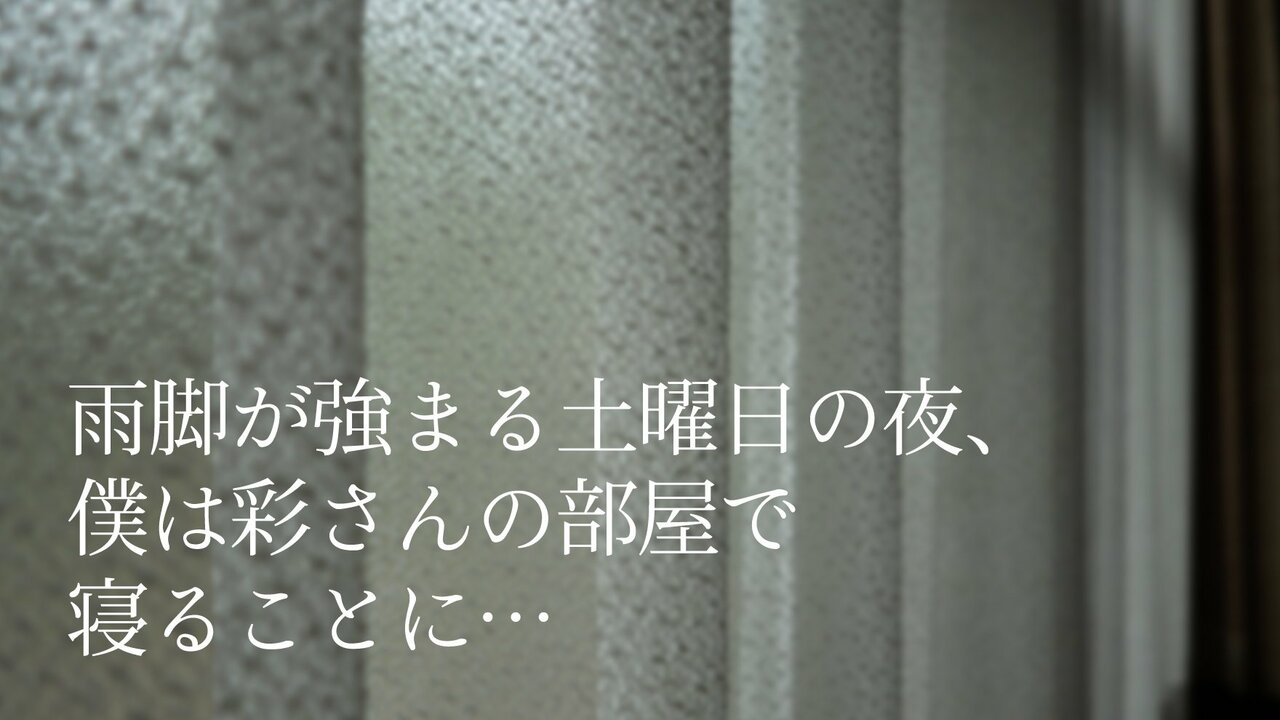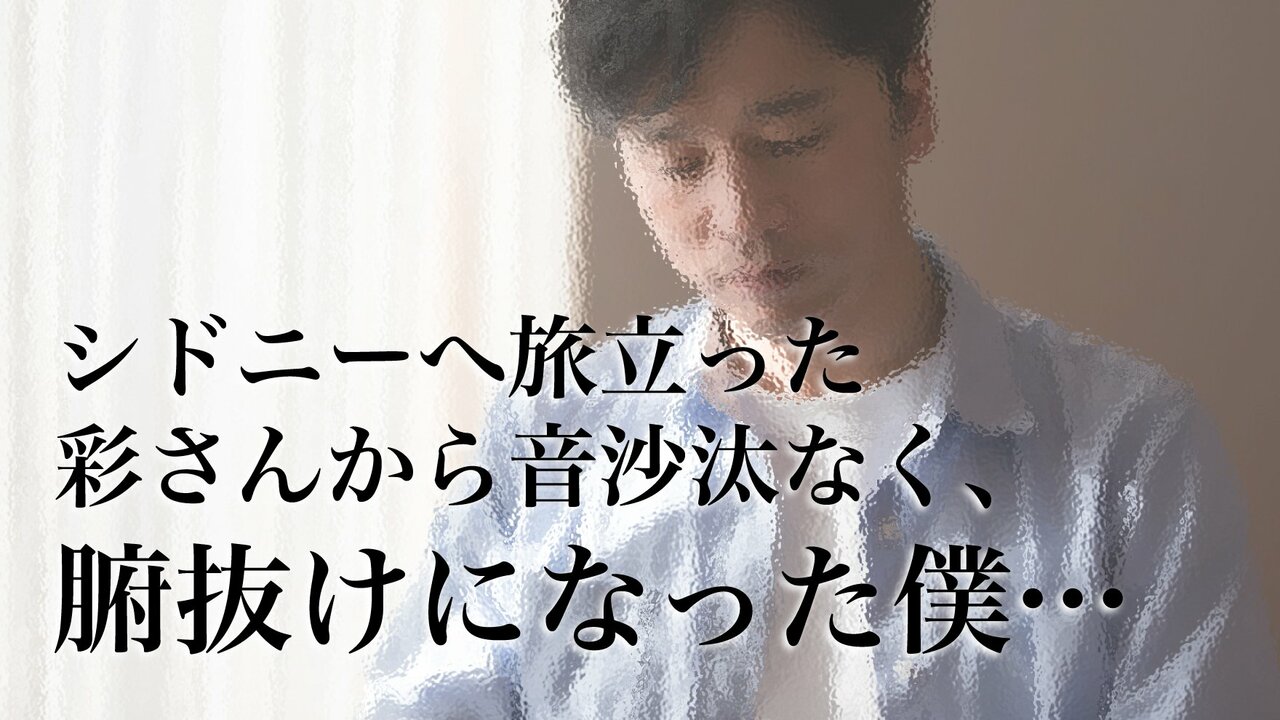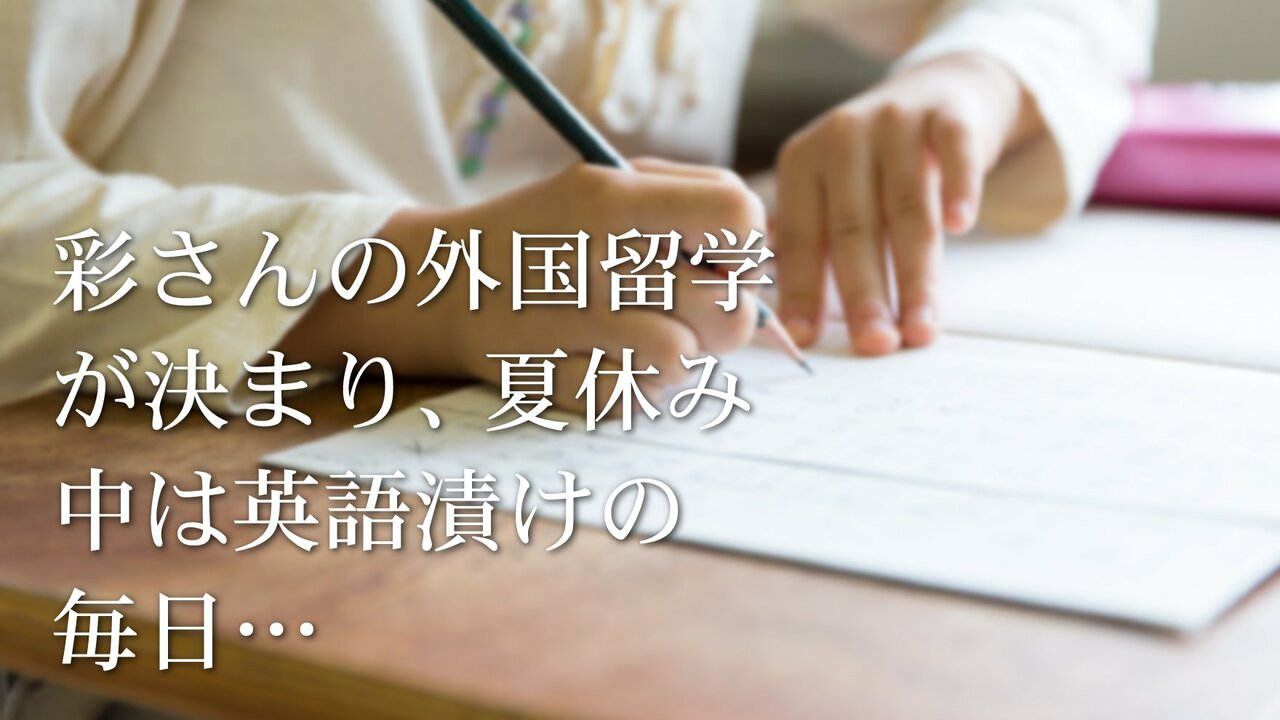【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
家庭教師
耳を澄ますと、雨脚が強くなってきたのか、窓を叩く音が盛んになった。
二人きりで過ごす初めての土曜日。無事に過ごせるのか。雨が激しくなってきたのが気になる。強い雨音がそこはかとなく、不安な気持ちを掻き立てた。
彩さんは、特にやることもないから早く休みたいと言い出した。彩さんは自室のベッドで寝るが、独りじゃ怖いから僕も一緒の部屋で寝てほしいと強く要求した。雨音が激しいから僕も落ち着かず不安を感じていた。
僕は彼女の要求を断る理由がなかった。彩さんの部屋は、十畳くらいのフローリングで、北西の隅にピンクのベッドが置いてあった。
ベッドには大きな枕と熊さんの縫いぐるみがあった。あとは、クローゼットに机、本棚などが並んでいた。意外に片付いていた。僕が来るのを予想して、綺麗にしておいたのかもしれない。
「あの悪いけど、蒲団を用意するから私のベッドの下の横で寝てくれない?」
「うん、まあ、それしかないよね」
僕は、彩さんの希望通り蒲団をベッドの下に敷いた。特にやることもなかったので、僕たちは早めに寝た。まだ、夜の十時くらいだった。二人はそれぞれの寝床に付いたが、雨の音が強く風も出てきたので、容易には寝付けなかった。
しかも僕が寝るのは、いつも十二時半くらいだったから、なおさらだ。彩さんも寝られないらしく、話しかけてきた。
「ねえ、あんた寝てる?」
「ううん。まだ時間も早いし、外がうるさいから寝られない。それに蒲団が変わると寝られないじゃん」
「そっか、たしかに。だったら、ねえ、そっち行ってもいい?」
「え、どういう意味?」
「そっちの蒲団に行ってもいいかっていうこと」
「それはまずいよ!」
「だって寝られないんだもん……うるさくて。あんただって寝られないんでしょ?」
彩さんは、甘えた声でそう言った。不穏な状況だ。やはり、同宿すべきでなかったのかもしれない。
多少の災難は覚悟していたが、いざ直面すると親との約束や大塚夫人の姿が走馬灯のように迫ってくる。変な罪の意識や不徳を感じないわけにはいかなかった。
「やっぱりまずいよ。彩さんは、中学生だし。僕は家庭教師でお母さんに留守を頼まれた身だから」
「何、わけのわかんないこと言ってんの! 怖いからそっちに行きたいって言ってるだけじゃん。あんた、頭おかしいんじゃないの?」
「いや、僕には責任があるから」
僕は少し意固地になっていた。そうすることで、自分の正当性を無意識のうちに守ろうとしていたのかもしれない。
「変なやつ! 女心がわかんないんだ! 女は優しい男には甘えたいんだよ……」
「わかるよ」
「わかってないよ」
彩さんの声が、ベッドから甘くささやくように聞こえた。ときどき怒るように聞こえたりもした。それが雨音のなかで奇妙に谺した。