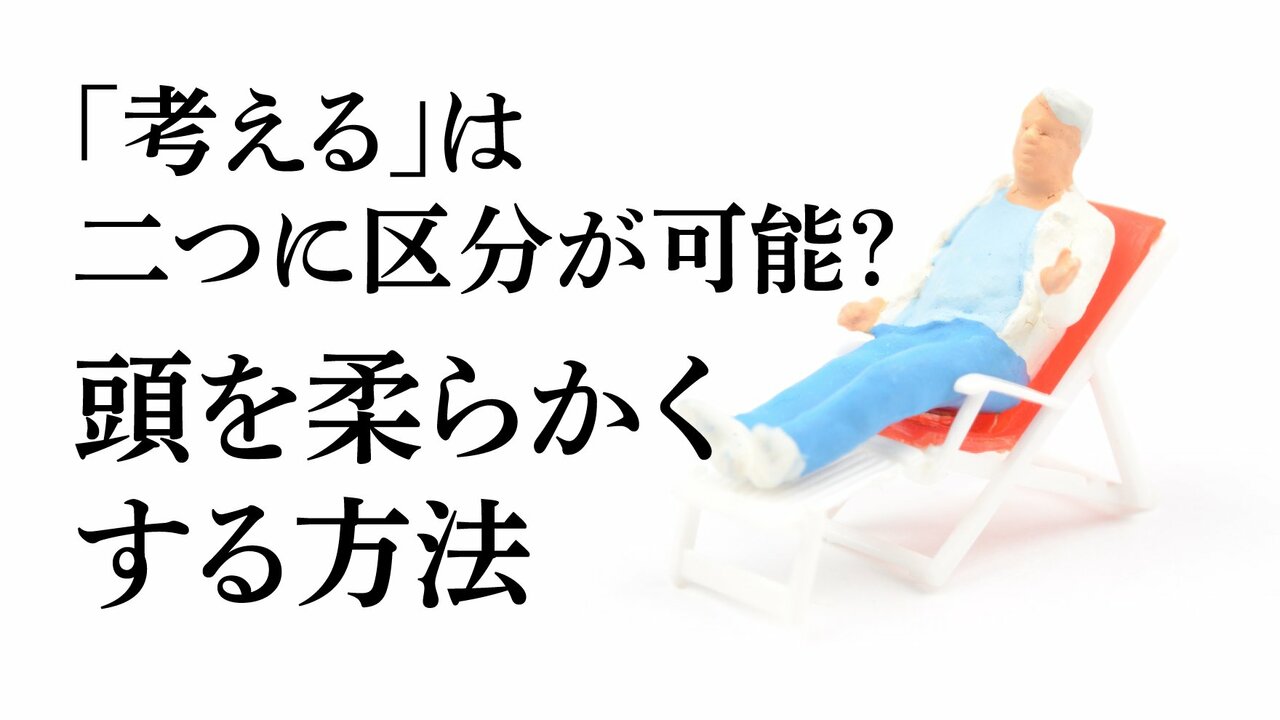血の糸
沖田刑事は、乱れた頭髪を更に掻きむしらんばかりにして、うず高く積まれた書類をめくっている。体から刑事としての気迫がほとばしっている。だが、いまだに、おぼろげにも事件解決の糸を掴み取るには至っていなかった。事件解決にはほど遠い、と沖田刑事は感じた。
ところが、10月6日。事件は急速に解明することになったのである。夜、、沖田刑事の自宅に、電話がかかってきたのだ。
それは、若い男の上ずった声だった。
「沖田刑事さん、俺は知ってるんです。若山洋子を殺した犯人を俺はしっかりと見ているんです。俺は、このことを知らせようか、どうしようか迷っていたんです。そして、今、決心して公衆電話でかけているんです」
「何! 本当か? あんたは一体誰だい? でたらめ言っちゃいかんぞ」
「刑事さん、刑事さんならよく知っている人なんです」
「何だって? まわりくどい言い方をしてからかうんじゃないぞ。最近になってやっと悪戯電話が来なくて良かったと思っているんだから。あんたの名前を言いなさい」