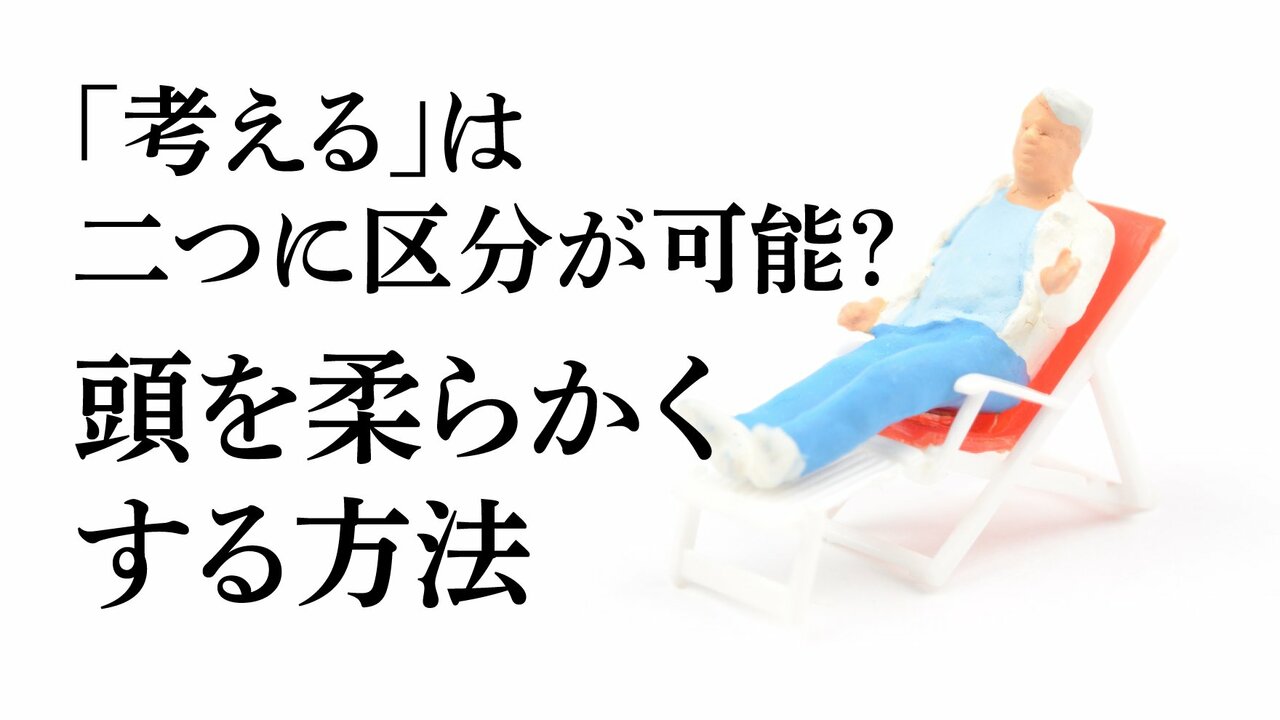でも、考えてみると、それが間違いでした。私は、子どもに対して、父であることを示したいのです。厳しさ、苦しさと同時に、確かな意思があり、そして努力すれば必ず達成できるということを教えたいのです。稔は、京都にある大学に入学することを夢見ておりました。だから、大学受験には是非とも合格させてやりたいのです」
「香村さん、あんたの真意は十分にわかったとは言いがたいが、香村さんがそこまで言うならば、俺も男だ。約束しよう」
「沖田刑事、本当にありがとうございます。私は、真の刑事として、稔の父親として、心から感謝します。来年の4月になったら、香村良平は、香村稔と二人で、鉄格子の部屋へ入るつもりです。だから、息子の方も、4月まではそっとしておいて下さい」
「え? 香村刑事、刑事は今、何と言ったんですか?」
「息子と二人で鉄格子の部屋に入ります。だから息子の方も4月まではそっとしておいて下さい、と言ったのです」
沖田刑事は、胸が締め付けられるような思いがした。思いがけない香村の言葉だった。あまりの驚きに声を出すこともできないでいると、香村良平は、花瓶の小さな白菊を見ながら言った。
「本当は、私は、二宮啓子殺しの犯人を知っているんです。沖田刑事にも多分覚えがあろうかと思いますが。じつは、二宮啓子のアパートにあったクシャクシャになった煙草が知らせてくれたんです。
噛みくだかれた煙草──それは、私の息子が殺したという証拠でもあったんです。稔は、興奮して怒ると、何でも噛む癖があったんです。煙草を噛むこともありました。クシャクシャに噛みくだかれた煙草は、息子の部屋でもしばしば見い出したものなんです。稔は、何か気に入らないことがあると、食事もせずに部屋に閉じこもりました。時には子どもの部屋から何かを叩きつけるような音、破壊する音が聞こえて来ました。また、居るのか居ないのかわからないような時もありました。こんな翌日には、息子の留守の間にそっと部屋を調べたのです。すると、やはり、噛み砕かれた煙草があったのです。息子からはどんなにバカにされても、私は稔のことが心配で、じっと生活ぶりを見ていたのです。
沖田刑事、今となってはもう遅すぎるかもしれません。けれども、私は、父として私の手で息子に手錠をかけたいのです。それが親子をつなぐ〝血の糸〟だと思います」