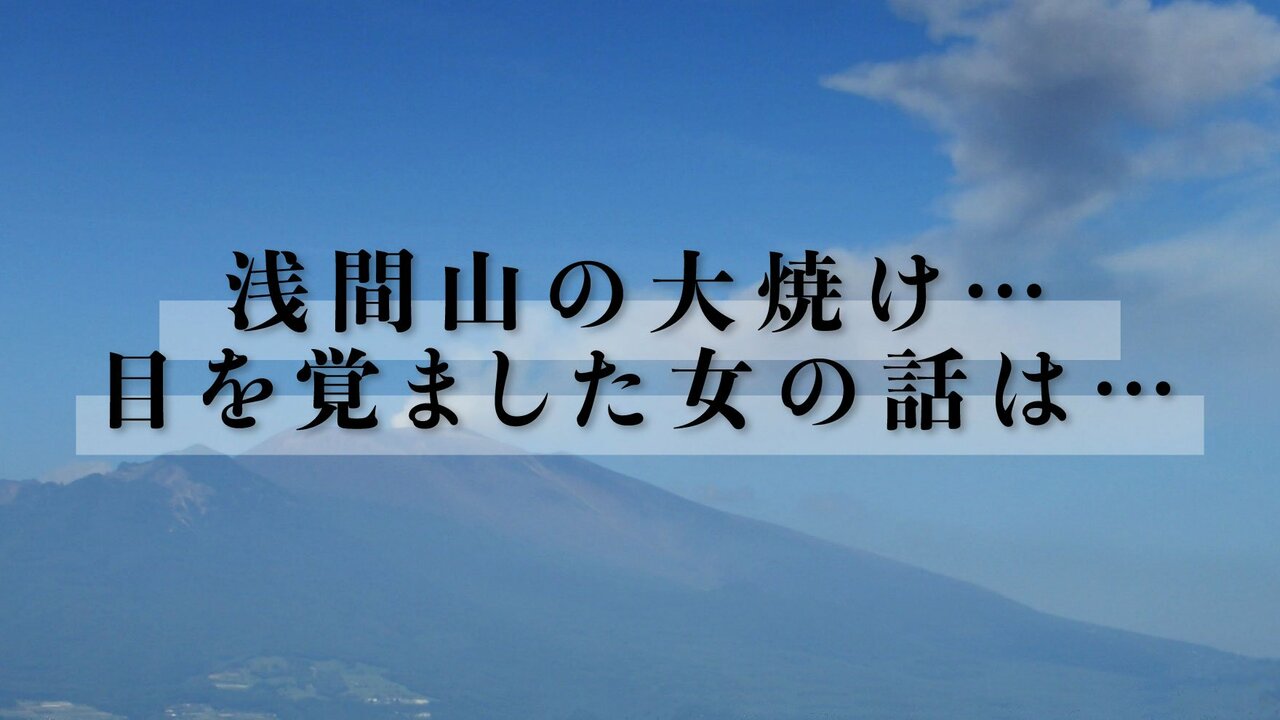「顔から血が出ているがどうなさったね。これを使いなされ」
伊助は腰に下げた手拭いを差し出した。女は手で額の血のりを拭ったが、また染み出してきた。
「血を止めるにはこうしなきゃあだめだ」
伊助は女の額を手拭いできつく縛りつけた。
「申しわけありません。河原道を歩いてきて、子どもに石を投げられました。それが運悪くあたりまして……」
「そりゃあ難儀だったなあ。浅間山の山焼けがはじまってから村や家を捨て、こっちの方まで逃げてくる人が多くなってね。腹を空かせて畑の野菜やらなにやら盗んでいくんで村でも困っているんだ。あんたも勘違いされたんだな。あんたどこから来たんだい?」
女は黙ってうつむいた。そして思いつめたように胸の菰を強く握った。
「何かわけがあるんだね。無理に聞きゃあしないよ。みんなそれぞれ抱えているものがあるからなあ。奥州のほうじゃ随分と凶作のようで一家離散や餓死者が出て、村がなくなったとも聞くけど、ここらも今年は雨が多くてこの多摩川がいつ氾濫するかわからねえし、こんな河原地で石起こししている場合じゃねえんだが、ようやく手に入れた土地なんで嬉しくて早く田んぼにしようと思ってね」
女はじっとうつむいて伊助の話に耳を傾けているようだったが、人心地ついたのか深々と伊助に頭を下げると立ち上がろうとしてよろけた。
「大丈夫かい。おっと触らねえよ。その刀で斬られたんじゃたまらねえからな」
しかし女は膝をついた。思わず伊助は肩に手を掛けた。
「これからどこへ行こうてんだい。こんな体じゃまた倒れるぜ」
「江戸は神田明神下大工町まで帰ろうかと……。お父っつぁんが住む長屋へ行こうと思っております」
「これから神田まで行くったって十里近くはあるぜ。あんた金子はあるのかい。その身なりじゃ旅籠でも追い払われるぜ。困ったな。……よし、とりあえず今夜はうちのあばら家で良ければ泊まりな。親父とおふくろと三人暮しだ。雨露をしのぐ場所ぐらいあるから」
女は動かなかった、というよりは動けなかった。伊助は大八車の後ろに女を座らせるとあばら家に連れ帰った。
「おっ母さん、河原で行き倒れちまった女の人を連れてきた。一晩泊めてやってくれ」
伊助の声に、初が土間から顔を出した。
「おやまあ、ひどい疲れようだねえ。さぞ難儀してやってきたんだろうね。百姓の女房じゃなさそうだね。菰に御刀を包んで……、まあまあかわいそうに怪我までして……、お武家のお内儀さんかね?」
初に気がついた女は、大八車から転げ落ちるように降りると、膝をつき深々と頭を下げた。
「厚かましくもご好意に甘えてしまいました。軒下でも貸していただければ明日早暁には立ち退きます。ご迷惑をお掛けして誠に申しわけもありません」
「いいんだよ。困っているときはお互い様だよ。お内儀さん、先を急ぐ身かもしれないが、しっかり歩けるようになるまで休んでいくといいよ。こんなあばら家だけどね」
「おっ母さん、俺は名主様と組頭のところへ行ってわけを話してくるから」
そう言うと伊助は手拭いで野良着をはたき、慌てて出て行った。