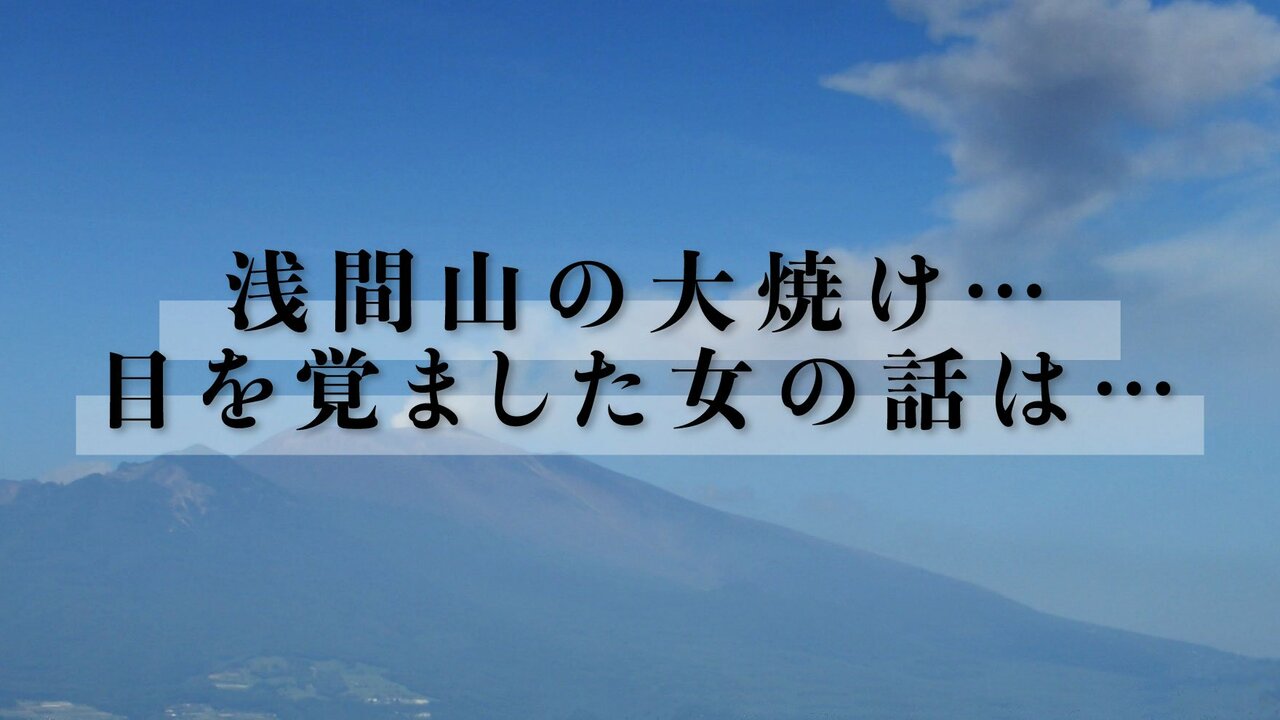第二章 出会(二)
その日、伊助はいつものように河原新田で土を起こしていた。手を休め、手拭いで汗を拭っていると、河原道をみすぼらしい身なりをした女が菰を胸に抱えて、ややうつむきながら歩いてくるのが見えた。
伊助が女の姿を目で追った。女はぼんやりと伊助を認めると、ふらふらとおぼつかない足取りで近づいてきた。伊助もぼんやりと女を見ていた。
女の顔には生気がなく、疲れ果てた様子でうつろな眼差しを伊助に向けた。額からうっすらと血が流れている。まるでお化けのようであった。女は伊助の近くまできてしゃがみこんだ。
(どうせ乞食だろうし、放っておけば行ってしまうだろう。かかわるまい)
と目を避け、また鋤をふるいはじめた。
か細い声で女が何か言っている。無視していたが、やがて女はがっくりと頭を垂れてその場へへたり込み、突っ伏してしまった。
「弱ったな。死んじまったんじゃ寝覚めが悪いし、代官所に届けるといろいろ聞かれて面倒くさいし……、え~い、しょうがねえなあ」
伊助は鋤を土に刺すと手拭いで額の汗を拭き、女の元へ歩み寄った。
「どうしなすったね。体の具合でも悪いのかね。あんたにここで倒れられたんじゃ仕事が止まっちまうんだよ」
女は動かなかった。佇ずんでいた伊助は仕方なく女の肩に手を掛けて揺すった。女は、ぼーっとした目を伊助に向けると突然、胸の菰をぎゅっと抱きしめて、
「無礼者、何をする!」
と裾を合わせ、菰から取り出した長さ二尺二寸はあろうか、黒塗り鞘の脇差の柄に手を掛けた。
びっくりして伊助はのけぞり、女から飛びのいた。しかし女は再び目を回してへたり込んでしまった。
そっと近づいた伊助は気つけにと思い、水の入った竹筒を取って来て女のそばに置いた。
少し離れてしばらく様子を窺っているとおぼろげに女が目を覚ました。女はそばの竹筒に気がつくと一瞬、伊助を窺ったが、慌てて竹筒の水をごくりごくりと飲んだ。
「喉が渇いていたのかい。じゃあ腹も減っているだろう。これでよかったら食いな」
伊助は竹皮に包んだ麦の握り飯を差し出した。女はじっとうつむいていたが、
「俺は何もしやあしないよ。あっちに行っているから」
と言って女の膝の上に置くと背を向けて畑に戻った。背後から女のか細いうめくような声が聞こえた。
「お情けありがとうございます。遠慮なくちょうだいいたします……」
そっと振り向くと、女は両手で大事そうに握り飯を握りしめ、涙とともに頬張って食っていた。一息ついたのか顔に赤みが差してきた。