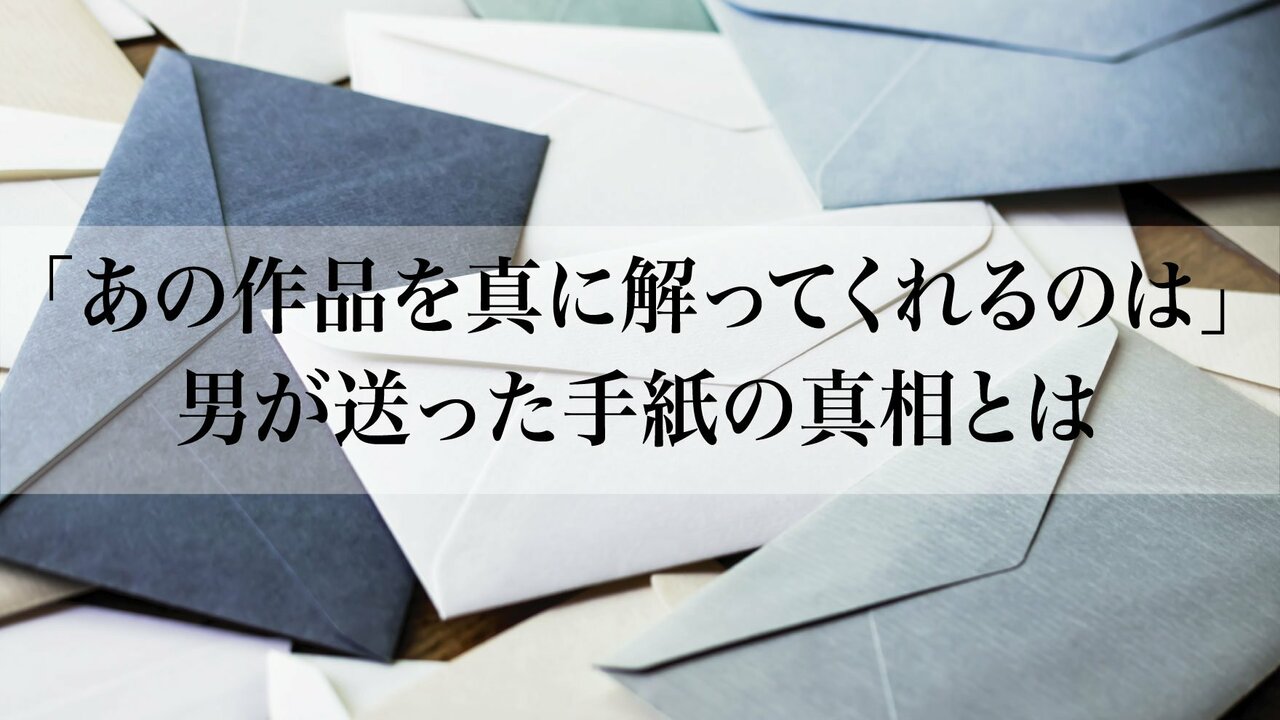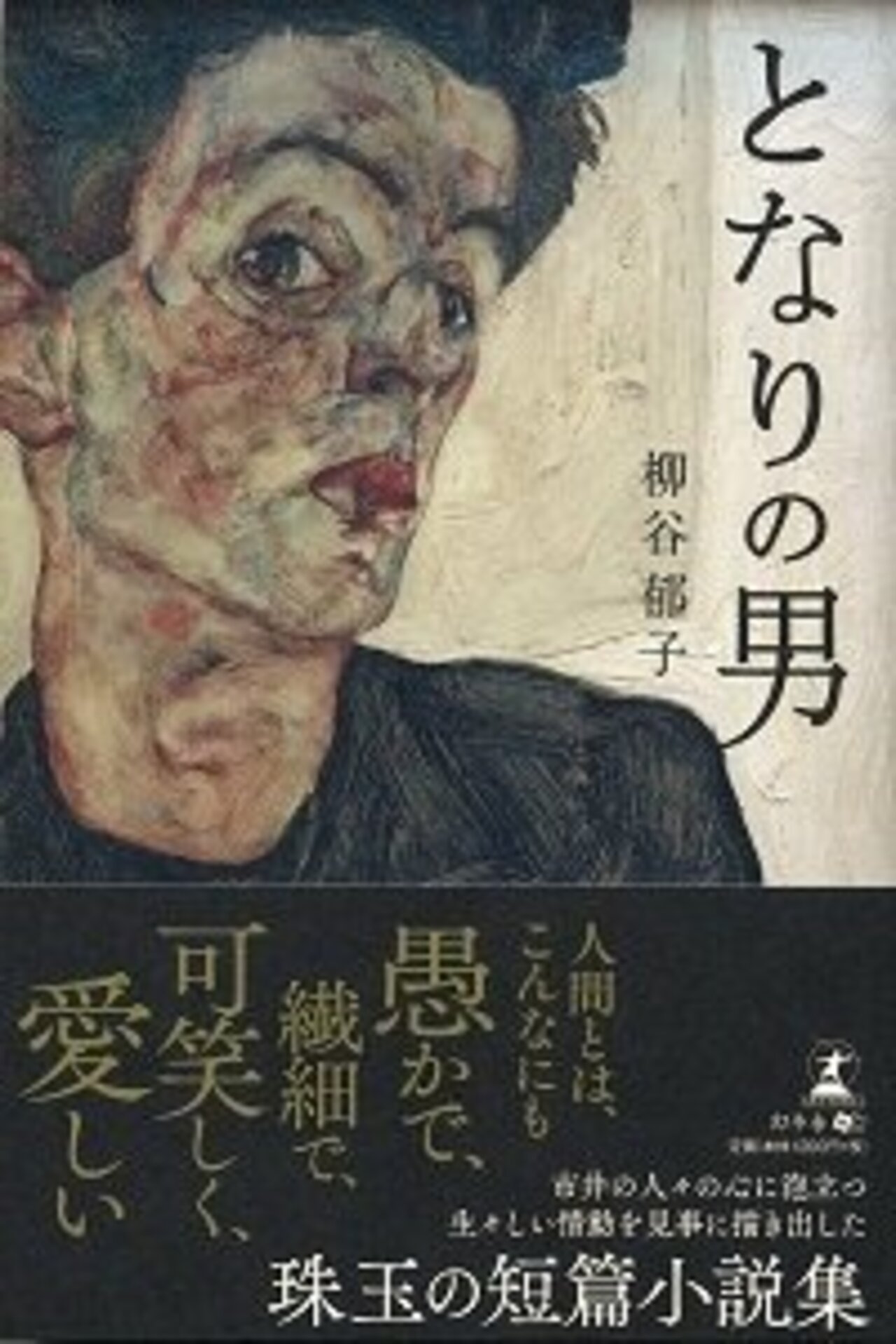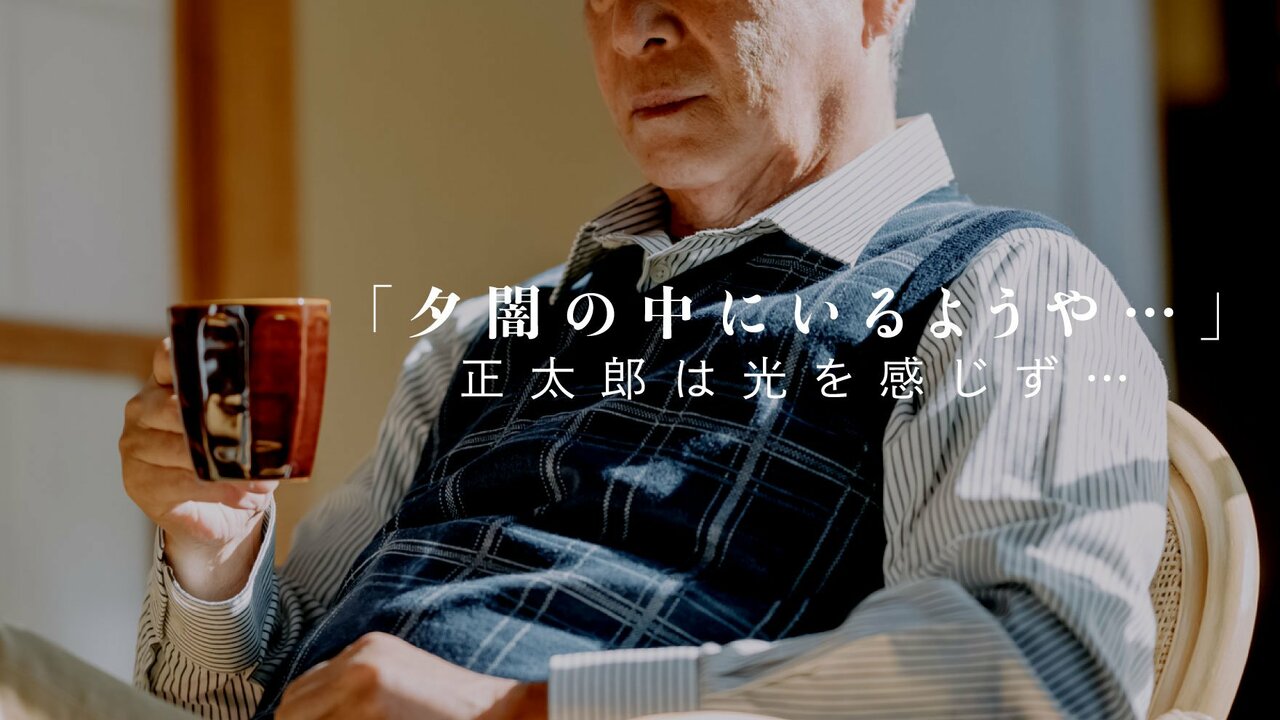ユタの肖像
すでに大学のゼミも終了し冬季休暇に入っていたが、インド研究会で発行する研究会報の資料収集のために、あなたは帰省を遅らせていた。その心の奥にもう一つ帰省を躊躇う理由があることに、あなたは気づかない振りをしている。
―前略。君は、あのフランツ・シューベルトにまつわる甘い甘い伝説のように、僕の作品を永遠に〈未完成〉に終わらせるつもりか。僕にはそんなローマンティックなことはとても我慢出来ない。もっとも、今まで君が来なかったことについて、僕は勝手にローマンティックな筋書きを立てているのだから、実に僕らしくない話だ。
僕はただ、君の罪の、いや無罪についてのご託を、どうしても聴きたいのだ。僕の全官能を全開放して、全照応して。君の言葉を!
君のたった一つの声を!
さあ、来たまえ。
十二月二十七日、午後五時。初めて君を見た(心に)ユタにて。終電まで待っている。
今度ばかりは、ほんのちょっぴりでいい、僕の手伝いをしてくれたまえ。二十七日より遅くなってはもう間に合わない。つまり僕は次の出展作品に君を描くことに決めているのだ。そのことももう一つの用件であることを、お忘れなく―。
苛立ちの見える居丈高な思い切り気障だと思うしかない手紙に、あなたはもう反発しなかったが、やはり応えることもしなかったのであった。
そしてその手紙に得心したかのように、何故か安心して帰省したのだった。
春が来て、あなたは二年生になった。まだ二十歳になるまでに数か月あった。
田島からの一方的な手紙は少し間遠になったが間断なくつづき、たちまちあなたは卒業の春を迎えた。