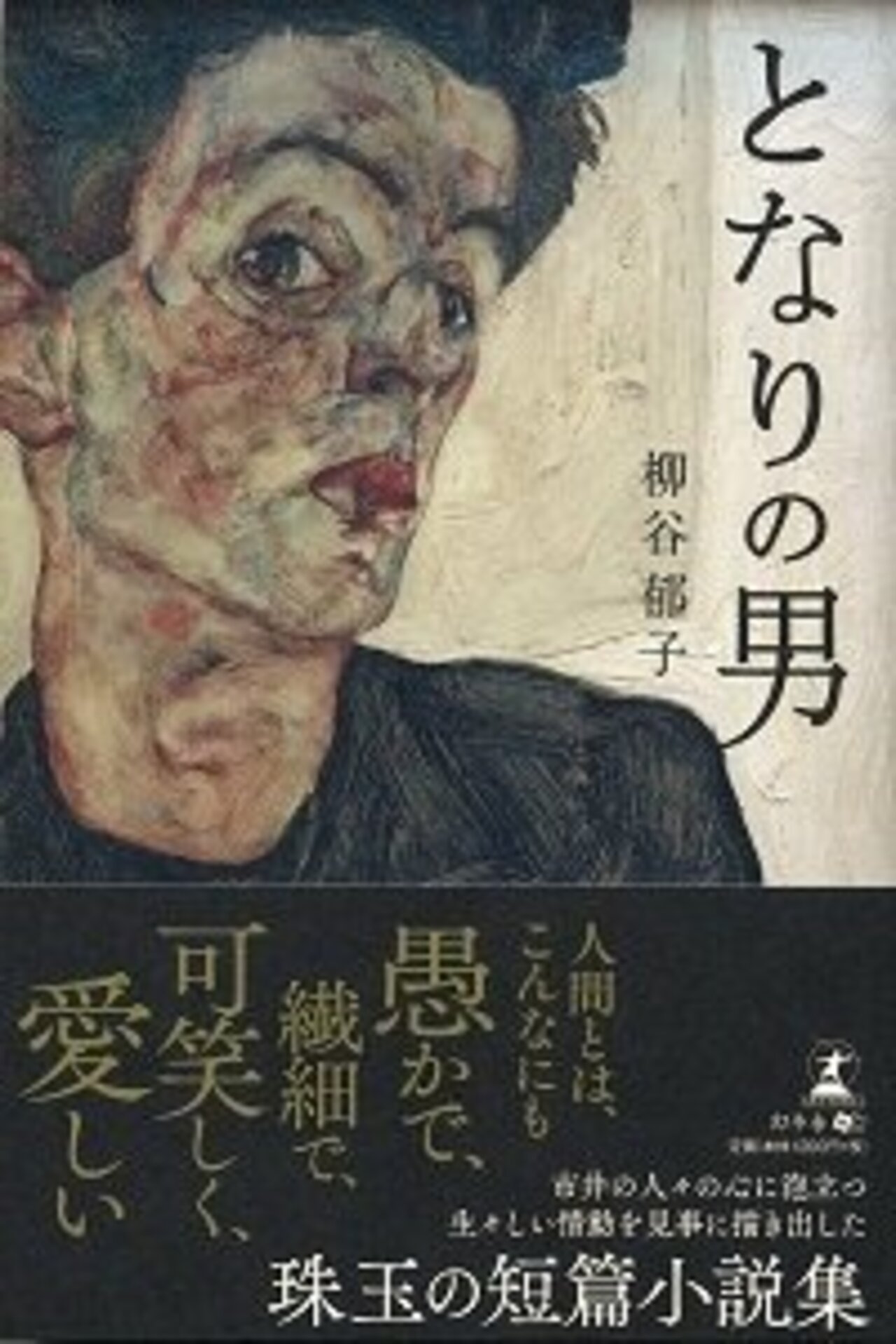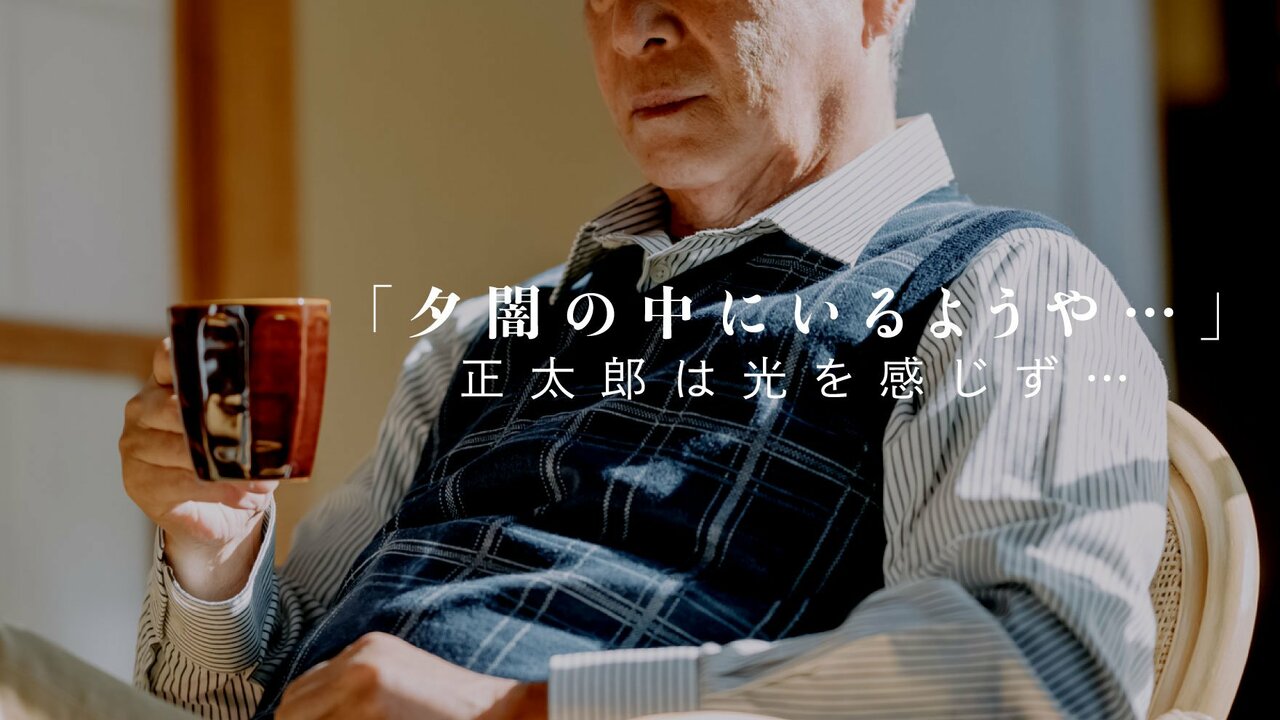ユタの肖像
九時四分にはまだ三十分ある。どこに立っていようかとあなたは迷う。
【人気記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
あなたが迷おうが迷うまいが誰も見ている人などいないのに、あなたは迷っていることを知られたくなくて、自分にも知られたくなくて、さもそこが当然に決められている自分の場所だとでもいうように、改札口を出るとすぐ横手の薄汚れた丸い柱の根元にさりげなく立ち、少し膨らんでいるボストンケースを下ろす。
十年前にもこうして此処に立っていた。四十二歳だった。
その十年前にも此処に立っていた。三十二歳であった。
東京からはるか西の小さな町に住んでもう三十年が経ったのだと、五十二歳のあなたは十年ごとの歳月をあらためて思っている。
高田馬場は乗降客は夥(おびただ)しく多いのだが古ぼけた小さな駅である。駅も周辺のありようもあなたがこの学生の街の住人であった頃とほとんど変わっていない。
しかし間をおかず絶えず改札口に吸い込まれ吐き出されてくる無数の人々の群れは、あなたにはもう呆然と眺める影絵でしかない。
夜が更ければ更けるほどに人々は無表情になり、音も無く輪郭がぼやけて闇に融けてゆく。駅舎に降っている白い蛍光も外に煌々と輝く色とりどりのネオン街も、闇を際立たせる舞台でしかない。幾つかの売店だけが活きのいい生き物のように明りをかき集めている。
商品が溢れかえる屋台の前には積み上げられた雑誌や新聞が雪崩れかかり、傍らには安物の衣服やバッグややたらに光る色とりどりのアクセサリーがぶら下がっていたりして、その野放図な乱雑さが客を引き寄せる。あなたがこの駅を我が物顔に猛スピードで駆け抜けた頃には、駅舎にこのような屋台売りの売店はなかった。
この時間になると、夜行性の動物のごとく目に奇妙な光を湛えた人の群れが秘密めいた息遣いを荒くしていたものだ。三十年前のその荒々しい息遣いが、しだいに大きくなる時計の振り子の音のようにあなたを取り巻き始める。
けれども目の前ではあっけらかんと現実的な会話が飛び交っていた。
「また一杯やってくの?」
「いや今日はうちで残業」
「それはそれはご愁傷様。夕飯、食べたん?」
「これ、これ、――」