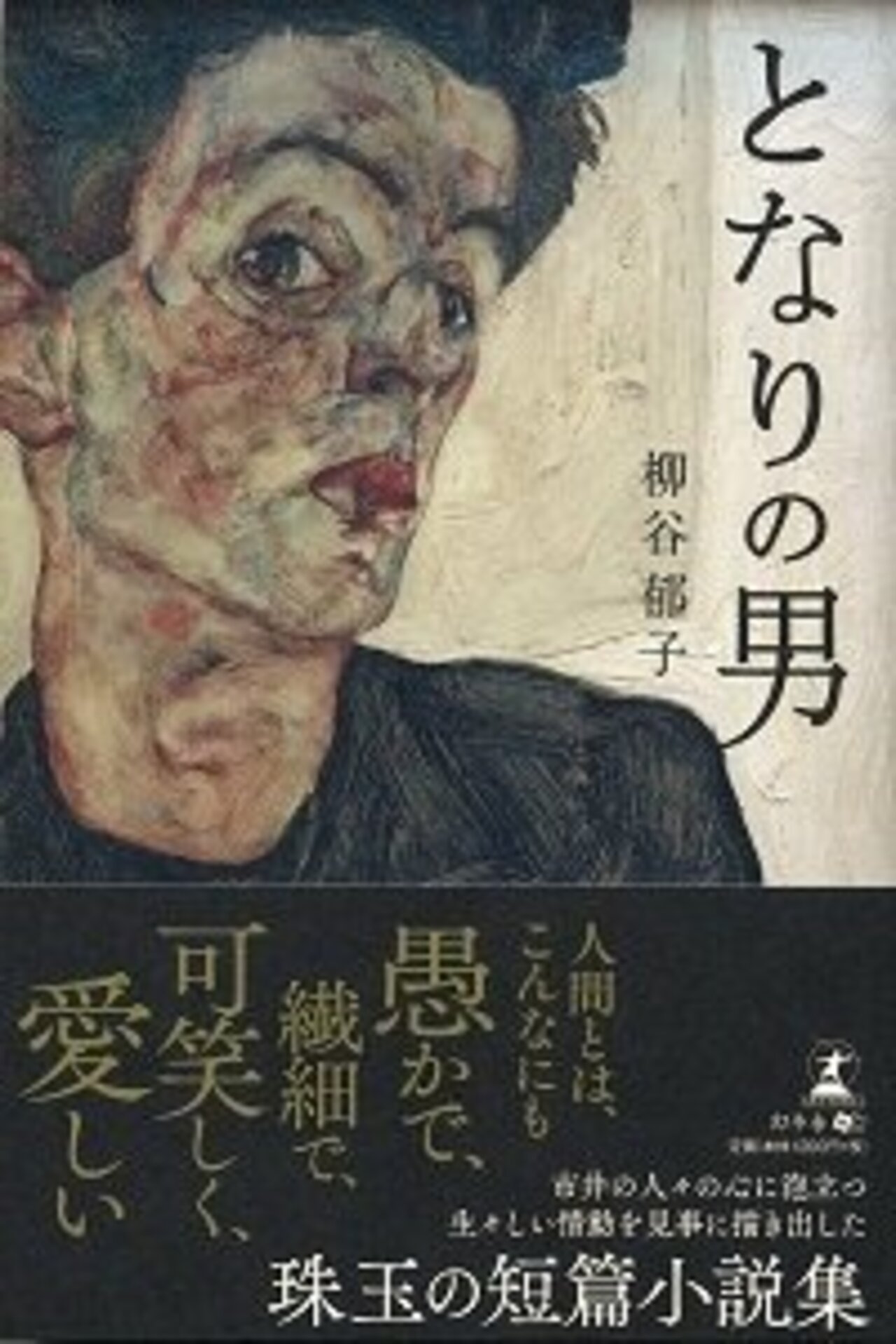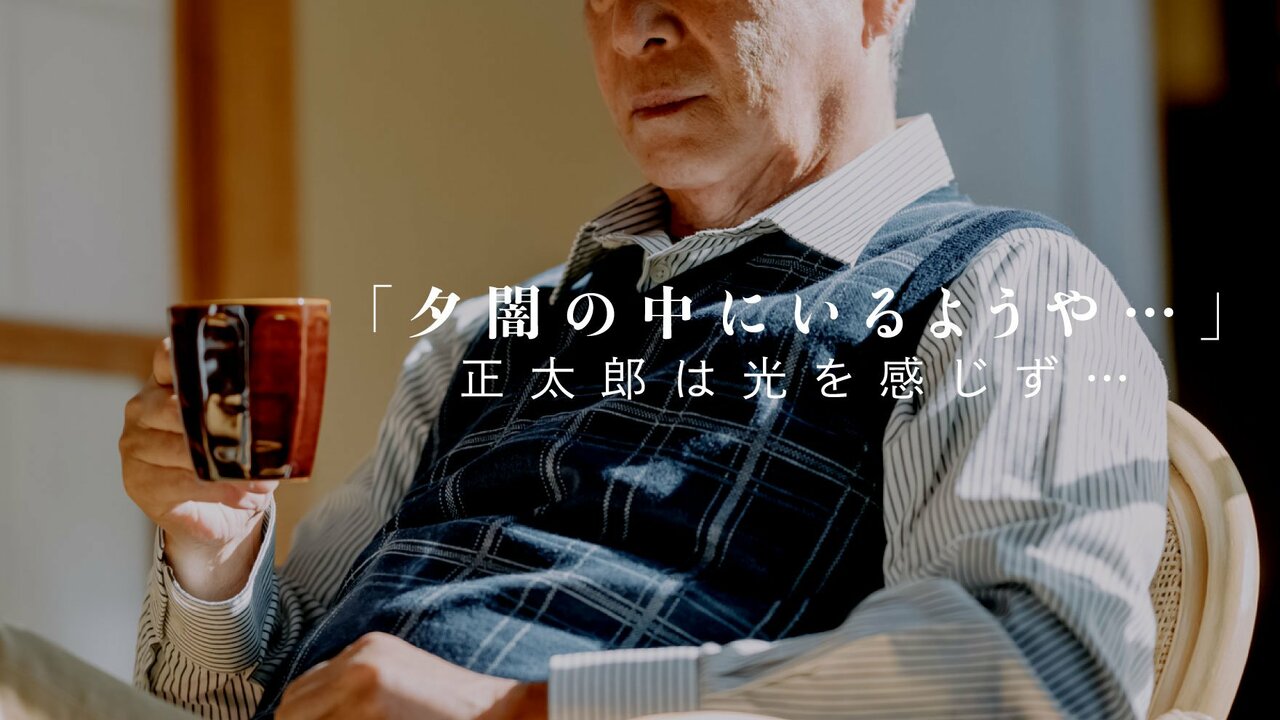桜かがよう声よ
もう本来の手術は無理であった。
血圧と脈拍が僅かにも好転したところで、とりあえず剥がれかかっている網膜に空気を吹きつけるだけの措置を施すことになった。
着替えを取りに帰宅すると、電話が鳴り続けている。
「八木沢さまでいらっしゃいますか」
営業用のものなれた甲高い声であった。
「はい、八木沢でございます」
「こちらはブティック・モアでございます。いつもお引き立てにあずかりまして有難うございます」
「――モアさん?」
「はい、モアでございます。先日はまたお買い上げ下さいまして有難うございます。本日お引き落としをさせていただきましたので、お礼かたがたご報告させていただきます」
「あの、何を買ったんでしょうか」
「はい、あの、ワンピースコートを――。あの、あの時の方と違うんでしょうか、おじいさまとご一緒に来られた――」
受話器の向こうがざわついた。
「銀行ですね? 口座の名義は確かに八木沢正太郎なんですね?」
「はいそうです。八木沢さまです。あの、お宅さまは?」
「息子の嫁です」
「それでは、あの方は―」
「小柄でぽっちゃりの笑顔のいい人ですよね? それで、そのワンピースコート、お幾らだったんでしょう」
相手は言いよどんだが、しょせんトラブルは客の方の事情である。
「十六万八千円でございます」
きっぱりと返事が返った。わしは花も人形も嫌いじゃと言い、殺風景なほど余分なものを削ぎ落として揺るぎない日常の中に端然と居るかに見えていた正太郎が、好江が付き添う整骨院かクリニックの帰りだろう、彼女に法外に高額な服を買ってやっていたのだ。
電話の様子では一度や二度ではなさそうだ。何食わぬ顔の好江の鼻にかかった甘ったるい声音がにわかにふゆ子の耳に突き刺さる。
躰の衰えはあっても頭の老化はないものと、妻に先立たれた寂しさも口にしない正太郎の精神の強靭さを、ふゆ子たちは疑いもしなかったのだが、やはり正太郎の老いは切羽詰まっていたのだ。
傍に寄り添ってくれる者でさえあれば誰にでも縋りたくなっているのだろう。老いに追い立てられて自分でも知らずに上げているに違いない正太郎の悲鳴を、ふゆ子は聴く。
正太郎が俯せ寝を強いられる少なくとも二十日間は昼夜を付き添わなければならない。好江は必要であった。その好江に電話の件を言えないままに、ふゆ子は胸にしまいこんだ。
正太郎は眉毛を剃られ睫毛を切られた。また血圧が上がったが、そのまま手術室へ運ばれて行った。