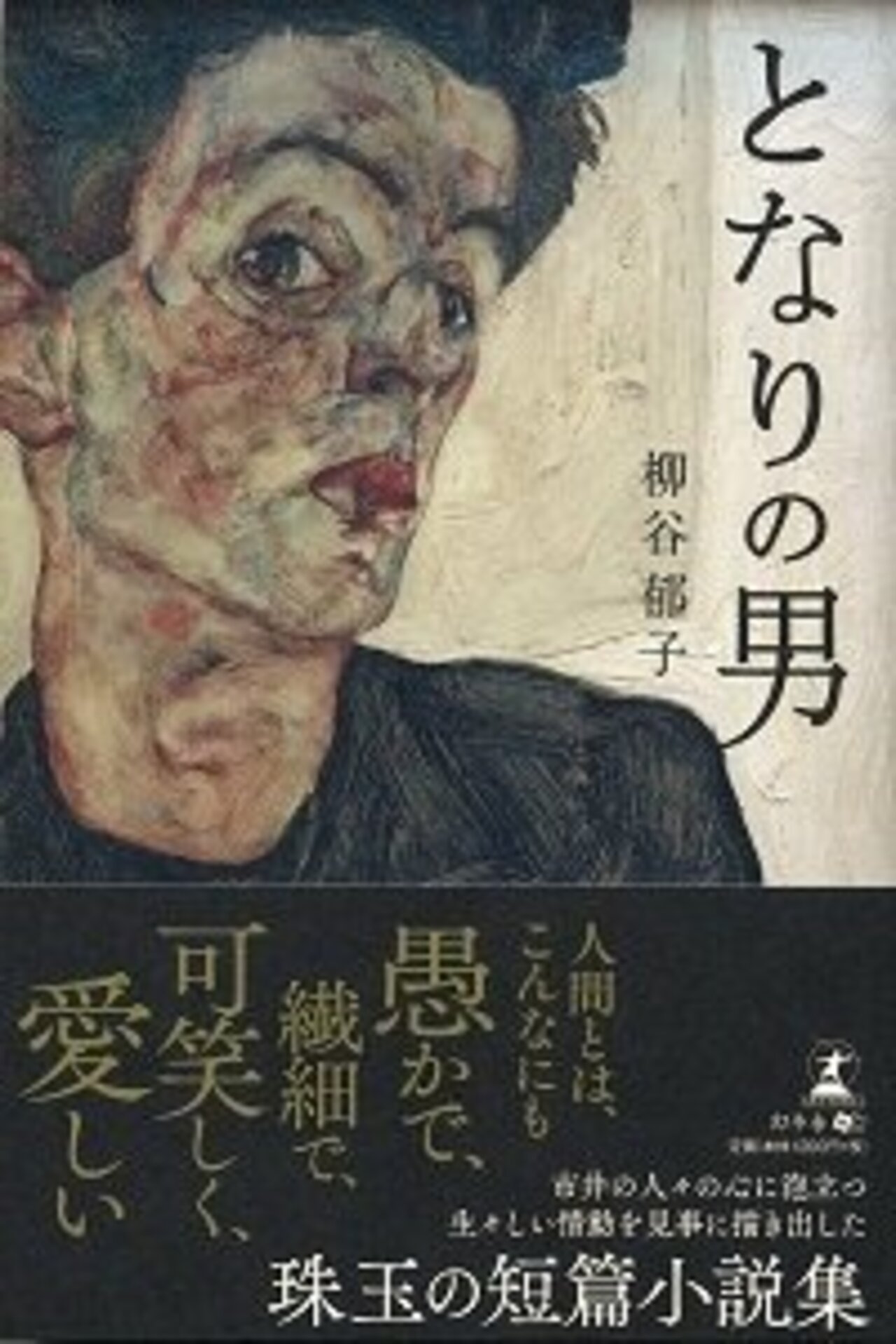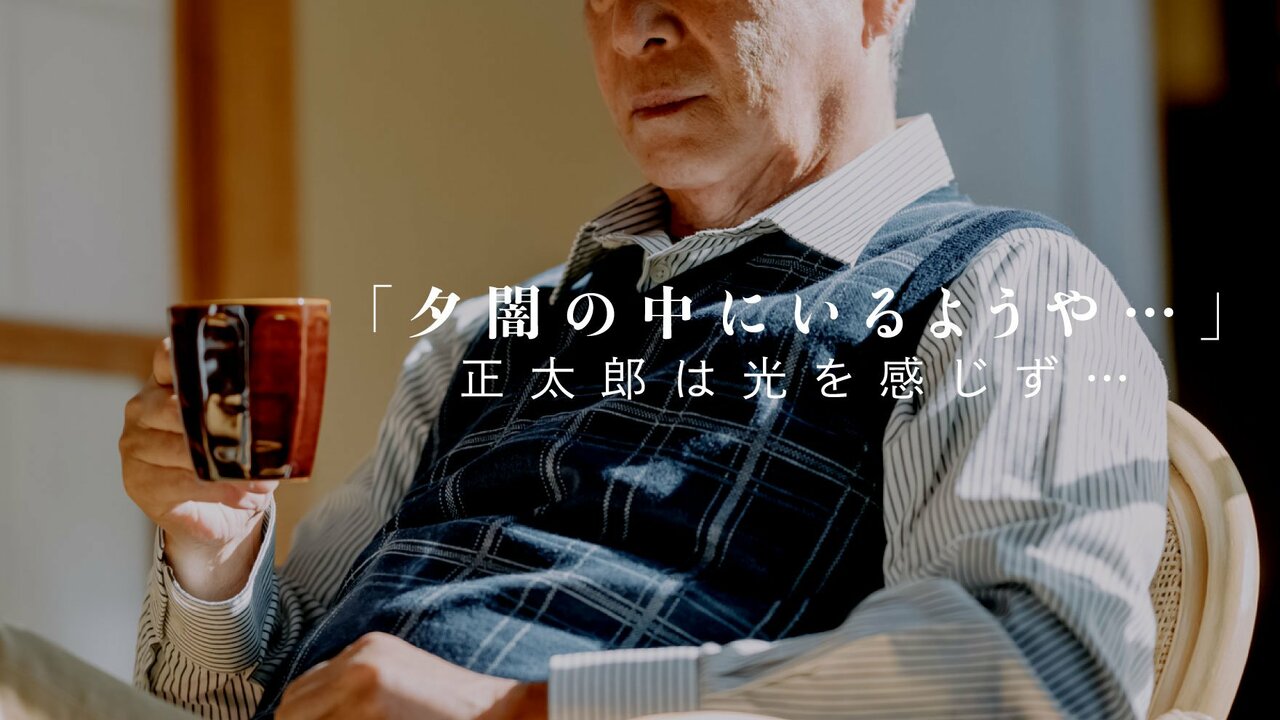東京から圭二が飛んで来た。髪をオールバックに後ろでくくっている。髭の伸びた顎には薄汚れた白い襟が立っている。夏物だ。よれよれの革ジャンだけが冬らしい衣服だ。
「寒くないの?」
ふゆ子は大仰に額に手をかざして眺め、おどける。
「なんて恰好でありますか、なんだか人相が悪く見えますが」
「もともとだろ」
「いいえ、わたくしの息子はもっと人相が良かったはずでございます」
傍にいるだけで心が温もる。三十六歳にもなるもう立派に大人の男をつかまえて、もう少し言いようはないものか。真面目な挨拶をすると、その圭二の優しさの裡に潜んでいるどうしようもない闇の扉を開けてしまうような気がする。
圭二は目を眇めてふゆ子を見下ろした。
「おじいちゃん、大丈夫なんやろ?」
「大丈夫よ。手術といっても、簡単なことしか出来なくなっちゃったから、二十分ぐらいで済むそうよ。ほんとにタイミングよく間に合ったわね」
「僕の勘はいいんだ」
「もうじきお父さんも健一も来るわ。聡子さんも、あっちゃんも。美沙叔母さんも、きっと」
「美沙叔母さんも? やっぱり一応手術となると大変なんだ」
「そうよ、それに何といってもおじいちゃん、歳だもの。一番近いところの娘ぐらいには知らせておかなくちゃ。しかも、おじいちゃん、初めての入院ですっかり怖気づいてしまっているの」
少し変なの、困っているの、と言おうとして呑みこんだ。殊に圭二には知られてはいけないのだ。
「僕はおじいちゃんの無事な顔を見たらすぐ帰るからね」
来たばかりだというのに、圭二が言う。にべもないその一言にも、引きとめる言葉を呑みこみ頷いた。
圭二は正太郎を元気づけるためだけに帰って来たのだ。武彦にも健一にも、まして兄嫁の聡子や叔母たちには、会いたくないのだ。というよりも合わせる顔がないのだ。
そんなことは気にしなくていいのよ、堂々としていればいいのよと、ふゆ子の言うことはいつもそれしかない。しかし圭二になり代わって、ふゆ子自身、彼らに何食わぬ顔をするのにかなり無理をしている。
圭二は働きながら勉強をすると言ったのだ。そうさせなかったのは正太郎と武彦とふゆ子だ。圭二ならしっかり勉強に没頭すれば二、三年の内には合格するだろうと信じて疑わなかった。
多少のアルバイトをするにしても、圭二の受験暮らしは結果的に八木沢事務所からの送金で成り立ってきたのである。すでに五年が過ぎようとしている。
年ごとの不合格の落胆よりも、三十を過ぎて実家に依存する重圧が圭二を追い詰めている。
圭二の主張が正しかったのだろう。働きながらの方が圭二は屈託なく自分を信じることが出来、いい結果を出すことが出来ていたに違いないと思うことが、ふゆ子を苦しめる。
ただの無職者、寄生虫、と空笑いしている圭二の自嘲が、ふゆ子にずっしりとのしかかっている。
続く