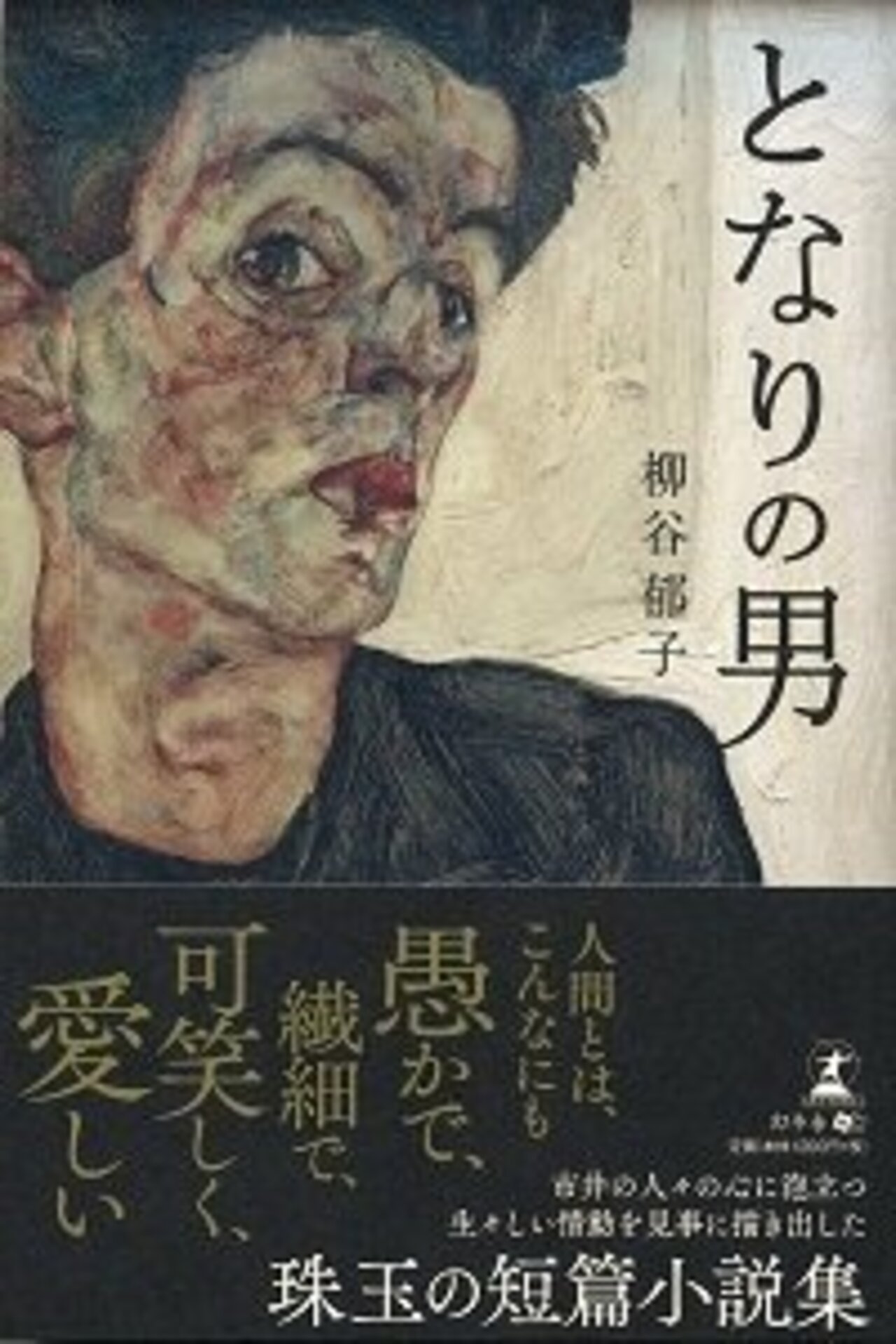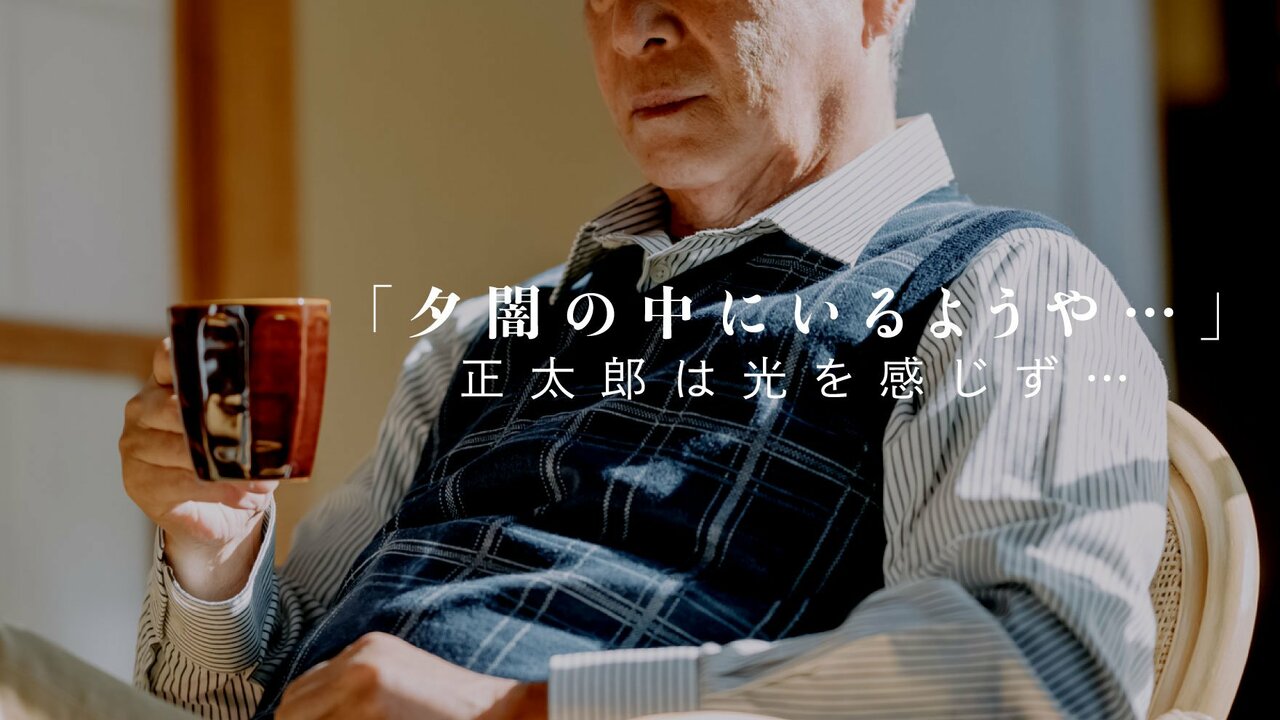桜かがよう声よ
網膜が剥がれかかっていた。本格的な手術は高齢から考えものであるが、ガスを吹きつけて接着が叶えば、とりあえずは完全な失明を免れることが出来るかも知れないという。
施術は短時間で済むが、しかし術後は三週間、顔を伏せたまま俯せ寝で動いてはならないという。それがちょっと大変ですがねと、眼科医は言った。手当ては一刻も早い方がいいのだ。ところが血圧の数値が跳ね上がっていた。
「普段からこんなに高いんですか」
「いいえ、本態性高血圧だとは言われていますが、お薬も何も。食養生で用心しております」
「ほう、お元気だったんですねえ。ですが今日は、お歳にしても高すぎます。一八〇ですからねえ。まあ白衣症候群かも知れませんが。いずれにしても血圧を安定させてからでなければ目の治療は出来ませんね。手術はそれからということにしましょう」
背中に手をまわしたふゆ子の腕の中で、大きな丸い躰を縮めて子どものようにすくんでいる正太郎を、医師はカルテに書き込んでいる手を止めてしばらく眺めた。
「入院は初めてなもんですから。きっと、その緊張のせいです。落ち着いたら、すぐに下がると思います」
庇うようにふゆ子は言った。六人部屋の廊下側のベッドに正太郎の名札が掛けられた。引きまわされている黄色いカーテンを分けて自分の領域に入ると、正太郎は指示されるまでもなくすぐさま病衣に着替えベッドに横たわった。
布団を肩まで掻きあげ、真っ直ぐ仰向けた顔は目を閉じたまま動かない。ふゆ子の問いかけにも唇をわずかに動かし微かな声を洩らすだけである。
正太郎の気持ちはすっかり重病人なのだ。動揺は収まるどころか取り留めもなく増していくようであった。血圧降下剤も効く気配がなかった。ついに二四〇を数える。異常な脈拍の速さにも医師は首を傾げた。
夕方、仕事を終えて立ち寄る武彦と孫の健一に、わしはもう目が見えんでもいいんやと俄かに力強い声で訴える正太郎に、
「何言うんや。まったく見えんのと少しでも見えるんとじゃあ大違いやで。まだまだ生きるんやろ。生涯現役や、一〇〇歳まで生きるんやて、いつも言ってたやないか」
「目が見えんかったら、今よりもっと歩けなくなってしまうがな。脚が弱ってしまったらそれこそおしまいや。長生き出来るもんも出来なくなってしまうやないか」
「まだみんな頼りにしてるんや。頑張ってくれんと」
「手術いうてもな、目に何か吹きつけるだけの、あっという間の処置だそうや。怖いことも心配することも何も無いんやで」
かわるがわる励ます二人に押し黙っている。
「おじいちゃん、怖いんか。怖くなんかないよなあ。そんな意気地なしやないもんなあ」