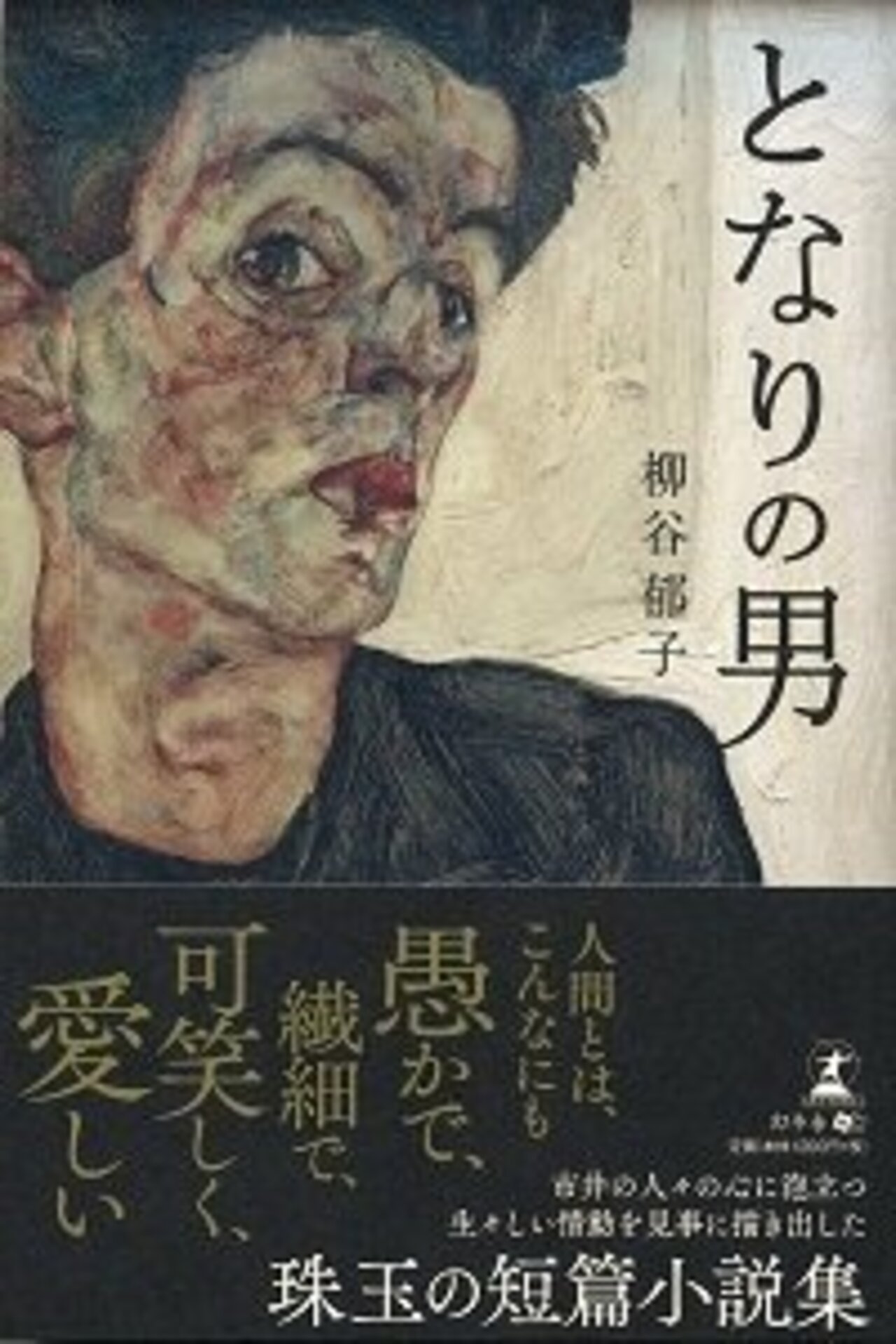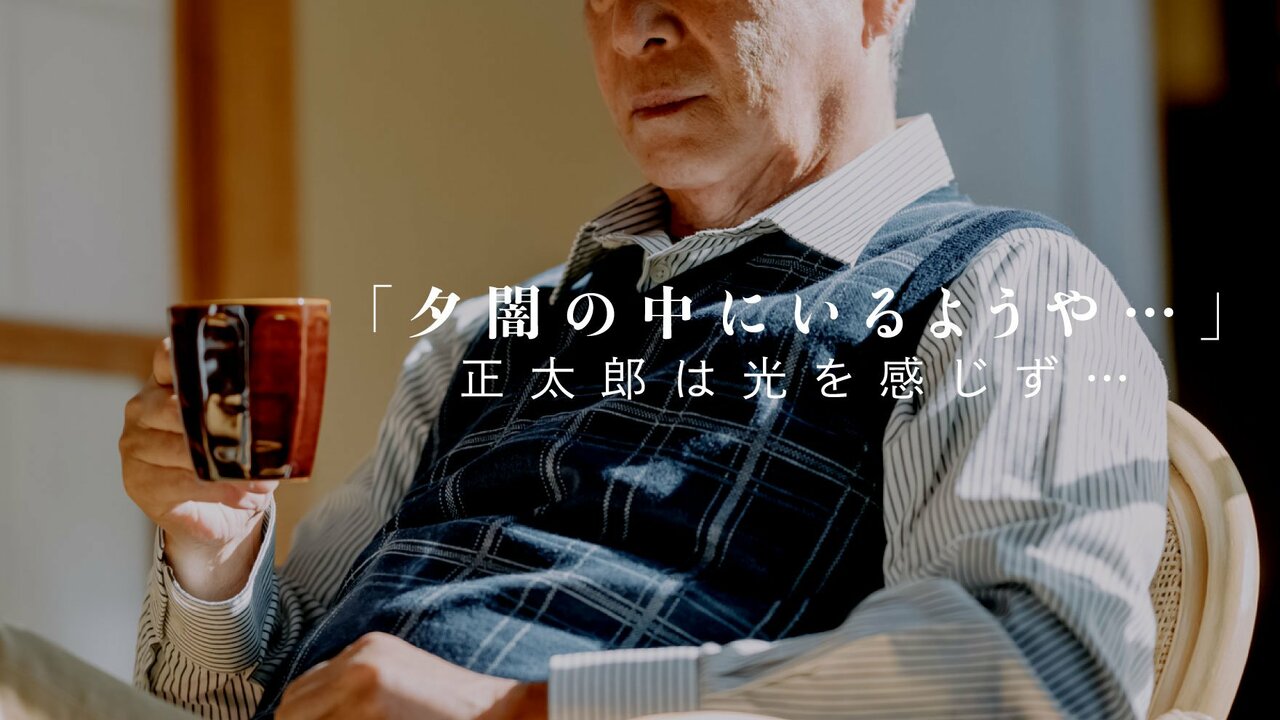夕刊を買った客は、手首にぶら下げたビニール袋を、もう一方の腕で胸に抱えている鞄の上へ上げて見せる。
「お袋さんの味も近頃はけっこう美味しくなってるんだけどねえ。それでもねえ。今度はいつ? 奥さんとこへ帰るの」
ビニール袋へちらりと目を泳がせただけでレジの引き出しを開けた売店の女あるじは、手を忙しく動かしながら、昨日の茶の間の話の続きのように訊ねる。
「うーん、いま会社が大変な時だからねえ。なかなか」
「そうだねえ。辛いねえ。子ォたちも待ってるだろうにねえ。はい、お釣り」
「ありがと」
小銭を受け取りそのままズボンのポケットに入れてくるりと背を向ける、その働き盛りの背広の背に、また声だけが飛ぶ。
「また明日ね。浮気したら駄目だよ。奥さん泣かしたらいけないよ」
常連なのだろう。男は歩きながら丸めた夕刊を頭の後ろで振った。それを女あるじはもう見ていない。次の客が雑誌と新聞を差し出している。
大都会の雑踏の片隅で、人はいつの間にか暮らしにまみれた肌をひそかに温め合っているのだ。思いもかけなかった遠い地に棲みついて、家庭を持ち子育てをし世間と付き合い何とか辻褄を合わせて生きることと格闘してきたあなたは、暮らしにまみれたどろどろの生臭い言葉を聴くとほっとする。
この駅を行き交っていた青春の頃には最も遠ざかりたかった、どうしようもなく憎い言葉たちに。あなたは駅の時計を見る。九時四分まであと数分。
改札口の横手に並ぶ公衆電話は閑である。時々その前に立つのは歳のいった人たちで、あなたより若い人たちは携帯電話を手にするかポケットに入れている。その傍若無人な会話を聴いているだけで退屈しない。
あなたも携帯を持っているが電源を切っている。十円玉しか使用出来ない公衆電話を探して走りまわった日々の若さを、あなたは妬ましく思い出す。百円玉しかなくてお釣りになる筈の九十円が電話機の中に残ってしまった心残りも。
三十分はあっという間に過ぎた。九時四分をカウントダウンする数分、あなたは平気を装いながらもさすがに駅の時計を睨む。
冷たい汗が滲んでいる。