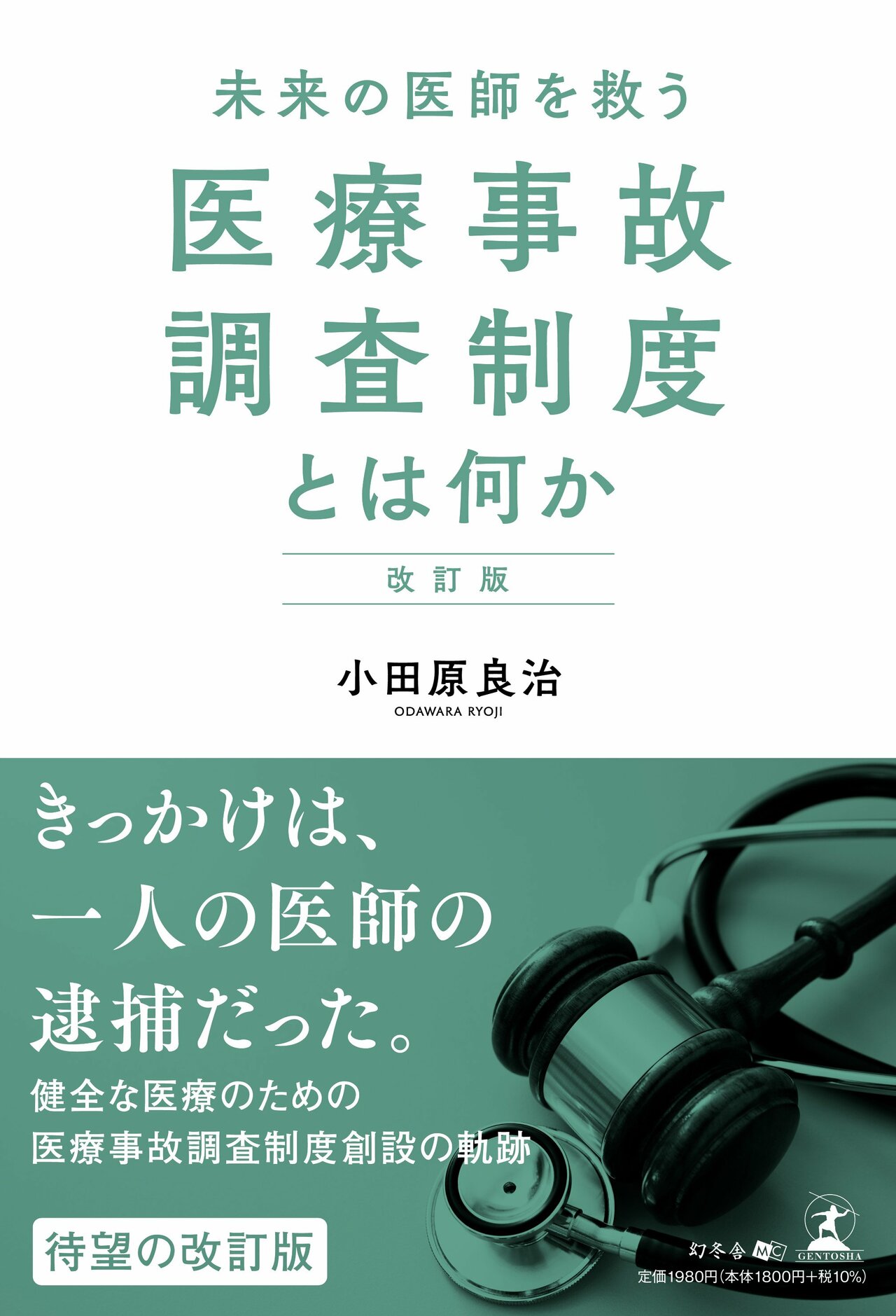もっとも、弁護人は、D医師が死亡を確認したころには、Aの右腕に異常着色は現れていなかったと言うが、Aの救命措置にあたっていたF看護師、○○看護師、××看護師らは、救命措置の最中にAの右腕に異常着色が現れていた旨供述しており、また、D医師自身も、心臓マッサージを施している際、Aの右腕には色素沈着のような状態があることに気付いていた旨供述していること(検察官調書謄本)などにかんがみれば、D医師がAの死亡を確認した際、既に異常着色が現れていたと認めるのが相当であり、弁護人の主張は失当である。
なお、弁護人はD医師は医師法第21条にいう死体の検案をしたことにはならないかのようにいうが、AはD医師が主治医として診療してきた入院患者であり、D医師は、Aの容態が急変して死亡し、その死亡について誤薬投与の可能性があり、診療中の傷病等とは別の原因で死亡した疑いがあった状況のもとで、それまでの診療経過により把握していた情報、急変の経過についてE医師から説明を受けた内容、自身が蘇生措置の際などに目にしたAの右腕の色素沈着などの事情を知った上で、心筋梗塞や薬物死の可能性も考え、死亡原因は不明であるとの判断をして、遺族に病理解剖の申し出をしているのであるから、Aの死体検案をしたものというべきであって、弁護人の主張は失当である。
第二 医師法第21条の適用について
弁護人は、医師法第21条を本件のような医師が診療中の入院患者が医療過誤により死亡した場合に適用するのは許されないという趣旨のことを主張するが、医師法第21条の規定は、死体に異状が認められる場合には犯罪の痕跡をとどめている場合があり得るので、所轄警察署に届出をさせ捜査官をして犯罪の発見、捜査、証拠保全などを容易にさせるためのものであるから、診療中の入院患者であっても診療中の傷病以外の原因で死亡した疑いのある異状が認められるときは、死体を検案した医師は医師法第21条の届け出をしなければならないものと解するのが相当であって、弁護人の主張は失当である。
第三 判示第二の虚偽有印公文書作成、同行使の事実について
弁護人は、判示第二の死亡診断書及び死亡証明書の作成について、Aの死因を病死と記載したことを虚偽としているが、三月十一日の時点ではまだAの血液検査の結果が出ておらず、事故死と断定できない段階であり、他方、病理解剖報告書の顕微鏡所見として肺血栓塞栓症という病名が記載されていたので、被告人は、それをもとに、病死として記載できる旨判断したのであるから、Aの死因を病死としても虚偽ではなく、また、虚偽であるとの認識もなく、そしてまた、被告人は、右各書面二通の作成についてD医師に対し助言はしたが、指示はしておらず、D医師とは共謀はしていないので、無罪である旨主張するので検討する。