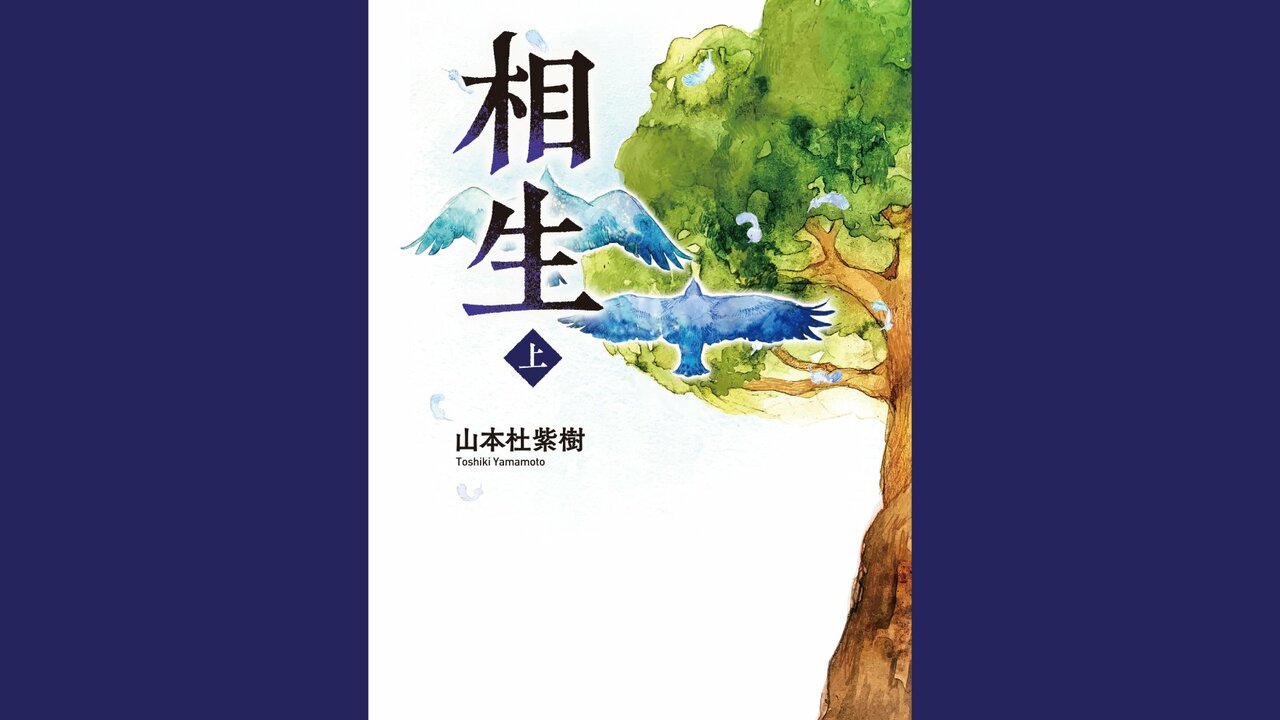清躬くん、ていいですね
「清躬さんは昔から優しいひとだったんですね」
【関連記事】「出て行け=行かないで」では、数式が成立しない。
棟方さんが微笑みながら言った。
橘子は、「ええ」と答えた。もっと具体的に答えたかったが、清躬のことにおもいを馳(は)せているうちにおもわず呟(つぶや)きが出た。
「なつかしいなあ、清躬くん」
言ってしまってから、戀人の前でそんなことを口に出したのが恥ずかしくなった。
「御免なさい」
「え?」
「いえ、なんでもありません」
橘子は惚(とぼ)けた。しかし、迂闊(うかつ)な物言いはなかったことにはならなかった。
「いいですね。昔の清躬さんを御存じなんて羨(うらや)ましい」
戀人から羨ましいと言われてしまって、橘子は困惑した。
「羨ましいなんて──私、唯の小学校時代の友達で……」
かれと今つきあっているあなたのほうがずっと羨ましいじゃないですか──そんなことを後には続けられなかった。自分も羨ましがったら、かの女のライバルになってしまう。
「小学校も五年生の時と六年生の途中までだけ。ほんの一年くらいよ」
橘子は自己弁護するように言った。
「でも、なかよしだったんでしょう?」
まさか嫉妬(しっと)? 私に? 子供の時のなかよしになぜ今の戀人が嫉妬するの? 突っ込まれて、答えをかえさないのはまずいとおもいながらも、いつのまに自分が当事者に入れられてしまったのか納得がゆかず、橘子は言葉を失った。
そして唯、怪訝(けげん)な眼で相手を見上げるだけだった。
「清躬くん、ていいですね」
棟方さんがぽつりと言った。その言い方はとても素直にきこえた。そして、その言葉は、橘子が妙な感情をまじえてとらえた先の発言とあまり間をおいていなかったので、自分が意味を取り違えしていたことに気づいた。
棟方さんは別に橘子にねたみの感情を懐(いだ)いているのではなく、未だに親しく呼べる清躬との距離感を純粋に羨ましく感じているだけなのだろうとおもえた。