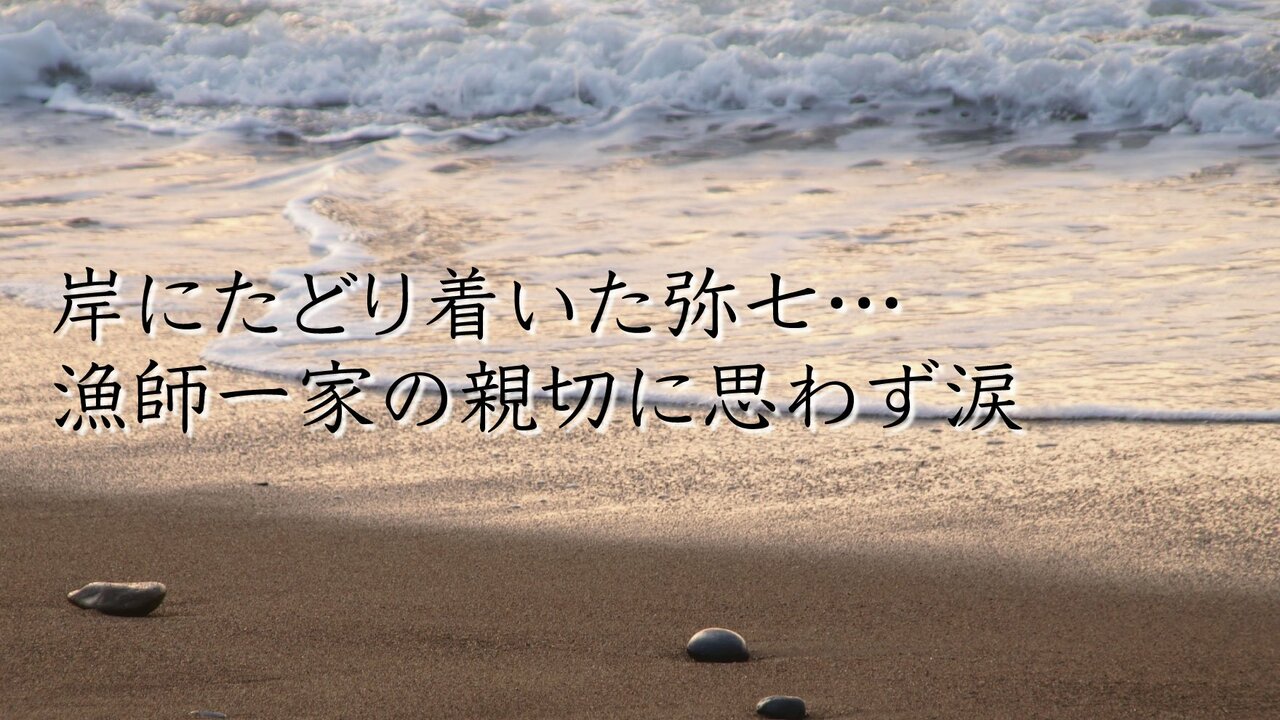弥生編
ひとしきり笑うと、丘の長は真顔に戻った。
【人気記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない
「実は、それが相談なんじゃ」
キナはまたニヤニヤして丘の長の顔を覗ったが、「いや、アトウルのことじゃ」と丘の長は言った。
「里の村だがの、川の周りの平らな土地はもうあらかた耕してしまったじゃろう」それはその通りで、里の長も、今後は水をあまり必要としない畑を広げる、くらいのつもりはあった。丘の長の話は、まだ見えない。
「丘者の中には、黒や緑の珍しい石を持って、それを交換しながら、遠くから旅をして来る者がおる。この土地は、遥か東の方にまで、ずっとつながっておるんじゃ。だが、東の地には、里者はおらんらしい」
丘の長は、こう一気に言って、里の長の顔を見た。
「なるほど」里の長は、唸らざるを得なかった。
「ですが、それとアトウルとどういう関係があるんです?」と聞いた。
「うむ。秋の漁祭りでもそうだったように、奴には衆を率いる素質がある。これまでは、もっぱら一人で山を駆け巡っておったが、最近は若い者たちに人気があるのを、自覚するようになった」
キナに意味を確認しながら、これまで彼を知らなかったのも道理だと思った。
「そして、わしには息子がおる」
丘の長の息子のムカルとは、里の長ももちろん面識があった。丘の長も代々息子が継ぐが、里に比べると、体力に優れ、統率力を示すことが、後継者には暗黙のうちに期待されるようだった。ムカルは、体力の点では問題なかったが、アトウルのような、人を惹きつける格別な魅力はなさそうだった。確かに、アトウルが長の子である可能性があるならば、事態が相当に複雑になるのも想像が出来る。
「なるほど。つまり、丘と里それぞれ希望する者を募って、東の地に移らせるのはどうか、という話ですな?」
里の長は、もう明らかとなった丘の長の提案を確かめた。
「そうじゃ。実のところ、秋の漁の後、何人か東を見にやったんじゃが、そいつらが先ごろ帰って来た。川と山を越えていくと、ここくらいの誰も住んでおらん土地はそこらじゅうにあるし、ひと月歩いたところには、大きな川と広い開けた土地があったそうじゃ」田を耕す者にとって、誰もいない広い開けた土地というのは、甘く響く言葉である。
「蓄えの多いこの冬に出発するのが一番じゃと思う。東に行くにあたっては、丘者の案内と言葉が必要となろう」
確かに、丘者が一緒に行って説明してくれなければ、里者に初めて会った他所の丘者が、彼らの生活を侵すどころか、これほどまでに素晴らしい共栄関係を築ける相手だと分かってくれる保証はない。
「そして、里者が春に米を作り始めれば、皆を養える」丘の長が、全てを良く考えた上での提案であると念押しした。
「アトウルは、行くと言っておる。そして、その娘に付いて来る気があるならば、喜んで連れて行くがどうか、という話じゃ」