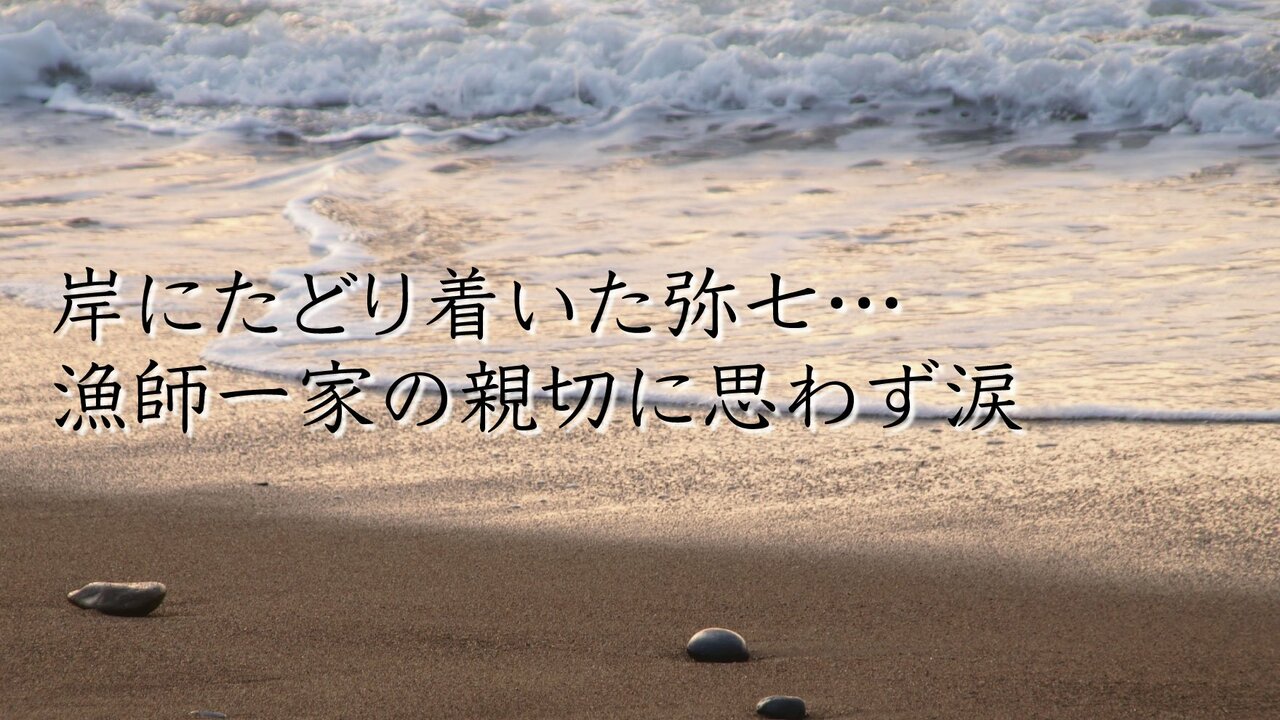弥生編
アトウルとユィリを夫婦にする儀式は、丘の村から川の上流にある森の中の滝で行うと決まった。
【人気記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない
里の村とは反対側に同じくらいの道のりを行ったところにあるその滝を、丘者は彼らの村の守り神とみなしているのだ。
普段は里者の立ち入りを許していない数少ない場所なのだが、この結婚は、これから一緒に旅立つ丘者と里者を象徴する特別なものであると、誰もが了解していた。
参加するのは、二人とその両親、それから双方の長と村の主だった者たち数組の夫妻である。朝、丘の村を出発するとすぐに、葉の落ちて見通しの良い森に入った。
皆が落ち葉を踏む音、冬籠りの前に最後の餌を探すリスや、冬にも活動をやめない鳥たちで賑やかなこの森では、アトウルはユィリに寄り添って歩き、時折短い言葉を交わしていたし、丘の長は、新婦の親戚たちに、森に棲む動物たちやその狩りや、秋に採れるドングリやキノコの話をしながら歩いた。
そうしてしばらく行くと、足元は険しくなり、鬱蒼と暗い杉林に入った。あたりには風の音もなく、森閑と静まりかえり、それにつられるように、みな黙り込んだ。
里者たちには、既に聖域に入ったかのように思われた。丘の長は、老齢にもかかわらずかくしゃくと歩き、そればかりか、老いた妻に肩を貸すよう息子に言い、息の上がった者たちが休みたいというのにも耳を貸さず、みなに先を急がせた。
やがて低く唸るような音が聞こえて来たかと思うと間もなく、とつぜん目の前が開け、人の背丈の四倍はあろうかという、大きな滝が姿を現した。
岩壁と杉の巨木に囲まれて、はるか上から降る水が、滝の下の淵に打ち付ける轟音が響き、宙には細かな飛沫が砕けて霧のようになって漂っている。
このような場所に来て、自然の神なる何かを感じない者がいるだろうか。少し休憩したのち、丘の長に促されてその妻が前に進み出、米と干肉を盛った木皿を足元の岩棚に置き、その前に新郎と新婦を立たせた。
そして、木の枝をかざして祝詞を唱え始めた。なんだか長い祈りだ、と里の長が思い始めたところに、とつぜん頭上から、ぱあっと陽の光が差し込んだ。