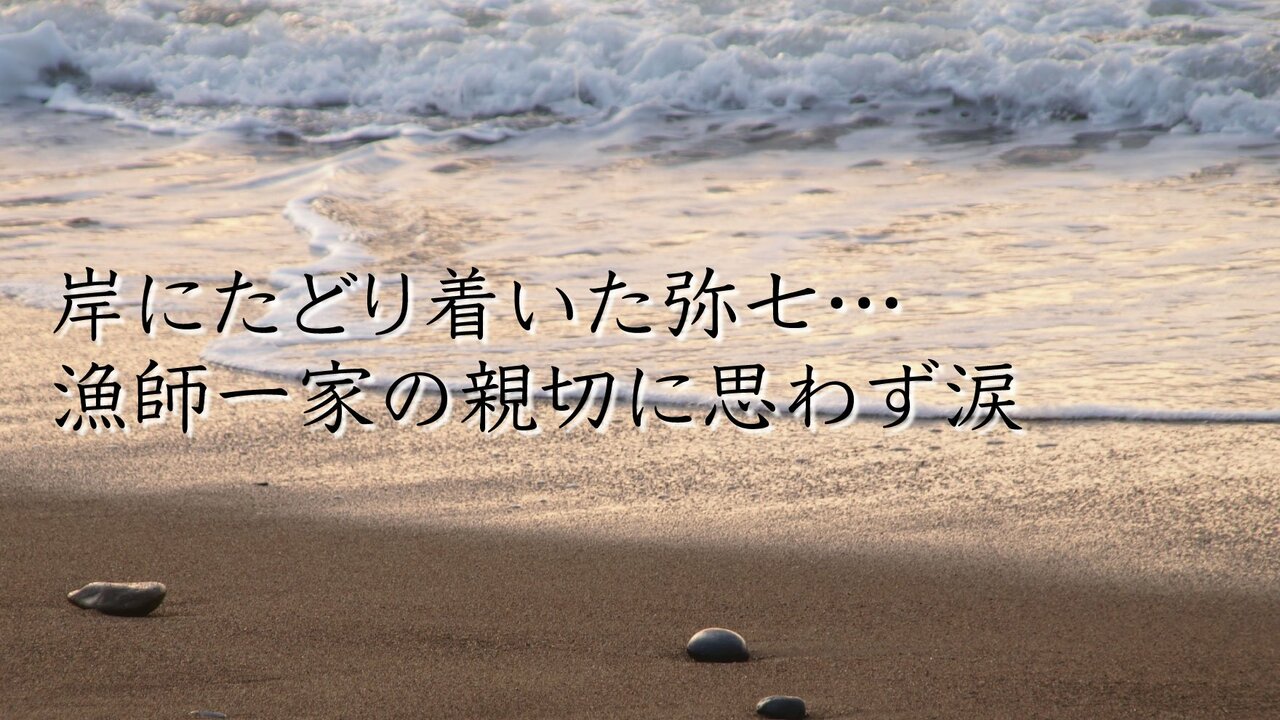弥生編
あの日の篝火の傍での出来事は、誰が見かけたか、あっというまに村中に広まり、その後しばらくの間、村一番の話の種だったからだ。
【人気記事】JALの機内で“ありがとう”という日本人はまずいない
「娘は、私の姪でユィリと言いましてな、気立ても良いし、里の若者どもからもよう好かれております」
「まあ、そのことなんだが……」
丘の長は、なぜか浮かない顔をした。
「ああ、どちらで暮らすかという問題はありますな」
里の長はしたり顔で言った。これまでも、キナの様に、丘の娘が里に嫁いで来る例はたびたびあったが、逆はほとんどなかった。
里者の方がそういう面では保守的な習慣を持っており、また、概して里の方が食べ物の蓄えに余裕があるのが主な原因であった。
「アトウルが、入れ墨をして里に入るという形でも良いでしょう。みな喜んで迎えるでしょうし、言葉には苦労するでしょうが、暮らしにはすぐ慣れますとも」
「里のや、まあ待て。お前たちの先祖が、海から大きな船でやってきて、七つの代になる」
ここで初めて、キナの通訳が必要となった。
「言い伝えによれば、船から降りて来たのは三十人ばかりであったそうじゃ」
丘の長は指を三本立てて言った。
「そしてその時、あなたがた丘者が助けてくれなかったとしたら、その三十人は、きっと野垂れ死んでおったでしょう」
里の長は、威儀を正して頭を下げた。里でも、自分たちの父祖が、西の海の彼方から、大きな災難を逃れてきてこの地に漂着したこと、そして、そのような大きな船を造る技術をはじめ、西の地では持っていた、様々な文化が失われてしまったことを語り継いでいた。
「いやいや、里者たちも、わしらが食べ物に困った時や、山の向こうの奴らがのさばってきた時には、よう助けてくれた。お互い様じゃ」
丘の長も笑って頭を下げた。そうなのだ。丘者と里者は、生活様式が異なるおかげで、ほとんど利害がぶつからず、それぞれの作る物や採る物の交換は、お互いに大いに満足のいく取引であり、むしろ敵と呼べるのは、それぞれの同類なのだった。
里の村にとっても、精悍な狩人たちである丘の村との強固な同盟関係は、湾の向こうの村に対する大きな牽制になっている。里の長は、家の者を呼び、酒と干し魚を持って来るように言った。