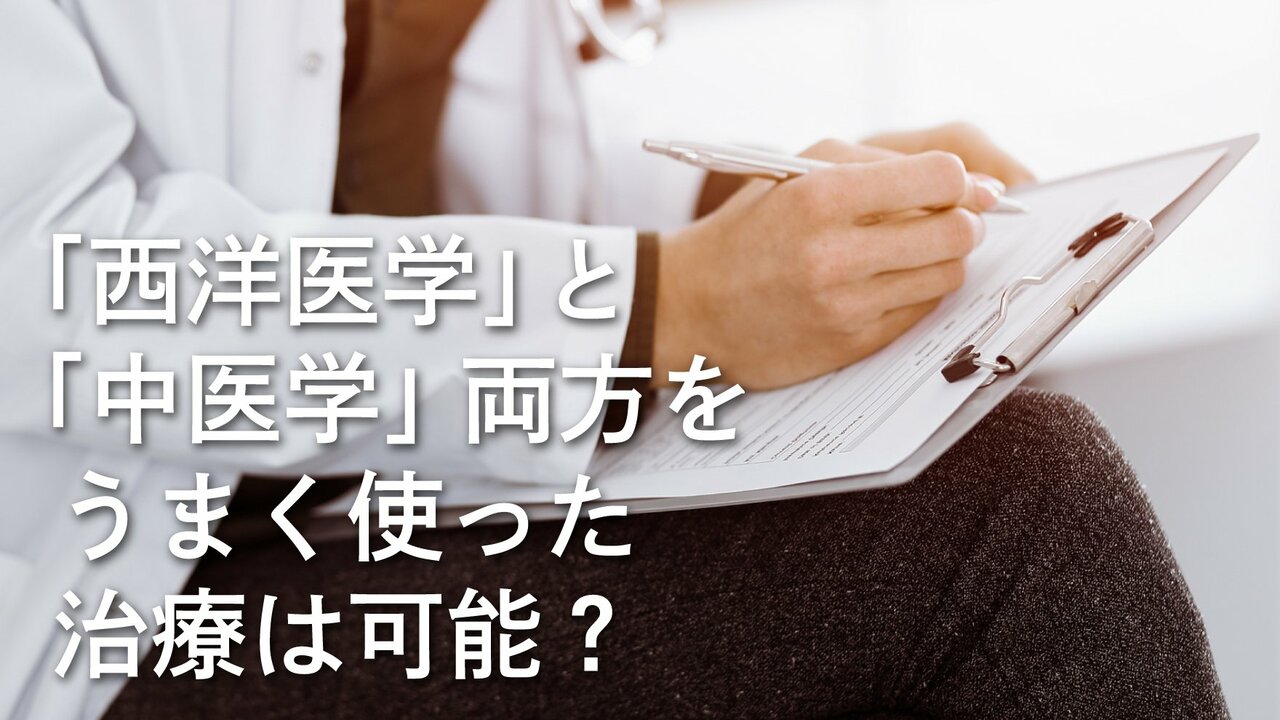僕は彼女の後ろについてよろよろと自転車を走らせた。街灯とたくさんの店の光で溢れる駅前で自転車を降りると、ケガの状態がさらによくわかった。
(これは痛いだろうな)
ケガに慣れている僕でもそう思うほどだ。いまだに血がにじみ出ている傷口にチェーンの油もついて染みて痛むのか、無言の彼女の顔は険しいままだ。
「ちょっと待っててくれる?」
言うが早いか、明るい光を放っていたドラッグストアに飛び込むと、消毒液入りカット綿、消炎鎮痛軟膏、傷につかない絆創膏を買ってきた。汚れを落とす水もないし、油が付いているし、こんなものだろう。これらはケガの絶えなかった僕が昔からよく使っていたものだった。
「化膿したらいかんからよかったら手当するけど」
店の前のベンチに俯いて腰掛けていた彼女に問いかける。少し考えていたようだけど、静かに僕に向き直った彼女は、さっきより青ざめた顔で呟いた。
「ごめん、お願い……」
(まあ体育会系の女の子でもなければ、そんなにケガすることもなかったんやろうな)
そんなことを考えながら僕は手を動かした。
※本記事は、2020年11月刊行の書籍『桜舞う春に、きみと歩く』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。
★邪気指数、新陳代謝指数、正気指数
漢方の立場で見た、主人公沢波俊樹の体調を示します。本来、漢方にはこんな指数はありませんが、これに近いことをもっと細かく考えながら対処します。これらの変化は人によって異なります。
●邪気指数
体の中に溜まった不要なもの(邪気)の量を示す指数です。邪気は誰の体の中にもあります。食事の質や偏り、嗜好品、食べる時間などで変化しやすく、新陳代謝指数が下がり排出が悪くなることでも上昇します。邪気がかゆみの元にもなることがあります。ここでは50~150を正常範囲とします。150を超えると体調を崩しやすくなります。ただし、正気指数が高い方は、邪気指数が高くなっても体調を維持することができます。
●新陳代謝指数
体の中の、良い物(正気)、悪い物(邪気)がどれだけスムーズに動いているかを示す指数です。通常人が生きていく中で、良い物(新)を取り入れて、いらないもの(陳)を排出しています。それがスムーズに動いていること(代謝)が大切です。飲食の消化吸収、大小便での排出、血流、発汗などトータルの指数とします。運動不足やストレスなどで低下します。ここでは70~100を正常範囲とします。新陳代謝指数が下がると邪気指数が上がりやすくなり、下がっているときには正気指数も下がっていることが多くなります。
●正気指
数
体の元気(エネルギー≒正気)の指数です。バランスの良い飲食で満たされ、ほど良い休息をとることで作られます。逆にストレスや過労で低下します。正気が少なくなると、体のだるさや意欲の低下がみられ、免疫をコントロールする力が弱り、かゆみを抑えられなくなり、症状が悪化します。ここでは70~100を正常範囲とします。正気指数が高いと新陳代謝指数は上がりやすく、邪気指数が少々高くても生活に支障はありません。