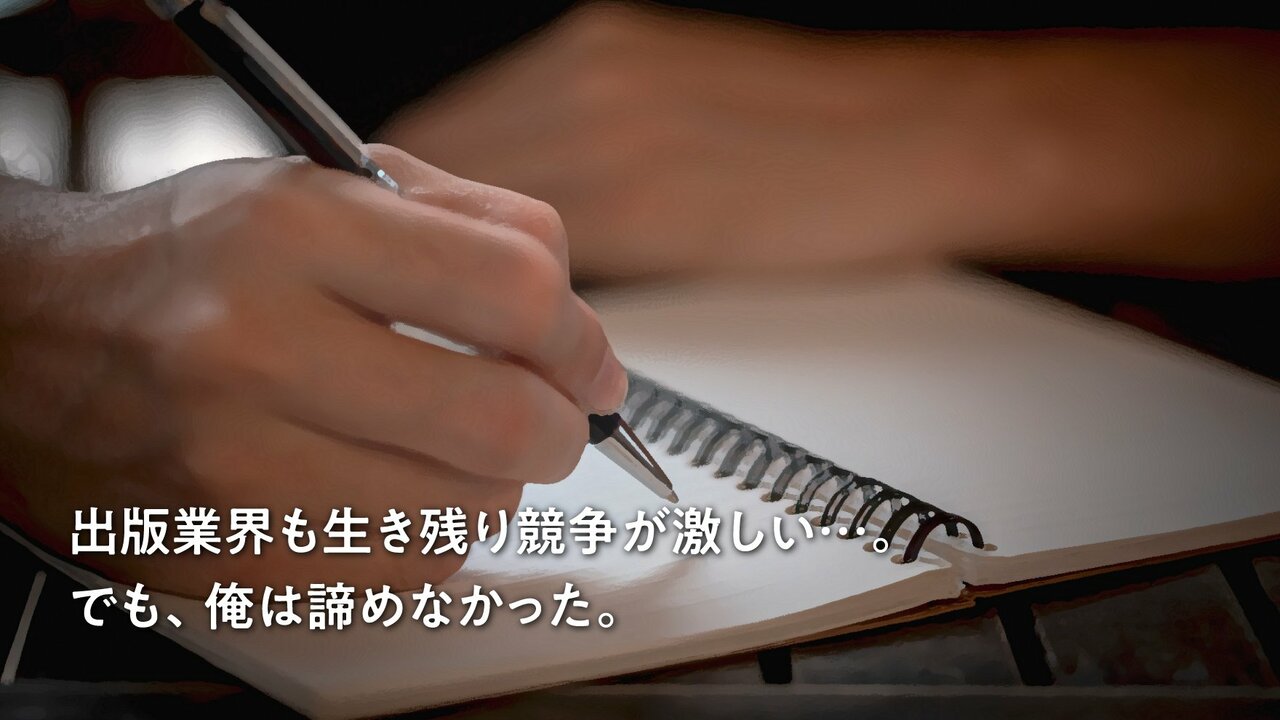もうしばらく、芸術家然とした男でいさせてくれないか
「沙希、ありがとう」
「御礼なんてやめて。俗世間から超越した芸術家然とした研ちゃんが好きなの」
沙希の言葉は俺を気恥ずかしくさせたが、揺らいだ心が次第に落ち着いてきた。
「沙希。悪いがもうしばらく、その芸術家然とした男でいさせてくれないか」
「そうこなくちゃ」
そう言って沙希は屈託なく笑った。それから、取り組んでいる画家と妻の物語『彩誕(さいたん)』の執筆に励んだ。非常に繊細な比喩表現を求められる作品なので完結までにはかなり時間がかかると思うが、書き上げれば芸術性の高い作品になるはずだ。
だが、これまでの持ち込み原稿については相変わらず出版社の反応はない。はたして読んでくれているのだろうか。出版業界も生き残り競争が激しくなり、難解な純文学に対しては余裕がなくなっているのだろう。
でも諦めるわけにはいかなかった。かけがえのない家族のために。
沙希が雫を残して実家に帰るのは初めてのことだった。数日前に沙希の母親の安代から長い電話があった。それからというもの、いつもの沙希と明らかに様子が違った。