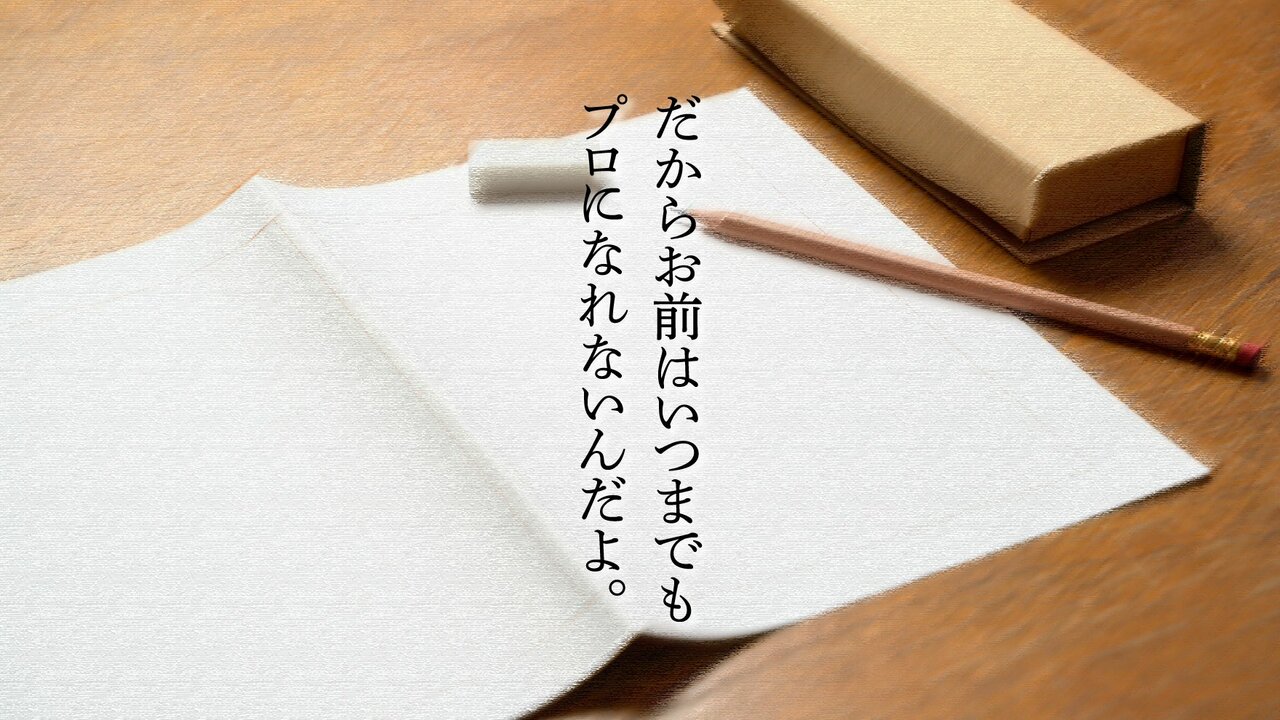持ちかけられる「小説家のアシスタント」の話
「芹生。お前は自分の書きたいものだけを書いているだろう」
彼は当たり前の言葉を投げつけた。
「自分の書きたいことを書いて何が悪い」
「お前はそんなことを言っているから本を出せないんだよ。わたしから言わせれば、お前の創作はマスターベーションだ」
「なんだと」
「いいか芹生。わたしは常に読み手を意識して創作してきた。読まれるための作品を書いてきた。そのために必要なことはなんでも取り入れた。お前は逆だ。自分の目線でしか書いていない自己満足の作品だ。だからいつまでもプロになれないんだよ。読まれない小説を書いて満足できるのは同好会だけだ。プロの作家として、その努力をしないことは怠慢だ」
彼は、俺の深層意識に密かに横たわるジレンマを突いてきた。それは同時に最も反発を呼び起こすツボでもあった。そして深層から表層へ、怒りとなって吹き上げた。
「俺には俺の求める道がある! お前にとやかく言われることはない!」
「そう興奮するな。まあいい。今日はこれ以上芹生と話している時間はない。その気になったら連絡をくれ。それなりの報酬は払う。では」