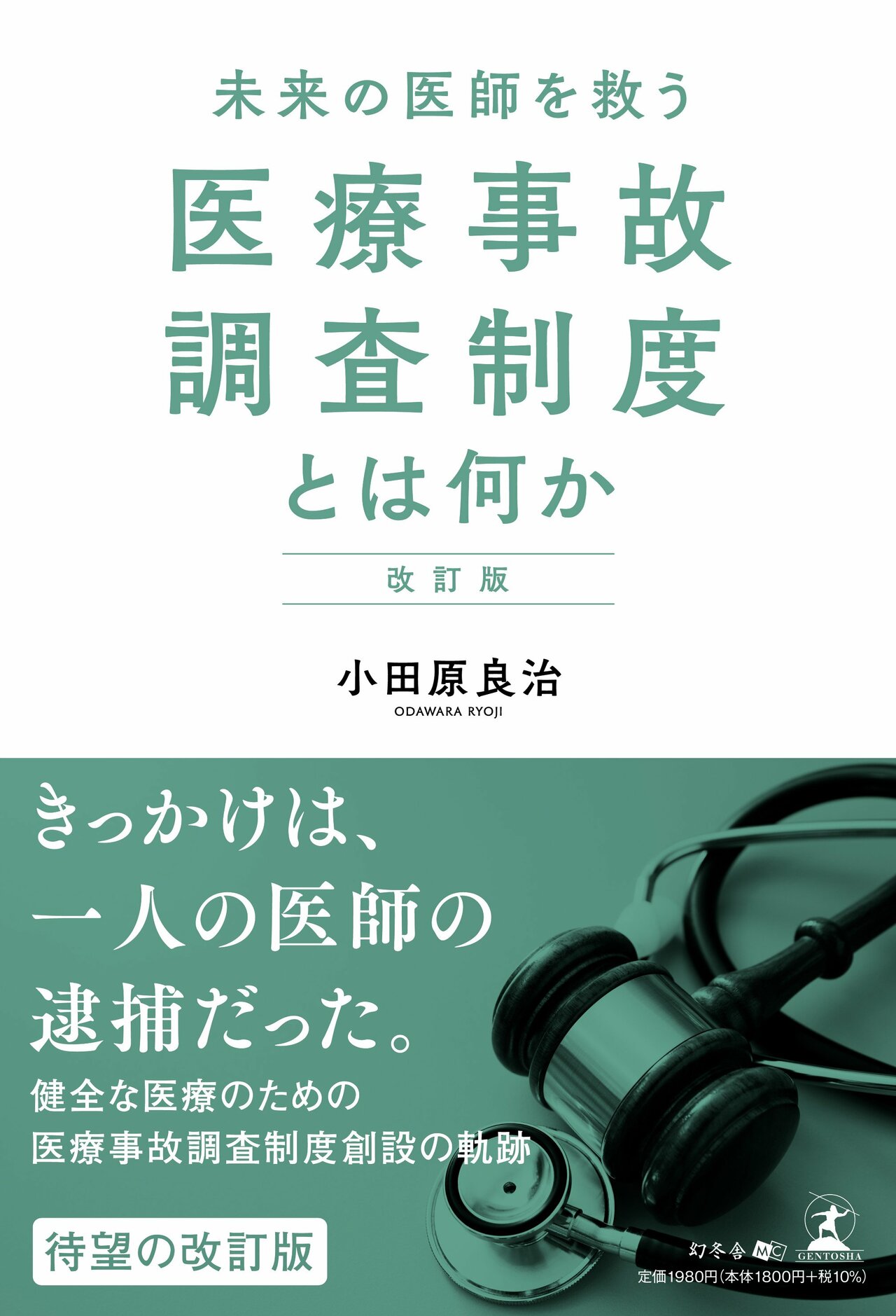③東京高裁は①、②を踏まえ、死体の『検案』時点を病理解剖時の平成十一年二月十二日午後一時頃であると認定している。「異状死体」の判断は「外表異状」によることを明示した判決であるが、控訴審においては、検察も「異状」の認識時点を病理解剖時点とすることを前提として訴因変更を行っている。
④院長の共謀については、病理解剖時のポラロイド写真を見て、なお且つ死体に「外表異状」があるとの報告を受けながら、「届出しない」とのそれまでの方針を転換しなかったことが共謀の根拠とされたようである。「外表異状」に根拠を置き、病理解剖時点が起点であるとする論旨と整合する論旨で、病理解剖時点での「外表異状」を認識した後の院長の対応を問題としたのであろう。
また、医師法第21条は、『検案』(死体の外表を検査)して、異状があれば届出義務が発生するとするものである。死亡した者が診療中の患者であったか否かを問わず、死体の外表に異状があったものを届け出るとすれば、憲法第31条の罪刑法定主義に違反することもない。
また、医師法第21条が要求しているのは「異状死体」があったことのみの届出であり、それ以上の報告を求めるものではないから、「診療中の患者死亡の場合であっても、自己に不利益な供述を強要するものではなく、届出義務を課すことが憲法第38条1項(自己負罪拒否特権)に違反することにならない」と判示している。
異状死体等の届出義務規定は、もともと、診療関連死以外の死体についての司法警察捜査への協力規定であった。同条届出義務違反に問われた大審院判決も東京地裁八王子支部判決も変死体についての届出義務違反である。従って、自己負罪拒否特権と衝突することはなかった。
しかし、東京地裁が自己が診療していた患者の死亡に医師法第21条を適用したことから、自己負罪拒否特権との整合性という新たな問題を引き起こした。医師法第21条をそれまで対象とされていなかった診療関連死領域に適用を拡大したことにより、医師法第21条そのものが憲法違反ではないかとの疑念が提示されることとなる。
東京高裁は、医師法第21条の検案の定義は死体の外表を検査することであるから、死体の外表を検査して異状を認めた場合には警察への届出義務が発生するとの客観基準で合憲限定解釈を行った。東京高裁判決は、医師法第21条にいう「異状」を限定解釈することにより違憲を避けたのであろう。
当時の状況とは異なり、現在、医療事故調査制度が医療事故の再発防止の制度として適切に運用されつつある。また死因究明等推進基本法も成立した。東京都立広尾病院事件解決の手段として、一部診療関連死に拡大された医師法第21条の適用も、本来の診療関連死外の規定へと回帰すべき時に来ていると思われる。