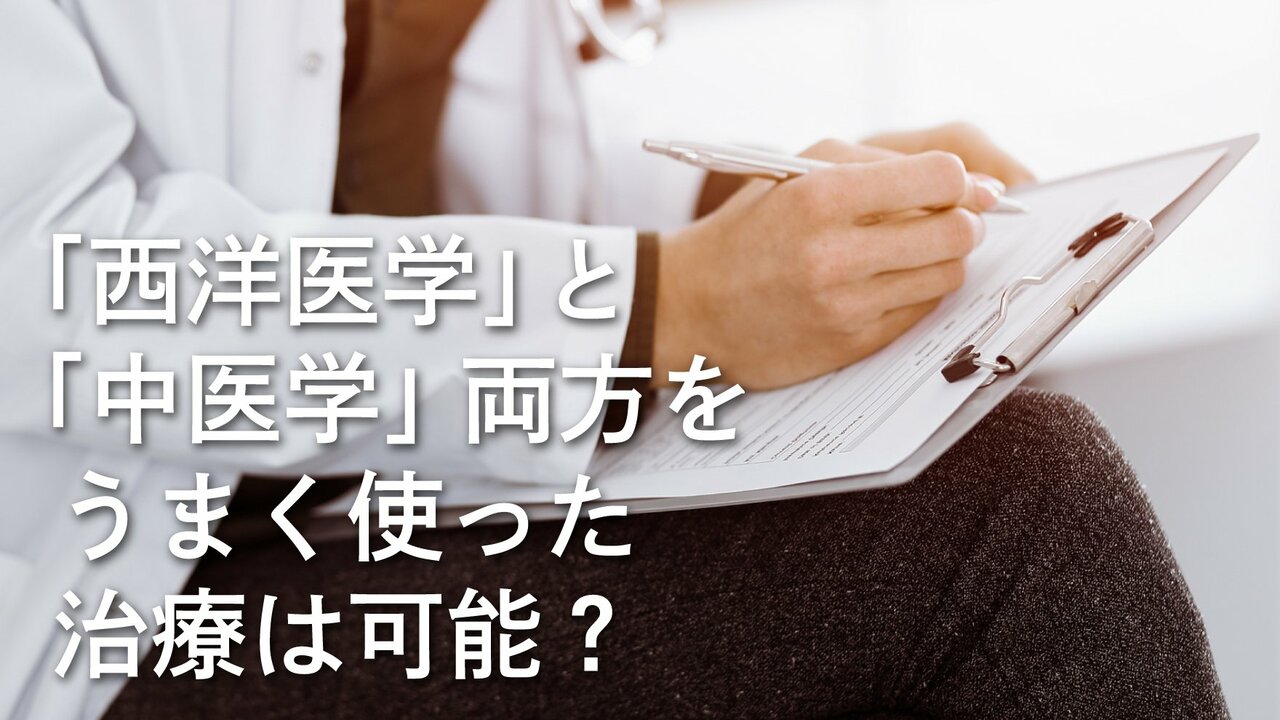春の出会い
邪気:90 代謝:80 正気:80
今日も挨拶こそたくさんしたけれど、どうにもうまく話を合わせることもできずに、最後の英語の授業を受けていた。まだウォーミングアップのような内容だから、先生の話をぼんやりと聞きながら、ただ背中を丸くして前を向いていた。
「なあ沢波。この授業、おもろなくない? なんか高校の英語とそう変わらんやん。思わん?」隣に座っていた内村和也(うちむらかずや)がさもつまらなそうに机に片肘をついて呟いた。僕は、二まわりほどごつい体躯の男になんのモーションもなく呼ばれ、あからさまに驚いて振り向いた。彼は身じろぎもせず、斜めに目だけ向けてきた。
彼とは入学式の後に簡単な挨拶を交わした記憶はあるが、それ以後話をする機会はなかったから、僕にとってはいまだはじめましてだ。
(へーこいつもう名前覚えてくれているんだ)
何よりもそれに感心したが、僕は肝心の彼の名前は思い出せない。
「そうやにゃぁ。おもろうないにゃぁ」
気まずさを隠すように返事をした。人付き合いは苦手でも人に興味がないわけではない。けれども名前を覚えるのは苦手なのかな、と自分の不得手に今気が付いた。
すると内村は何か面白いものを見つけたように、大きな顔にくっついている小さな目を大きく開いた。
「え? 沢波、どこ出身なん?」
大きく僕に向き直り体半分近づけて、興奮を抑えるかのように小声で訊いてきた。授業はおもしろくないが、邪魔しないように気は遣っているようだ。
「高知やけど」
素直にそう答えたとき、教壇の教師がじろりとこちらを見た。それに気づいた僕は、ばつが悪そうにすぐ頭を下げた。
同時に気づいた様子の内村は「僕は知りません」というような顔をして視線を逸らしている。じーっと見ていると目だけ動かしてこちらを見てニヤニヤと笑った。
以来僕は内村組に籍を置くことになった。なんだかすごく単純な理由だ。彼の名前は別の男子に呼ばれているのを聞いて思い出した。もちろん内村にそんなことは話せず、最初から知っていたかのように振舞った。