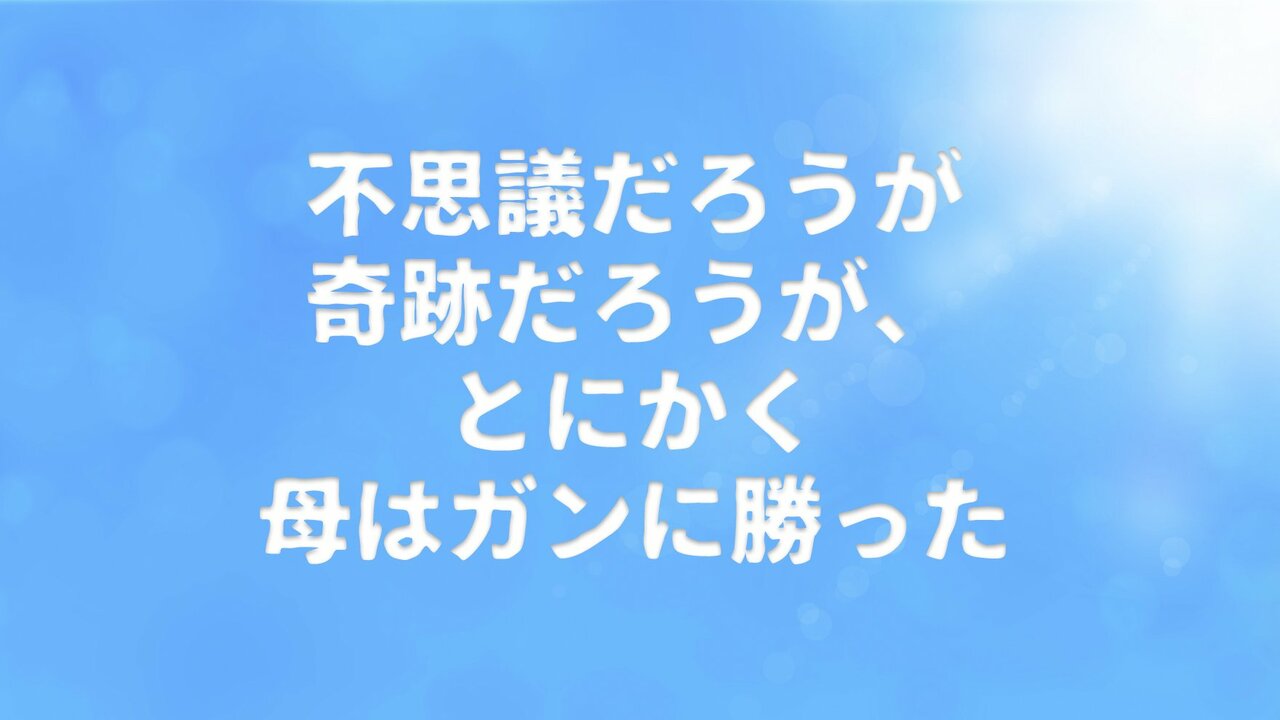第一章 青天霹靂 あと377日
二〇一六年
二月二十八日(日)晴
食事量が元に戻ってきたのが嬉しい。でも、やはり脳の具合が心配だ。「うー、うー、あー、あー」を繰り返し、ごく簡単な単語さえ出ない事があり、そんな時は苦しそうに顔を歪めて身体を震わす。またある時は、目を開けたまま夢にでもいるかのように呆然と空くうを見つめ、急に正気を戻し「お母さんこと助けて……、お母さんが死ぬ時は、一日も早く死なせて……」などと言って私を困らす。
「お母さん、よく聞いて……。もし、夢の中でワケが分からなくなったり道に迷ったら俺を探しな。俺はいつだってお母さんの道標べなんだから……。お母さんの手を引いて、ちゃんと連れ帰ってあげるから、心配しないでいいよ……。いいかい、わかったね」
三月一日(火)晴
母を背負いて、見知らぬ街で道を探して歩く夢をみた。
私の他に頼る者のない母が可愛く、愛おしくてならない。
降りだした小雨に気持ちが萎(な)えるも、我が背に母を感じているだけで心細さが癒える気がしていた。
嗚呼 母よ、幼き私を背負いし貴女も、こんな想いで辛い道を歩いていたのでしょうか。
独りではないという心丈夫は、背負う背負われるが替わり、腹の温みが背になっても同じであった。
お母さん、あなたの背中は、いつだって私のシェルターでしたよ。
*
母には、看護婦時代の同僚だった太刀川さんと坂場さんという二人の親友がいる。今だ行き来をする仲である二人からは、たびたび見舞いの品や手紙が届き、母はそれをいつも楽しみに待っている。
今日は、筆まめな太刀川さんから何度目かのハガキが届いたもので、早速お礼の電話をした。
「ありがとう、ありがとう」と、しきりに繰り返す母の顔は次第に辛そうな表情になり、ついには私へ電話を突き返しメソメソと泣いてしまった。
何年か前、二人が初めて安曇野を訪ねてくれ、最後に長野駅まで送った帰りの車中、「やっぱり、昔の友達は良いもんだねぇー」と、母がさめざめ落涙したのを思い出す。