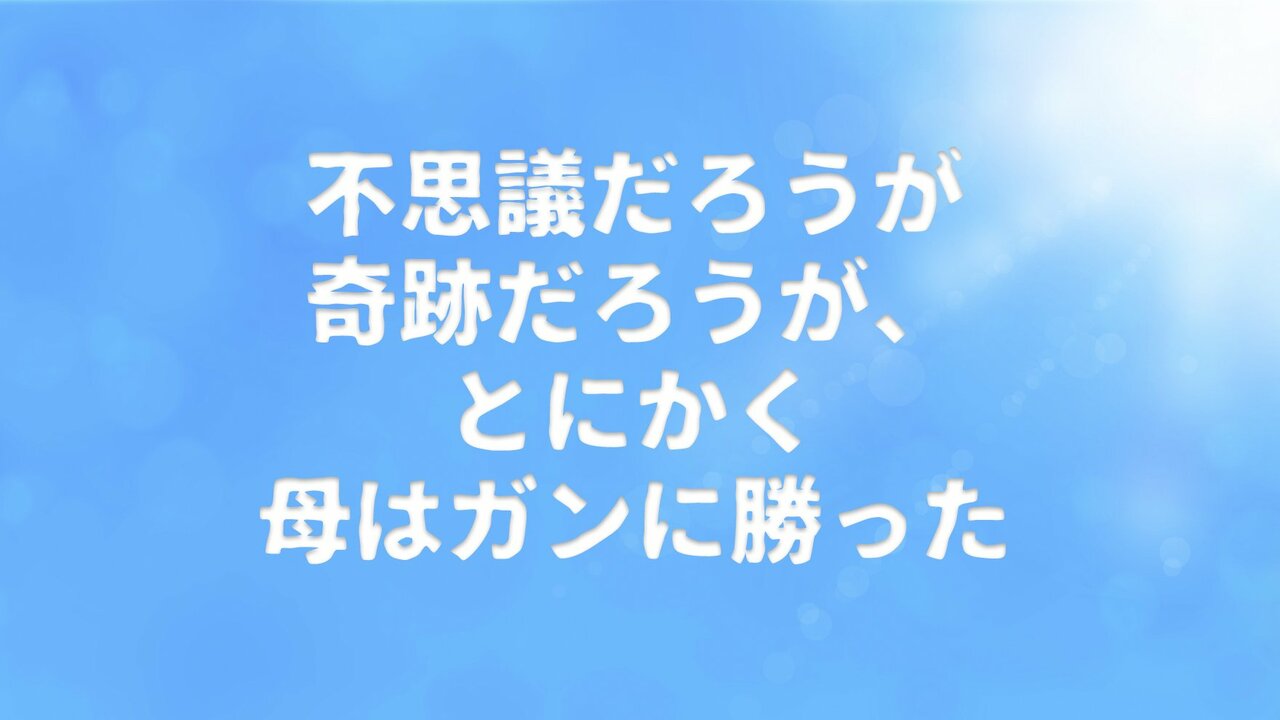第一章 青天霹靂 あと377日
二〇一六年
三月五日(土)晴
母の待ちわびた兄が、酸っぱいイチゴを持ってやってきた。「これは、ちょっと早かったなぁ……」と、顔をしかめる兄を見て母が愉快そうに笑い、その酸っぱいヤツをヘタごと口へ放り込む。
母はいつもそうだ。健康のためと言いつつ、ニンジンの皮もそのまま、ピーマンはおろかカボチャの種までそのまま煮てゴリゴリと食べてしまう。「イチゴのヘタなんか旨いのかい……」と、聞けば、「うん、美味しいよ」と、母。
それならば……と、試しに私も食べてはみたものの、当然うまいはずもない。兄は「おいおい、ボケたんじゃねぇかと思って驚いたぜ……」と、カッカッと笑う。
天気が良いので、病院からほど近い、知り合いの店まで散歩に出かける事にした。珍しく、母の方から外へ行きたいと言ったからだ。
目的地が遠目に見えるくらいまで来たところで急に風が吹きはじめ、母が「寒い」と言いだした。私と兄は上着を脱いで、母の肩と膝にかけてあげ、また歩きだした。
そして間もなくのこと、母は例のごとく「ありがとう、ありがとう」と、しきりに連呼し始めた。はじめ兄は「わかったよ、礼にはおよばねぇよー」と、言って車椅子を押し続けていたが、次第に、それが尋常ではなくなってきて、はたと気づいた。
やはり、これは嫌というサインなのだ。「もう、すぐ近くだけど、また今度にしようか……」と、来た道を戻ろうとした瞬間、母の発作のような“ありがとう”は治まった。
後日、言語聴覚士の伊藤さんに教わりようやく合点した。
「それは、失語症によくある一つの症状です。言葉が発せなくなってくると、最後に、その人が一番こだわっている言葉だけが残ります。