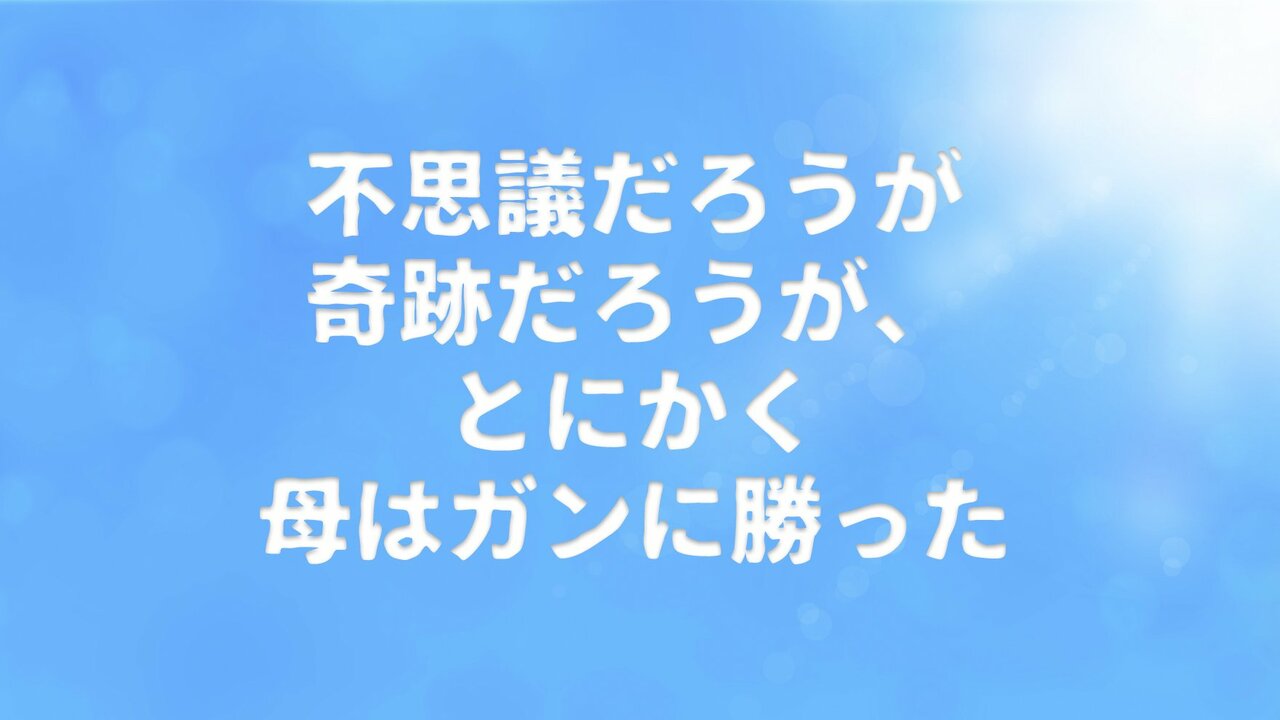第一章 青天霹靂 あと377日
二〇一六年
二月五日(金)
水差しの水を替えようかと部屋を出ると、言語聴覚士の伊藤さんと鉢合わせ、「母からの伝言がある……」と、廊下の椅子へいざなわれた。
このところ、とみに母の発語能力は落ち、喋る事がとても苦しそうになってきた。それで、言語リハビリの時、言葉の練習をするついでに母が伊藤さんへ腹蔵を託したのだ。
「それでは読みますね……」と、メモを出した。
「ケイソ、フコイダン、薬は安くないんだよ。
生活を切り詰めてまで、必要ない。
私の身体はもう治らないんだから、高い薬は買わないで。
心ぐるしいから。
誰も怨むな。病気のことも……」
頭をガツンと殴られたような思いがした。
覚悟と言うか、諦めと言うべきか……、いずれにしても、母が心を既に決めているであろう事は分かっているつもりでいたが、こうもはっきり言われてしまうと狼狽(うろた)える外ない。
他に頼りとするべき術(すべ)はなく、電位治療器と市販薬だけが頼みの綱であるというのに……、自らの延命より息子の懐具合の方が心配であると言うのか。