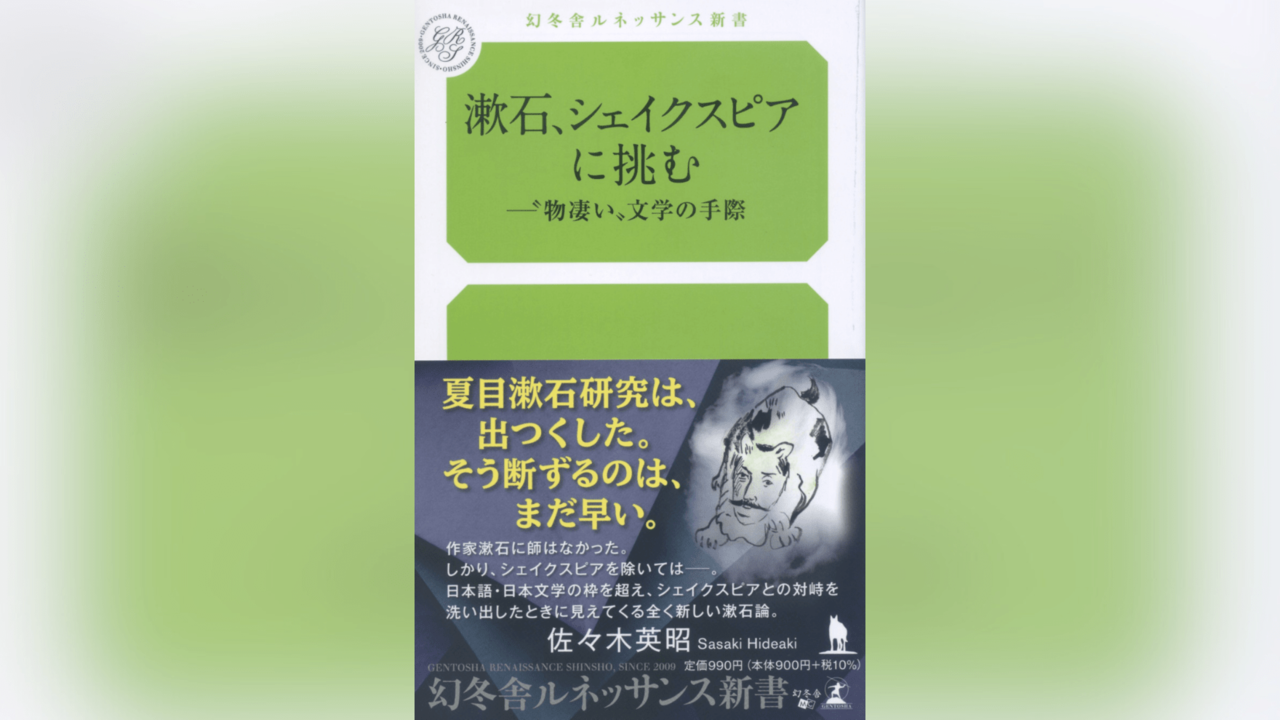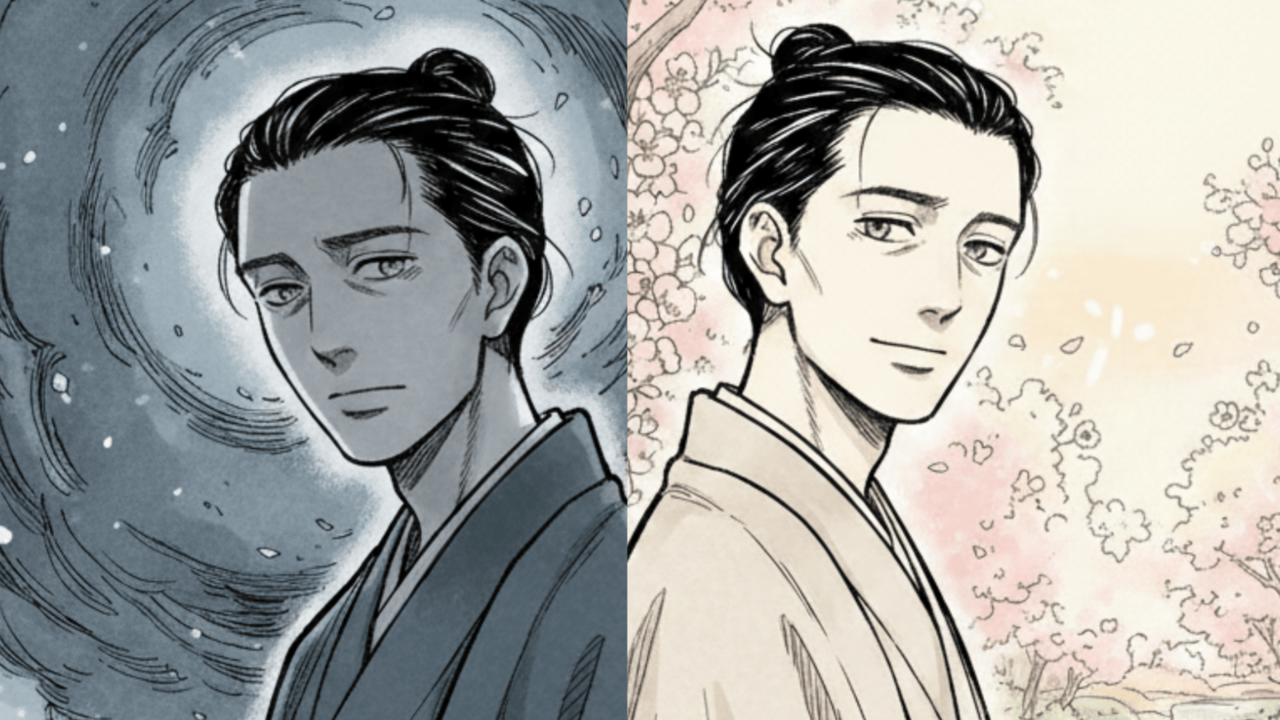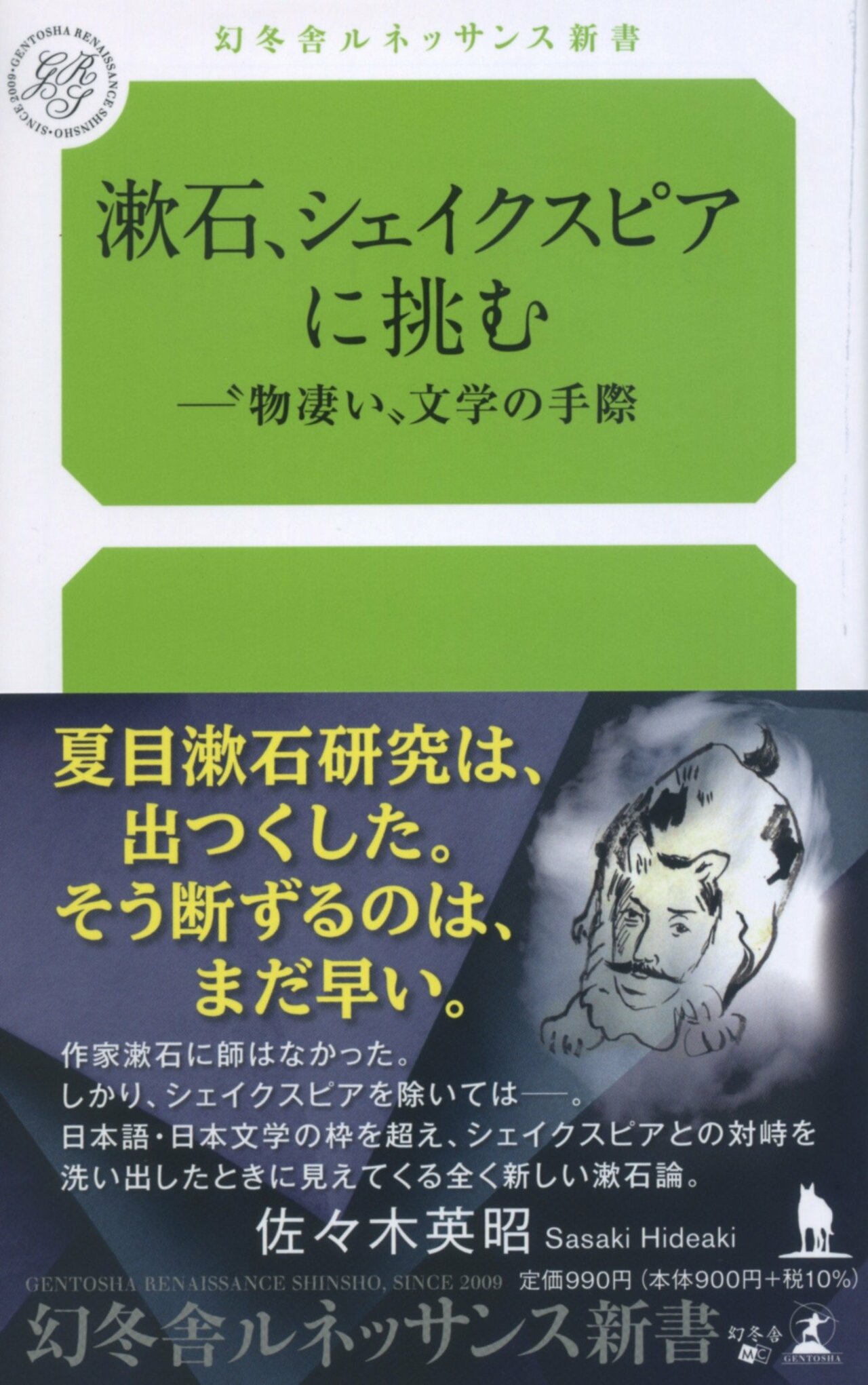【前回記事を読む】登場人物が自分の意志で動くとは? 漱石の『則天去私』とシェイクスピアの書き方
序章 ぎょっとするオセロ・マジック
文学理論としての「則天去私」
「シェイクスピアは特定の人物の肩をもったり、特定の主張を支持したりすることを、徹底的に避けているという事実」を力説してやまないのは、シェイクスピア劇の長年の研究者、喜志哲雄である。
「どれほどの悪人でも全面的に否定したりはしないし、どれほどの善人でも全面的に肯定したりはしない」と(『シェイクスピアのたくらみ』〔岩波書店、二〇〇八〕四頁)。
「則天去私」の体現者としてシェイクスピアの名を挙げた際の漱石の意識にあったのもこれに近い認識であったことが、森田の言葉からは伝わる。
さて、「折に触れて云つてゐられた」という時期がいつごろからのことなのかは不明だが、この口ぶりからすると、それは『明暗』を書くころに降って湧いたもののようには受け取れない。
この意味での「則天去私」なら自分は二年前の『こころ』ですでに実現しているという自負を、実は漱石はもっていたのではないだろうか。
というのも、少なくとも漱石のいう「結構」(その概念は第五章に詳述する)を軸に考えた場合、シェイクスピア劇が影を落とす作品としては『虞美人草』以降では『こころ』を挙げるほかなく、『明暗』もその前の『道草』(一九一五年)も後景に退くほかないからである。
『こころ(下)』の予告編としての役割を負う「上先生と私」の若い「私」は、「先生は美しい恋愛の裏に、恐ろしい悲劇を持つてゐた」として、さらに続く五行のうちに同じ語を四度も繰り返して「悲劇」を予告している(十二)。
まさにその「悲劇」の展開となる「下」には、すでにふれた「黒/白」両面の並立に「ぎよつとする」、物凄い場面にいくどか出会うほか、多岐にわたる劇的な技巧が認められるが、その多くにシェイクスピアの世界に通ずるものを探知することができるのだ。
さらに踏み込んで言えば、「悲劇」の誘因となったように見える人物を咎めることもなく、「私は私の過去を善悪ともに他の参考に供する積です」(五十六)と閉じられる「先生」の私語りは、それこそトルストイにこびりつく、「悪人」を懲らしめ「善人」に報いる類の「私」をすでに離脱している。
つまり、語られる「先生」自身を含む諸人物を「神」的な公平さで上空から眺めるのに近い趣があって、それはシェイクスピア劇の大きさに包まれる感じに近似している。
こうした通有性は、漱石がシェイクスピアから学びとった結果なのか、それとももともと漱石自身の資質としてあったものがシェイクスピアの作風に似ていったのか。
答えはそれこそ「両面がある」ということになるはずで、厳密な線引きは不可能だろう。ただ、学びの形跡を明らかにしていくに足るだけの資料を、幸いにも漱石は残してくれている。
それらに光を当てていくことが第一章以下の仕事となる。