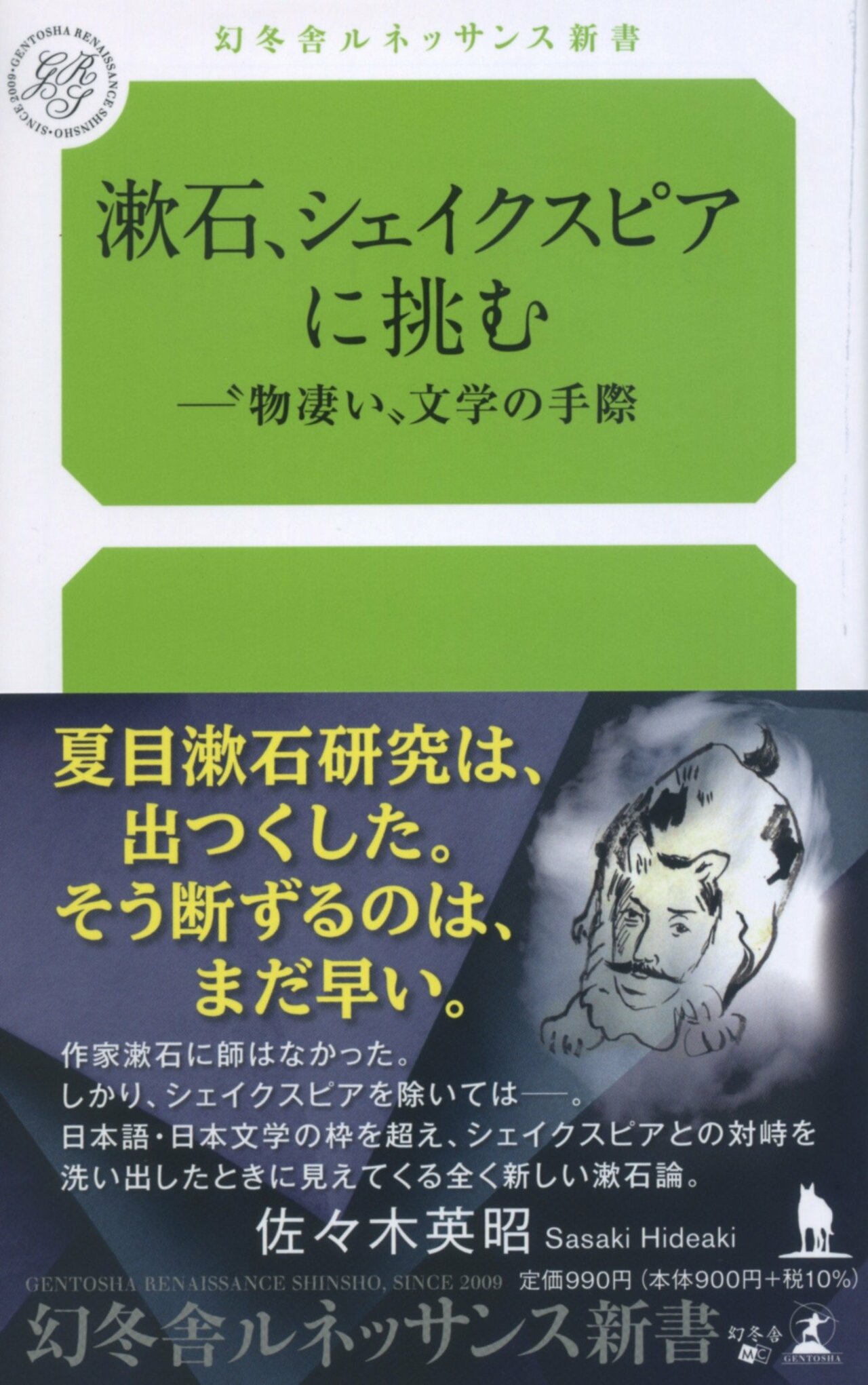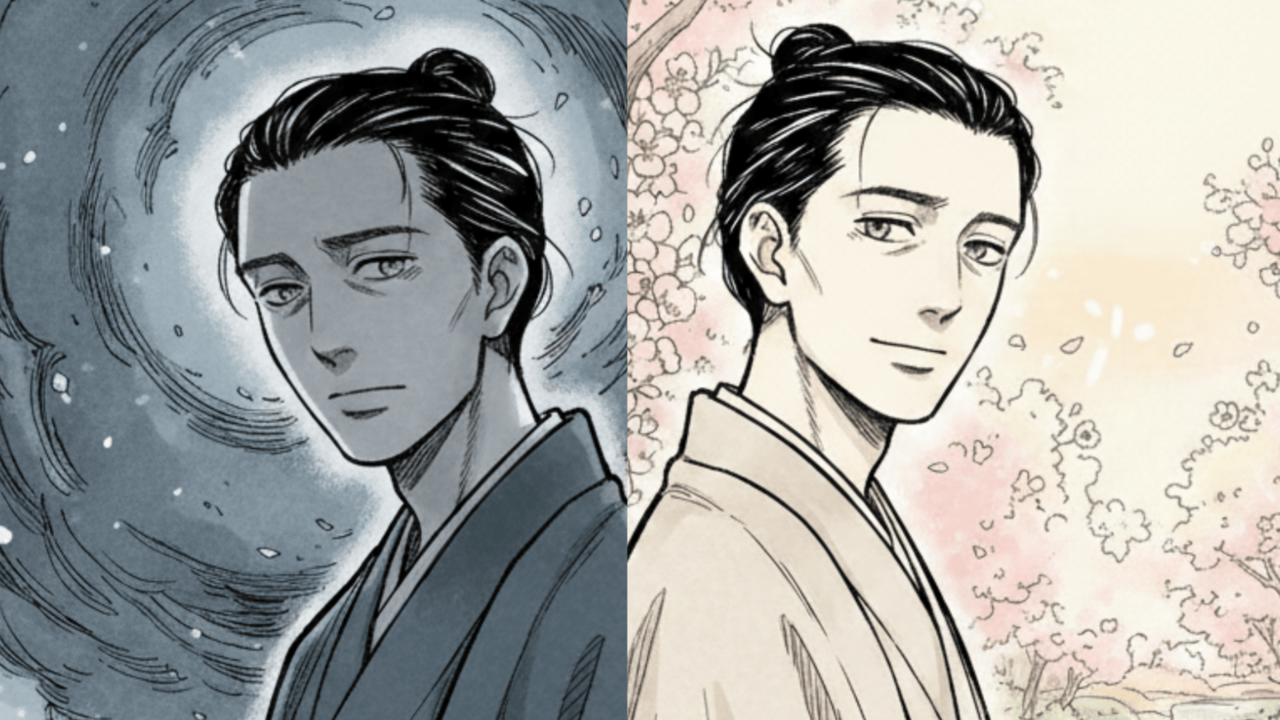第一章 沙翁の筆端神(しん)あるを知れり――『リチャード三世』『ジュリアス・シーザー』
心をかきむしる「悪人」シェイクスピア
「どれほどの悪人でも全面的に否定したりはしないし、どれほどの善人でも全面的に肯定したりはしない」という喜志哲雄のシェイクスピア観をひっくり返してみれば、どんな人物にも「両面」があって、「黒=悪」と見えても背後に「善=白」を隠し持っている、という人間観が出てくる。
早い話、たまには「股倉から」見て「君こりや駄目だよ」ぐらい言ってみろと猫が注文をつけた、その『ハムレット』の主人公は、「そもそも客観的な善悪などない、主観が善悪を作るんだ」※1(there is nothing good or bad, but thinking makes it so――第二幕第二場)と言い放っている。
なにごとも「主観」(thinking)次第、「股倉から」覗けば「善」が「悪」に、「悪」が「善」にもなる。
だから主人公で善人であるはずのハムレットは、「俺たちはみんな悪党だ」(We are arrant knaves, all――第三幕第一場)と豪語して平気である。
ところで、この『ハムレット』に言及するにあたって「私が本を読んで、心を一番かきむしられるのはシェイクスピアだ」と書いたフリードリッヒ・ニーチェ(『この人を見よ』「なぜ私はこんなに利口なのか?」4、一八八八〔丘沢静也訳、光文社文庫〕)は、その十年前にはこうも書いていた。
多分彼の気質からして多くの情熱にきわめて近しい交渉をもっていたであろう(劇作家は一般にかなり悪人である)。
しかし彼は、モンテーニュのように、それについて語ることはできずに、情念に関するもろもろの考察を情念につかれた人物の口に託した。(『人間的、あまりに人間的』一八七八、第四章一七六節、池尾健一訳、ちくま学芸文庫)
※1 松岡和子訳(シェイクスピア全集1 『ハムレット』、ちくま文庫)。以下、シェイクスピア作品からの引用は原則として同文庫の松岡訳により、原則を外れる場合のみ注記する。
【イチオシ記事】「抱き締めてキスしたい」から「キスして」になった。利用者とスタッフ、受け流していると彼は後ろからそっと私の頭を撫で…