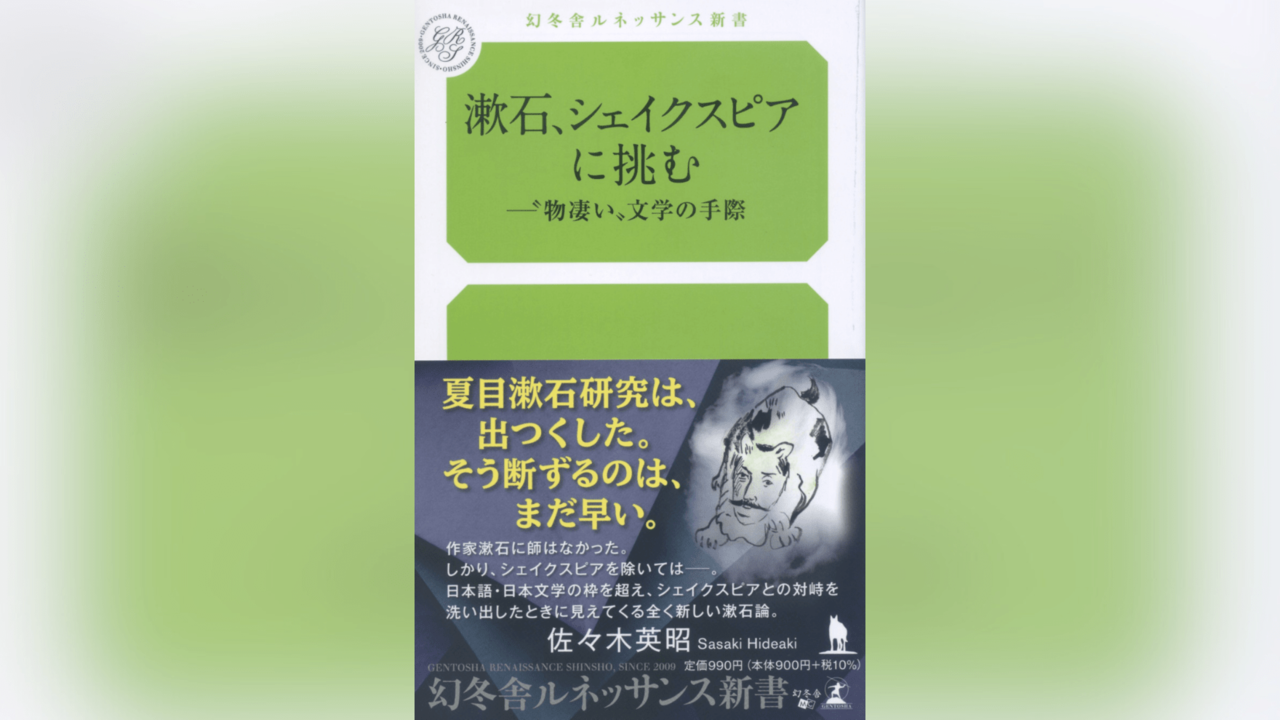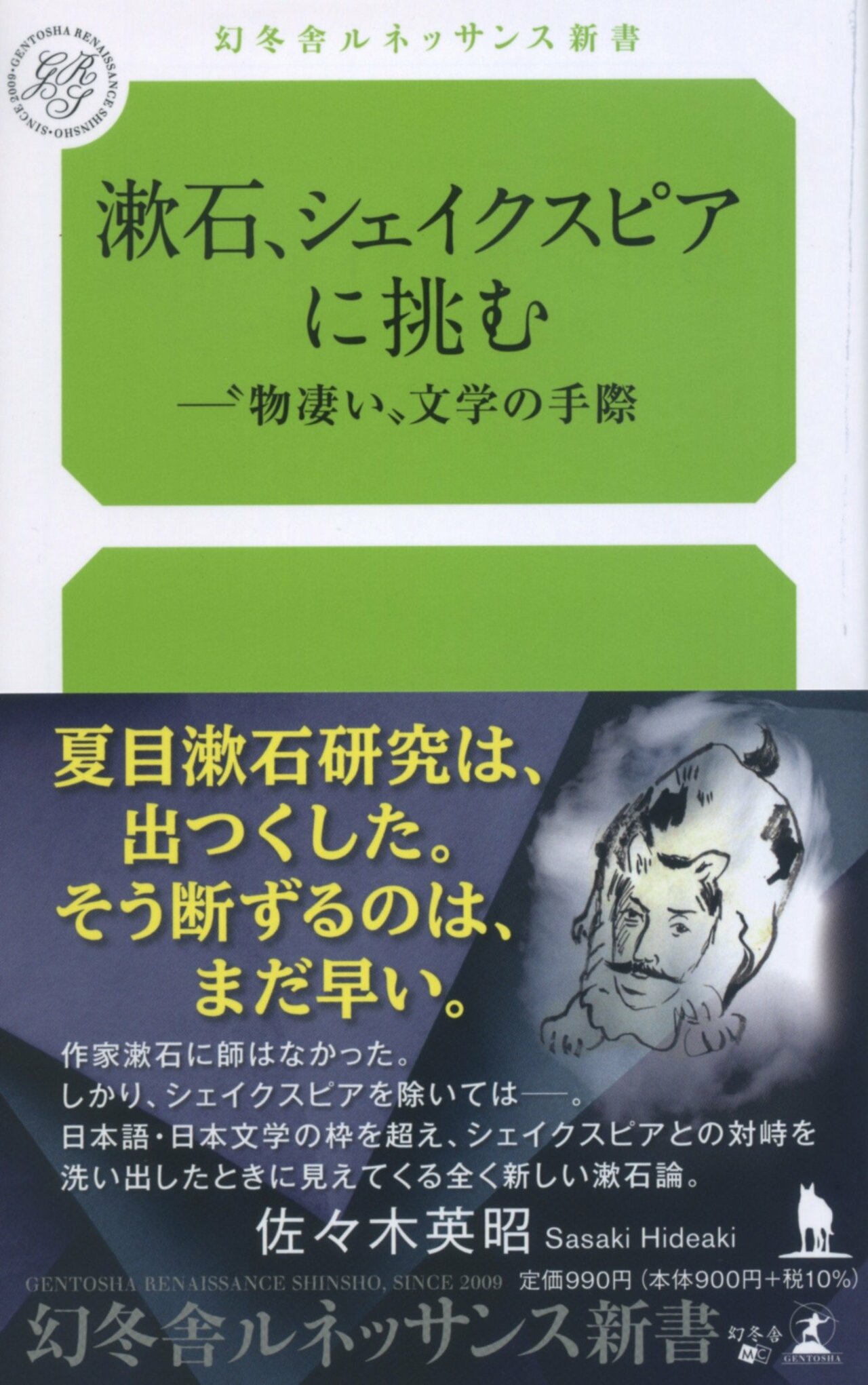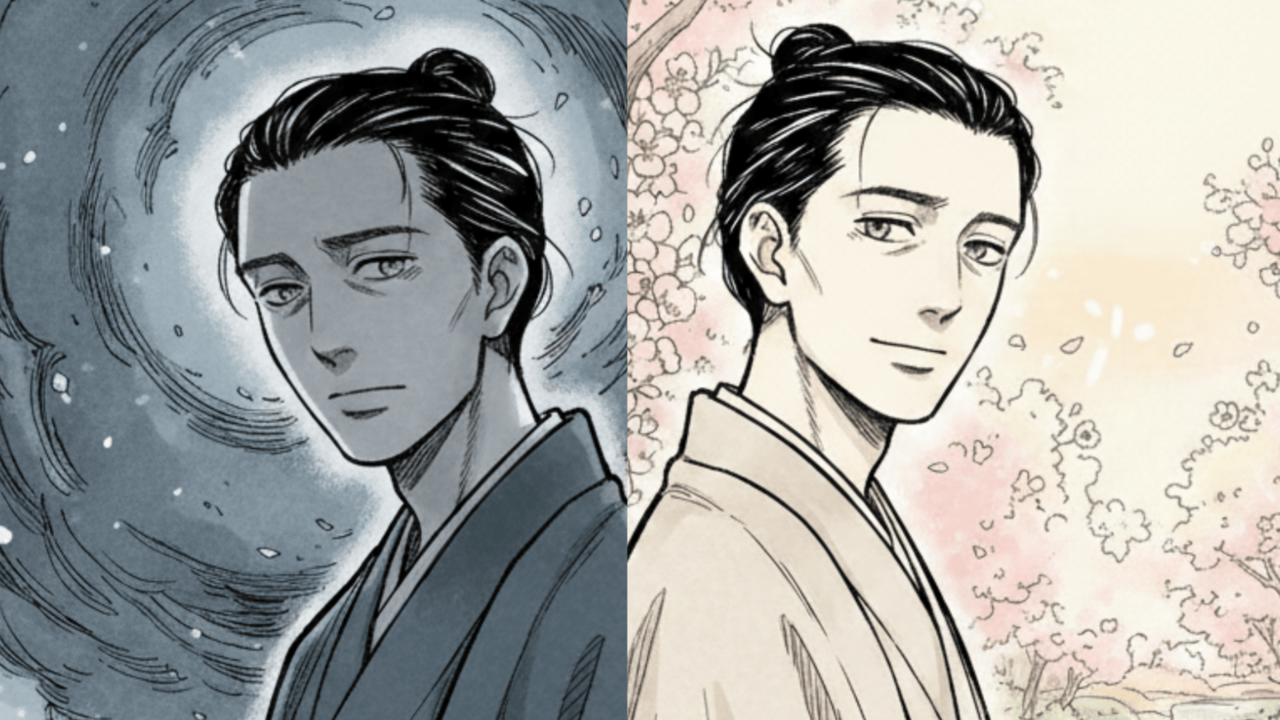【前回記事を読む】漱石とシェイクスピアの知られざる関係。大学生時代、『ハムレット』を読んで「ちっともわからなかった」
序章 ぎょっとするオセロ・マジック
黒白の変化を同一物の上に起こす
『マクベス』と『オセロー』はともに「四大悲劇」に数えられてきた傑作で(他の二作は『ハムレット』『リア王』)、どちらも、「黒白の変化を同一物の上に起す」、オセロ・マジックとさえ呼びたい「手際」を数多くひそませている。
そのような「手際」の好例が、本章冒頭に引用した「趣味の遺伝」で「山寺のカツポレ」の出てくる前にかなり長く解説されている『マクベス』の門番の長広舌なのである。
この部分はのちに『文学論』の一部をなす講義のおさらいのようでもあって(その内容は第二章で詳論する)、小説としてはいささか長々しく読みにくいが、ともかく「廃寺に一夜をあかした」直後に「庭前の一本杉の下でカツポレを踊るもの」を見る場合の「物凄い」感じは、「マクベスの門番」と「同格」の「諷語」だという議論になっていく。
この「諷語」は、そのすぐ前でこう解説されている。
諷語は表裏二面の意義を有して居る。先生を馬鹿の別号に用ひ、大将を匹夫の渾名(あだな)に使ふのは誰も心得て居やう。此筆法で行くと人に謙遜するのは益(ますます)人を愚にした待遇法で、他を称揚するのは熾(さかん)に他を罵倒した事になる。表面の意味が強ければ強い程、裏側の含蓄も漸く深くなる。
「此心理を一歩開拓して考へて見る」と、「滑稽の裏には真面目」が、「大笑の奥には熱涙」が、「雑談(じようだん)の底には啾々(しゆうしゆう)たる鬼哭」がひそんでいる。
だから『マクベス』の門番の駄弁の滑稽さにも、その直前に与えられて観客の意識にまだ残留している殺人の凄絶さが付随していて、その矛盾的併存が「山寺のカツポレ」と同質の物凄さをかもしだすというのである。