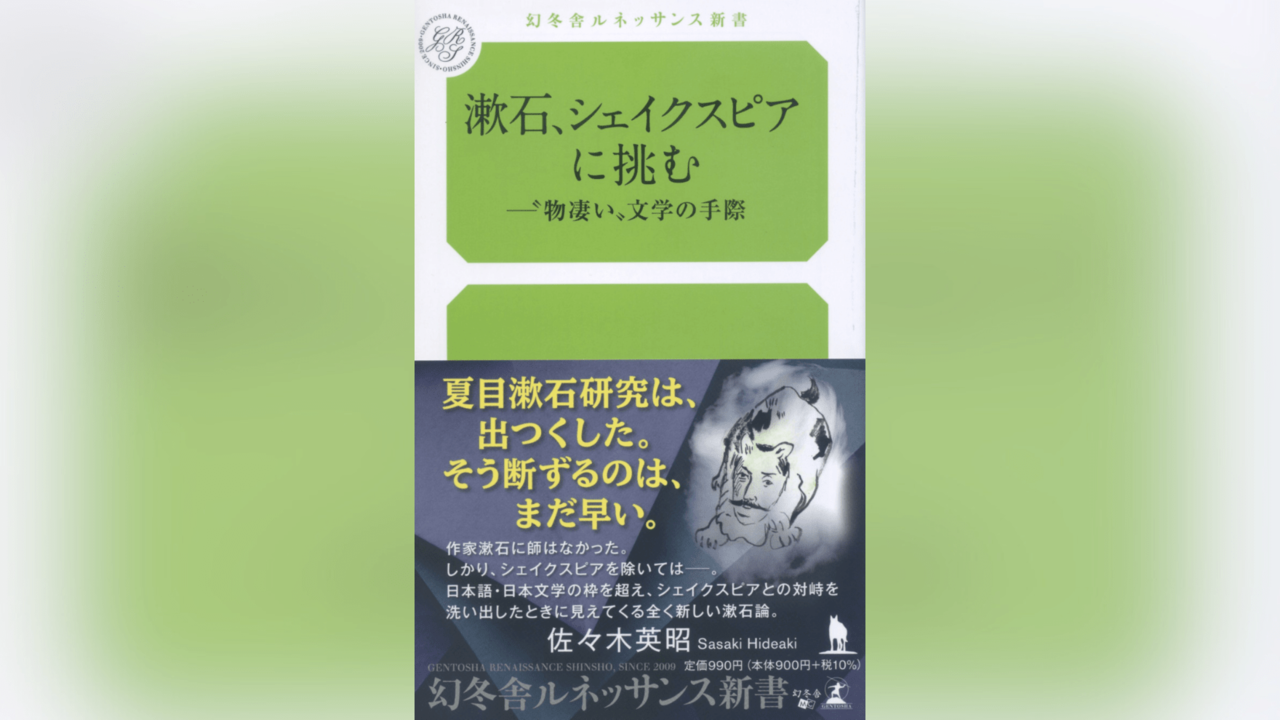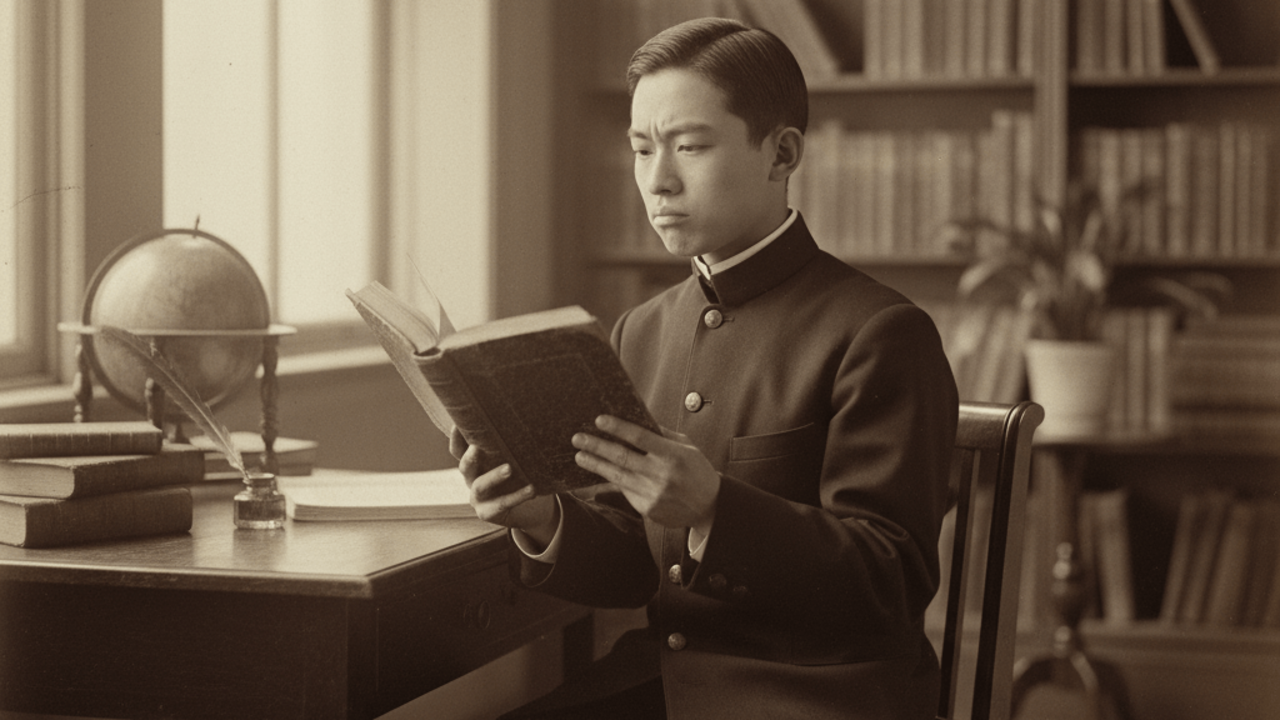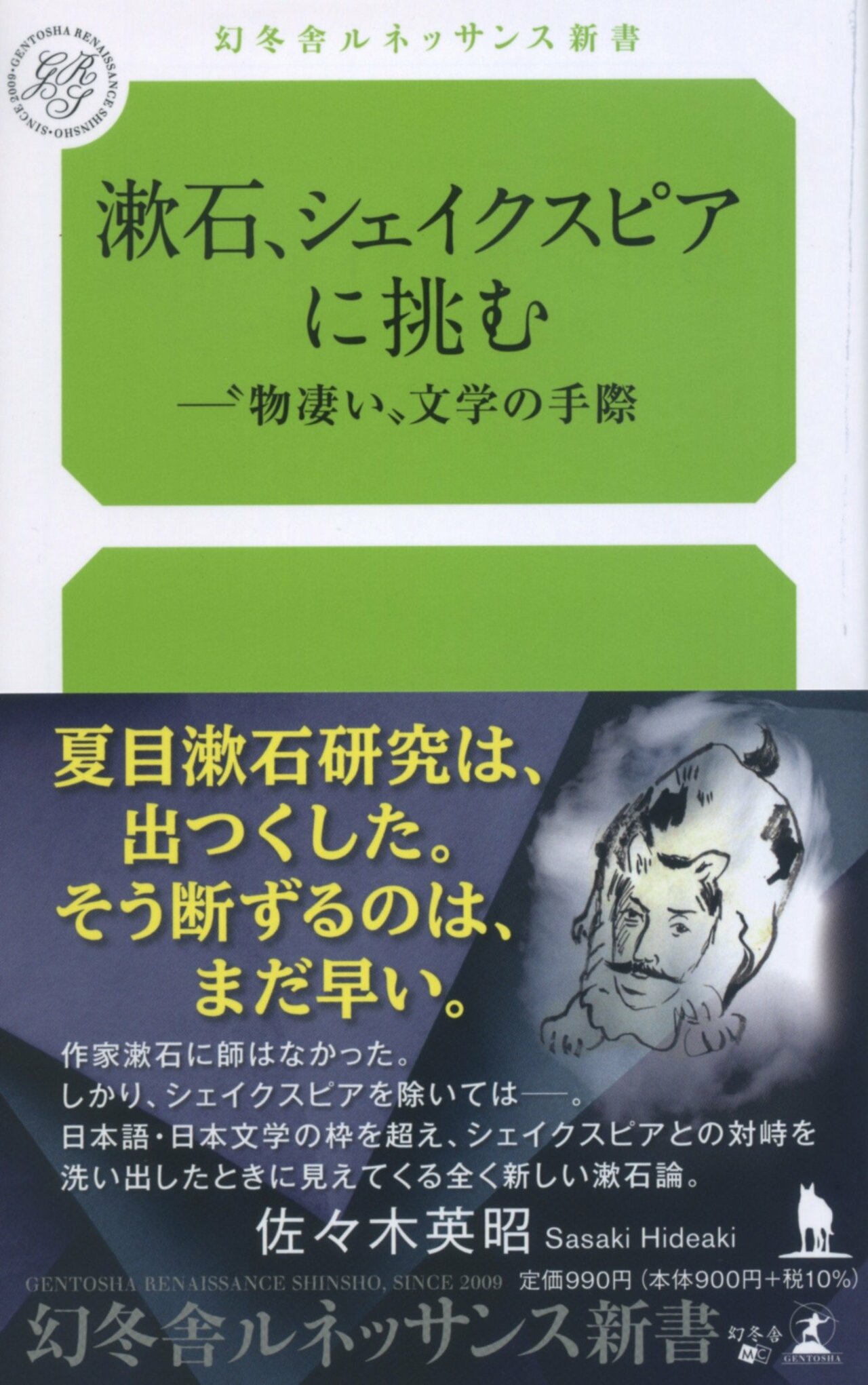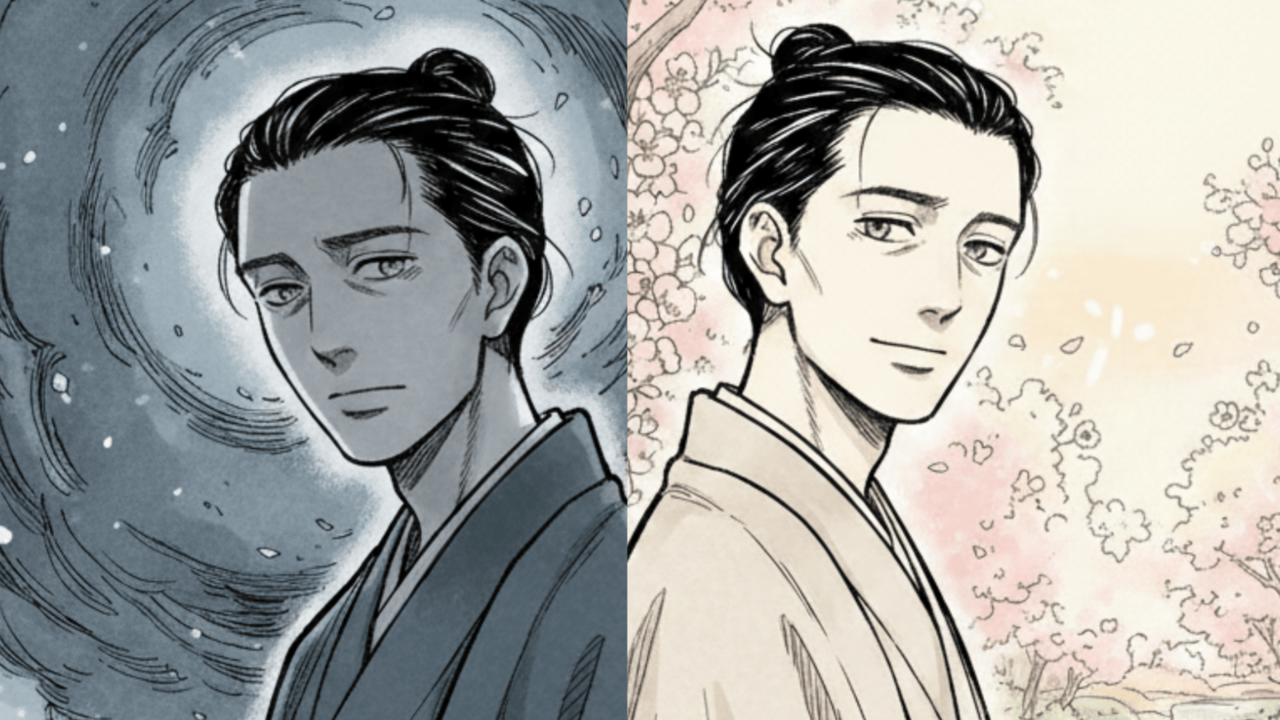【前回記事を読む】お墓にうつる黒と白——先生と奥さんの心がすれちがうときに見えるものとは? 「こころ」の一場面から考える
序章 ぎょっとするオセロ・マジック
黒白の変化を同一物の上に起こす
物には必ずその反面がある。一つの物でもその人の立場に依つては多種多様に見える。その一面にばかり拘泥して、これが真理だと他を排撃してはならない。
(『漱石先生と私』※1上巻〔東西出版社、一九四七〕三九三~四頁)
一つの黒いものも「その人の立場に依つては」白くも見え、「立場」が逆転すれば、「黒/白」が「真逆かさまにひつくり返る」こともある。SF的な仮想を言わせてもらえば、漱石がもしオセロ・ゲームを知っていたら、比喩に持ち出したのではないかとも思わせる。
この哲学を漱石が自ら温めていたことは明らかだし、漱石文学のところどころにそれが顔を出すことも、愛読者なら先刻ご承知だろう。
さて、右に引いた猫の説法は、まさにそれを文学の内容として記述していたわけだが、本書がまず明らかにしたいのは、内容よりむしろ方法としてひそんでいる、この「黒白」の反転または矛盾的並立という、オセロ・ゲーム的な仕掛けについてである。
そのような仕掛け、というか文学技法全般を漱石はしばしば「手際」と呼んだが、その「手際」がどこから学ばれて、どのようにわがものとされたかを問題にする場合、無視できない作家の筆頭に挙がるのが、このゲームの名の由来となった悲劇『オセロー』(推定執筆年 一六〇三~四年)を書きもし、
「趣味の遺伝」では『マクベス』(同一六〇六年)が言及を受けたばかりでなく、「先生は常に『ハムレツト見た様な傑作を書くんだ』と口癖の様に云つて居られた」との証言(野間眞綱「追想」、『思想』一九三五年一一月)さえあるところの、シェイクスピアにほかならない。
この文豪に漱石を対峙させたほぼ唯一の先行研究『漱石のシェイクスピア』(朝日出版社、一九七四)で、
野谷士(あきら)は「課題とすべきは漱石の精神形成に及ぼしたシェイクスピアの影響」であって「漱石が、劇作家シェイクスピアから技巧的に大きな影響を受けたと言うことは出来ない」としているが(三九頁)、実はこの「黒/白」も「ひつくり返」さなければならない。
大学予備門(現在の大学一・二年次に相当)時代、友人の中村是公 (よしこと)(「ぜこう」と呼びならわす)が買ってくれた『ハムレット』を読んでみたが