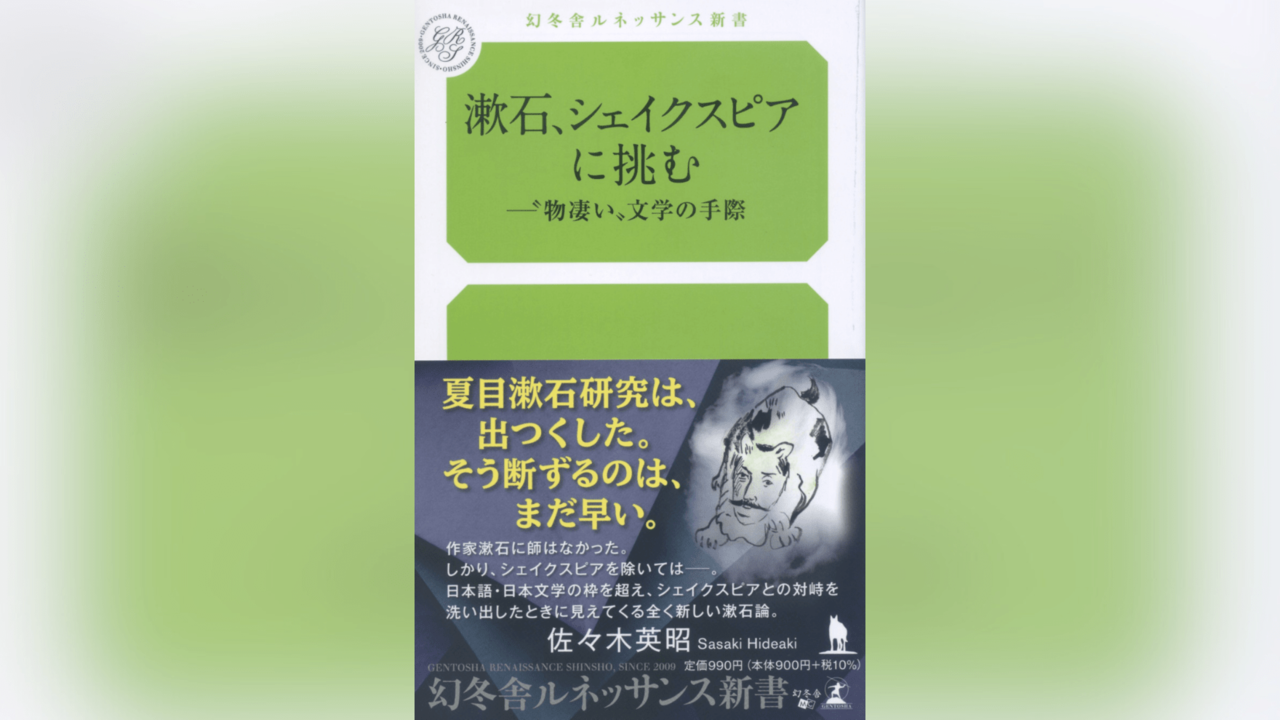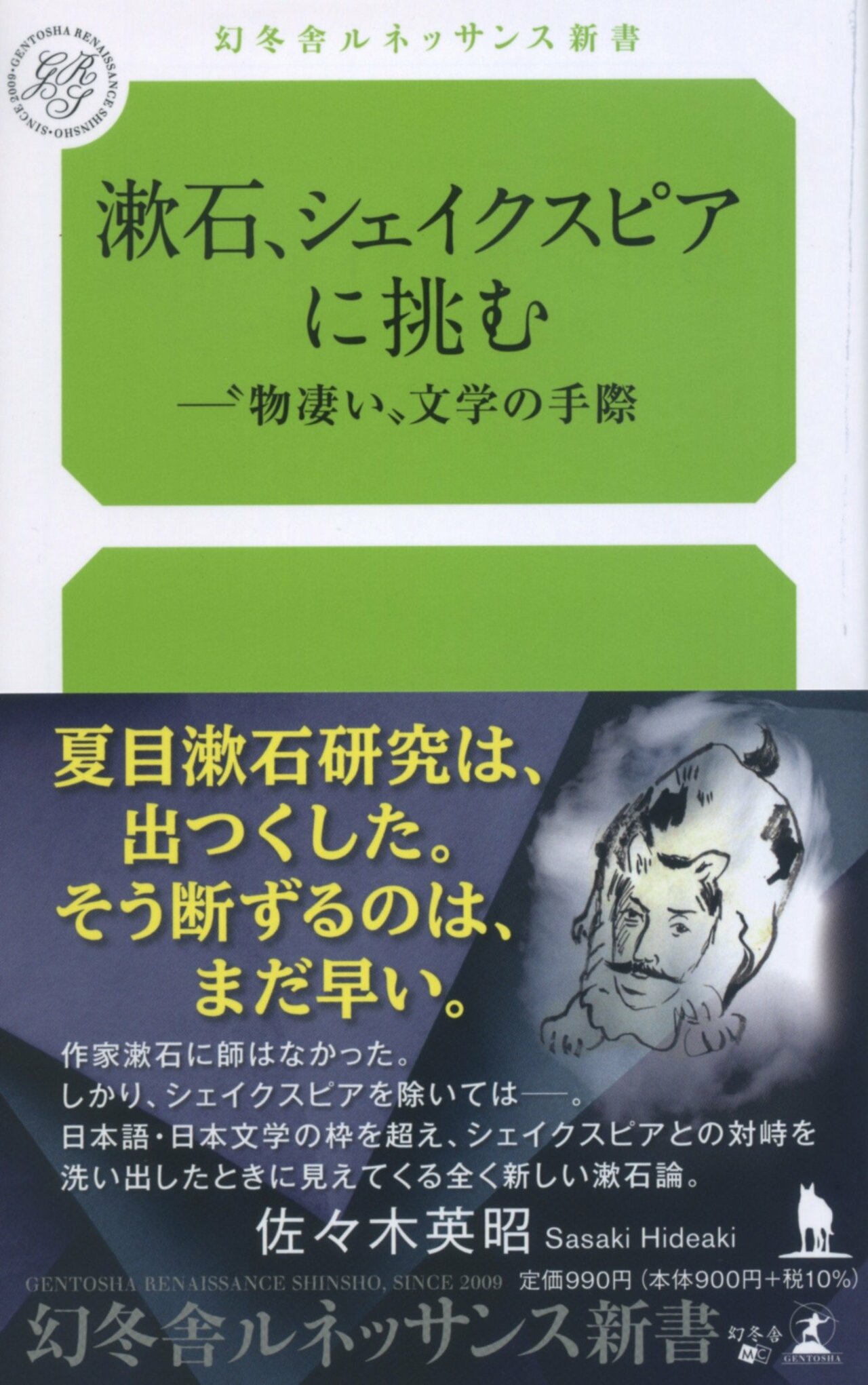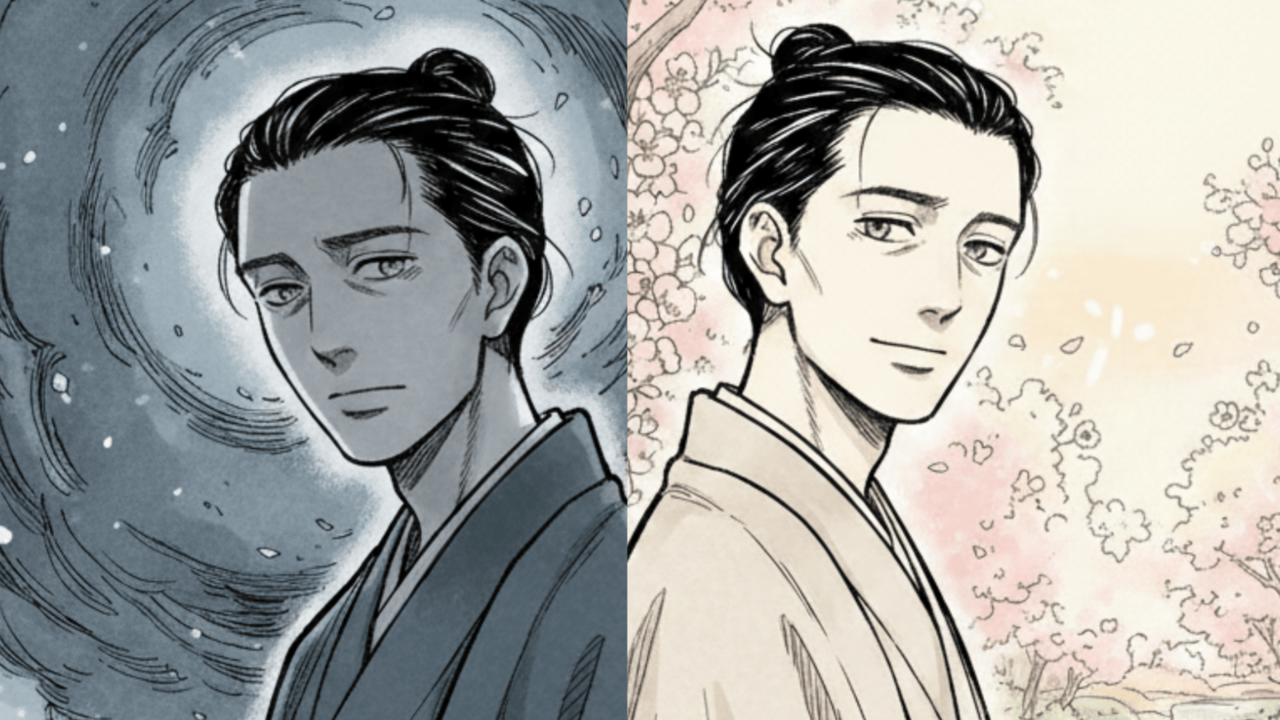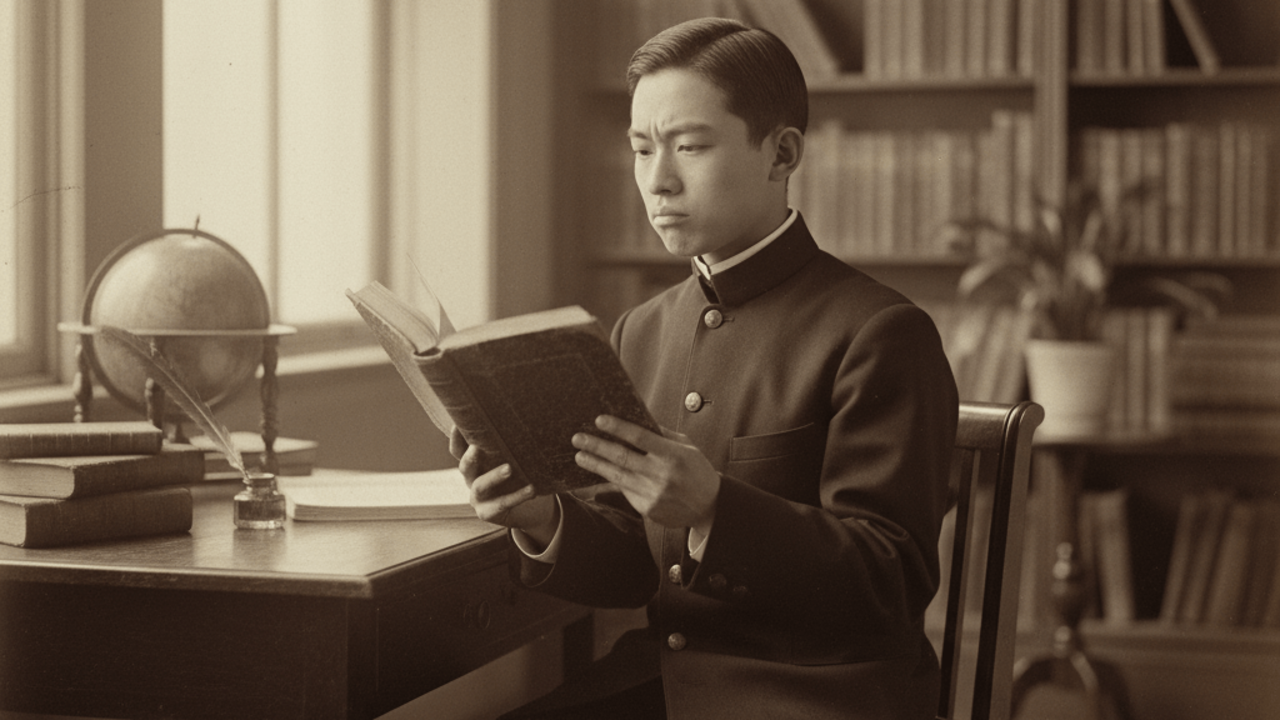【前回記事を読む】シェイクスピアを読むともっと面白くなる夏目漱石の文学 日本とイングランド、遠く離れた地で育った二人に共通する言葉を辿る―
序章 ぎょっとするオセロ・マジック
黒い光が物凄く照らす
私は意味もなく唯たゞぎよつとしました。何(ど)うしてそんな事を急に思ひ立つたのかと聞きました。妻(さい)は二人揃つて御参りをしたら、Kが嘸(さぞ)喜こぶだらうと云ふのです。私は何事も知らない妻の顔をしけじけ眺めてゐましたが、妻から何故そんな顔をするのかと問はれて始めて気が付きました。〔中略〕
其(その)時妻はKの墓を撫でゝ見て立派だと評してゐました。其墓は大したものではないのですけれども、私が自分で石屋へ行つて見立(みたて)たりした因縁があるので、妻はとくに左右(さう)云ひたかつたのでせう。私は其新らしい墓と、新らしい私の妻と、それから地面の下に埋められたKの新らしい白骨とを思ひ比べて、運命の冷罵を感ぜずにはゐられなかつたのです。私はそれ以後決して妻と一所にKの墓参りをしない事にしました。(下 五十一)
この部分(原文では三段落に及ぶ)全体を支配する焦点的なイメージがKの墓という物体にあるとすると、この同じ物体がまるで異なる色調で二人の目を捉えていることに、「面白いといふ感じ」を受ける読者もいることだろう。
何が「面白い」のかといえば、先生がそこに例の「黒い光」と「黒い影」の再現を見ている一方で、「上先生と私」であらかじめ「白」と結びつけられてもいる妻――夫婦で使うテーブル・クロスについて、先生は「白ければ純白でなくつちや」と「白」にこだわる(三十二)――は穢れのない純白のものであるかのようにそれを見守る、という皮肉(アイロニー)に出合うからである。
あるいは、この見え方の「黒/白」の背反それ自体が、廃寺の夜明けに一本杉の下でカ ツポレを踊るのにも似て物凄い。
それ自体が、皮肉抜きでも「面白い」のである。「二人でKの墓参りをしやう」と言われただけで先生が「意味もなく唯ぎよつとする」のは、その時点でこの光景を、心のどこかですでに予見していたからではないのか?