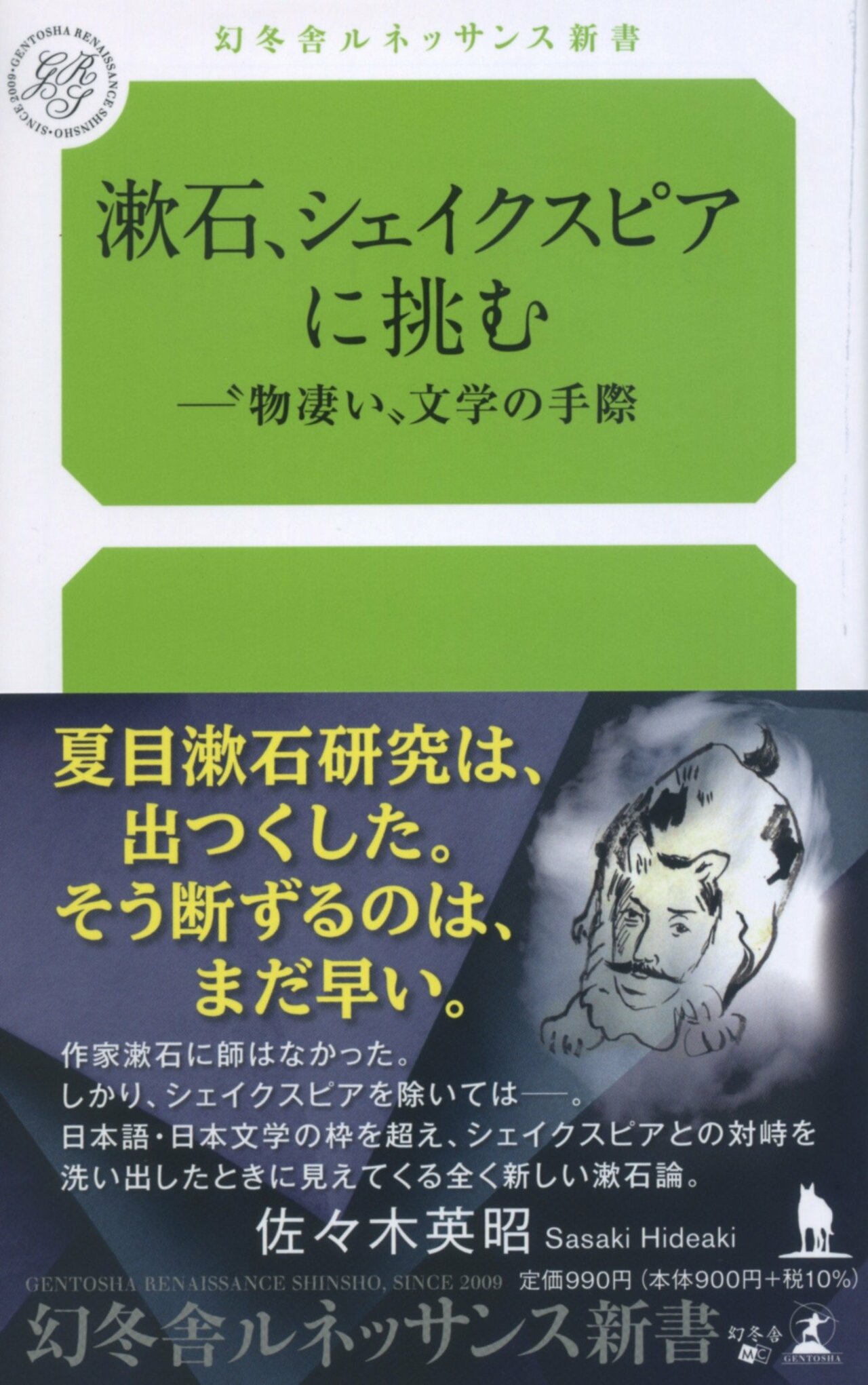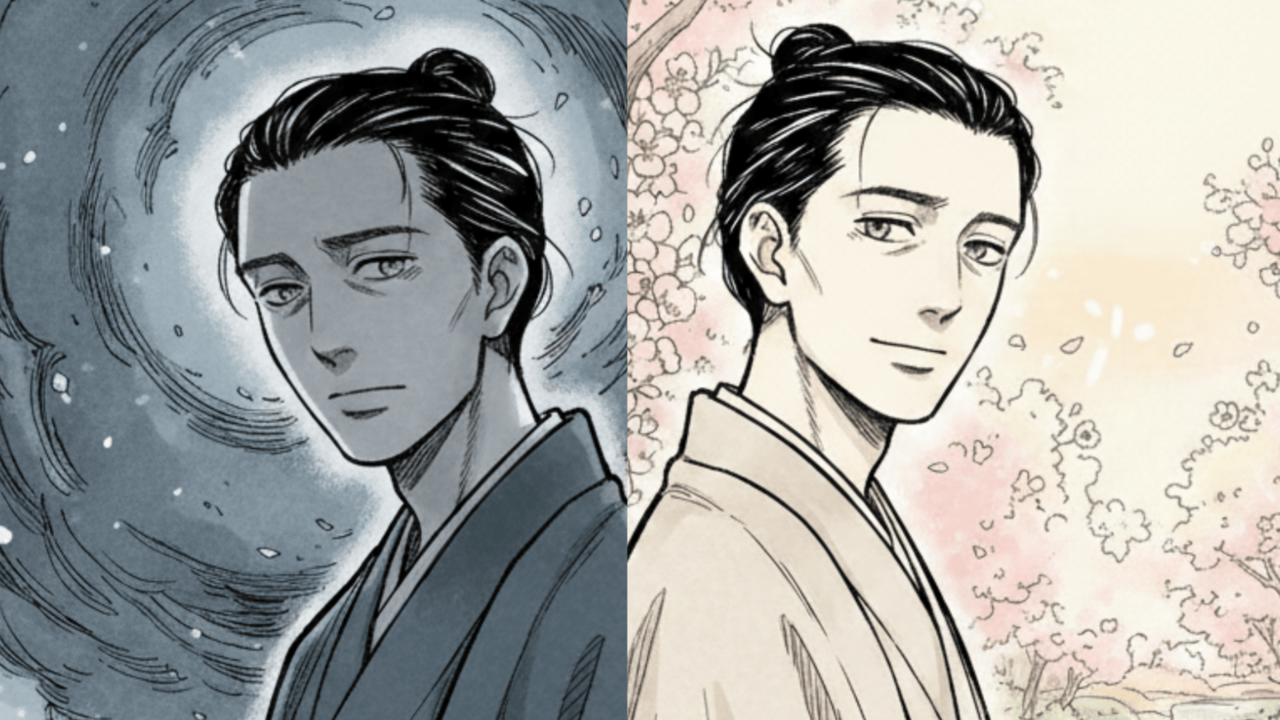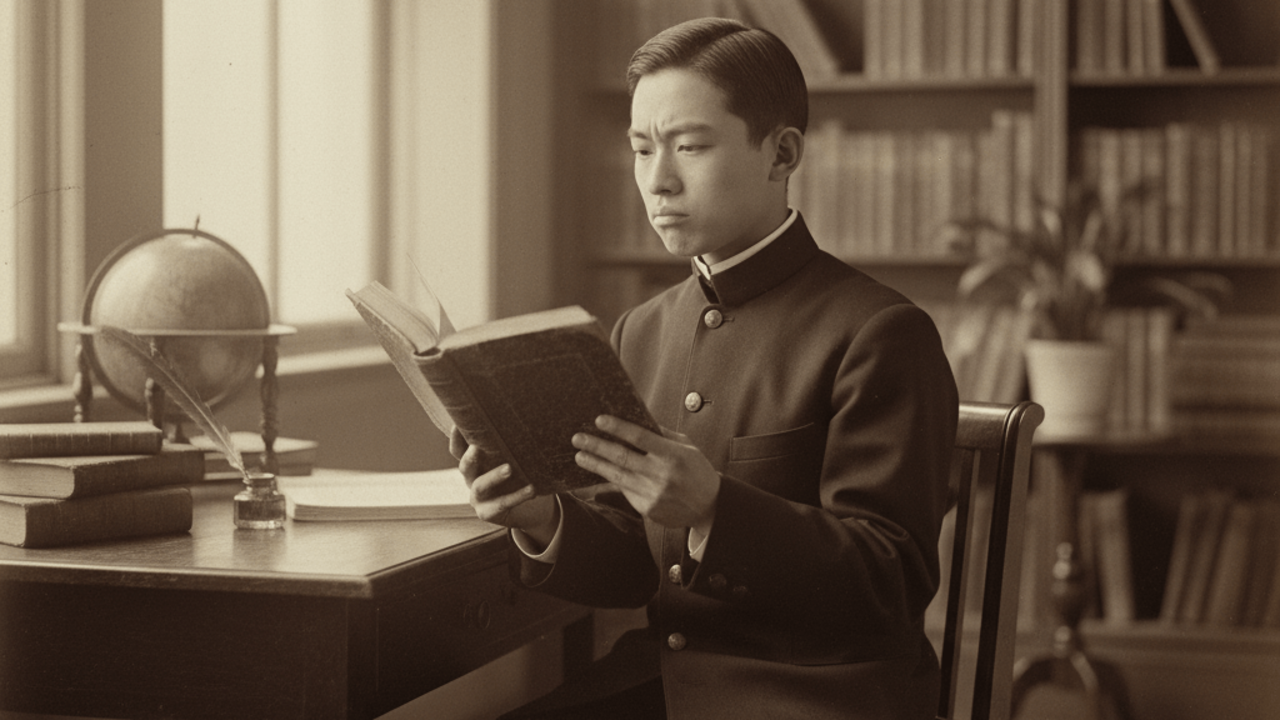黒白の変化を同一物の上に起こす
ともかく、『こころ』の先生が「ぎよつとする」理由はほかにないのだ。Kの墓という同一物についての、この「黒/白」二様の見え方、あるいはそれに似た「物凄い」光景を、漠とであれ予見したこと以外には。
ちなみに「趣味の遺伝」で言われていた「物凄からう」もまた、物事の「黒/白」二面性の発見によって発生する感覚なのであって、そのつながりは、この短編小説と同じ月に発表された『吾輩は猫である』第七回で、「吾輩」と称する猫が明かしてくれている。
いわく、「運動をする」ことは、昔は「下等」と見なされたにもかかわらず、今はもてはやされている。ことほどさように「吾人の評価は吾輩の目玉の変化の如く変化する」。
これが人間の「品隲(ひんしつ)〔品定め〕」になると、猫の目玉どころの話でなく「真逆かさまにひつくり返る」ことさえあるけれども、「ひつくり返つても差し支(つかえ)はない」のだ、と猫は説く。
物には両面がある、両端がある。両端を叩いて黒白の変化を同一物の上に起す所が人間の融通のきく所である。
方寸を逆かさまにして見ると寸方となる所に愛嬌がある。天の橋立を股倉から覗いて見ると又格別な趣が出る。セクスピヤも千古万古セクスピヤではつまらない。
偶(たま)には股倉からハムレツトを見て、君こりや駄目だよ位に云ふ者がないと、文界も進歩しないだらう。(傍点は「方寸」「寸方」のみ原文どおり)
後半の「セクスピヤも」云々はよく引かれてきた文だが※2、ここでは、それが「人間の品隲」を含め、あらゆる物事には「両面がある」とする説法の延長上に出てきていることに注意しよう。
つまり猫がシェイクスピアを引き合いに出したのは、「真逆かさまにひつくり返る」ような「黒白の変化を同一物の上に起す」という、まるでオセロ・ゲームのような「融通」が人間にはきく。そのことを高く(あるいは皮肉に)評価する文脈においてのことなのだ。
「物には両面がある」という洞察は、漱石が直々、「木曜会」(漱石宅で開かれていたサロンで、面会希望者が増えすぎたため、『猫』連載終了後の一九〇六年十月から木曜に限定された)で門弟たちに説いたところでもあった。うろおぼえながら、森田草平はこう祖述している。
※2 その最新のものに芦津かおり『股倉からみる『ハムレット』 シェイクスピアと日本人』(京都大学学術出版会、二〇二〇)があり、同書では漱石を含む多くの作家によるこの種の「股のぞき」が探求されている。