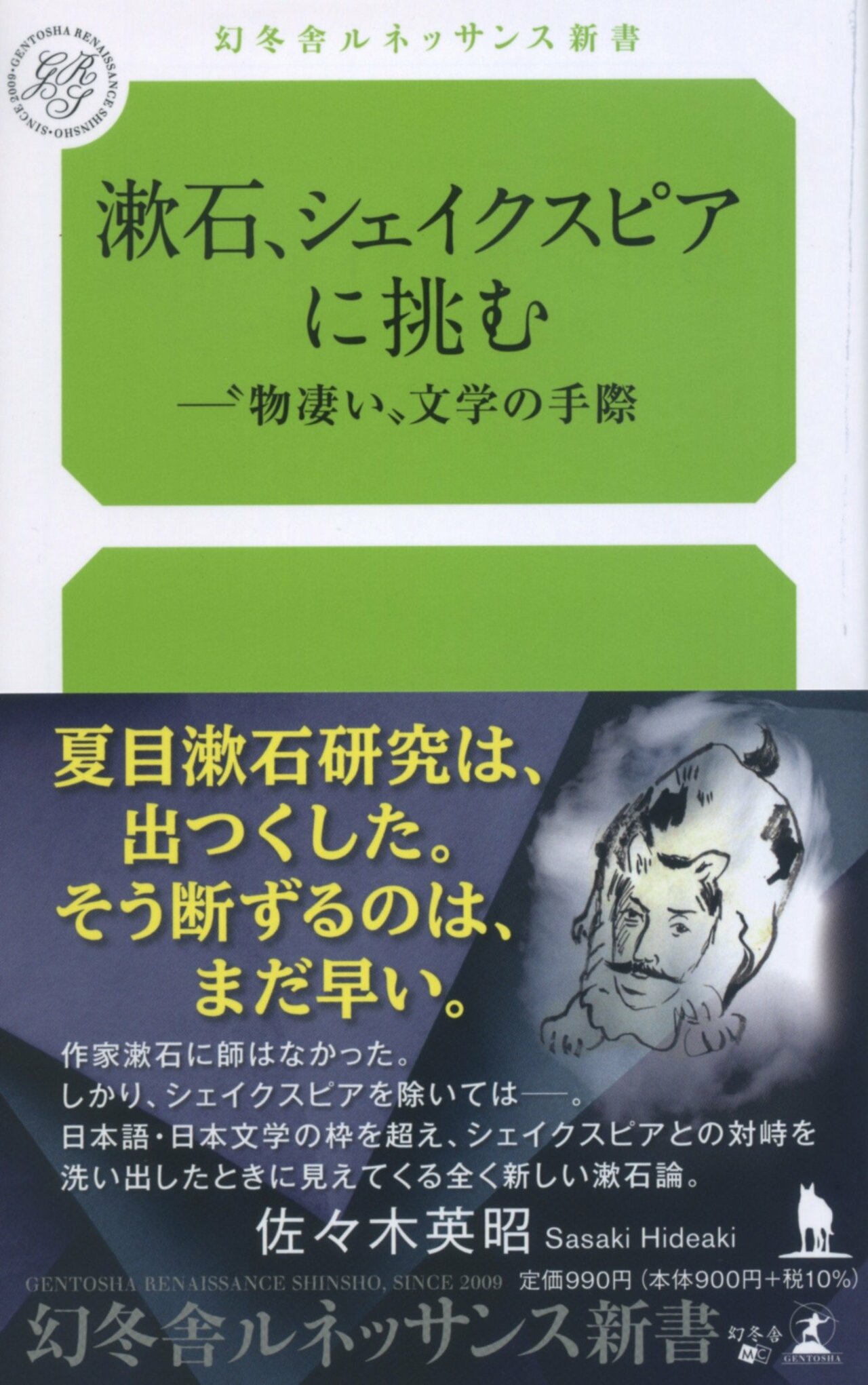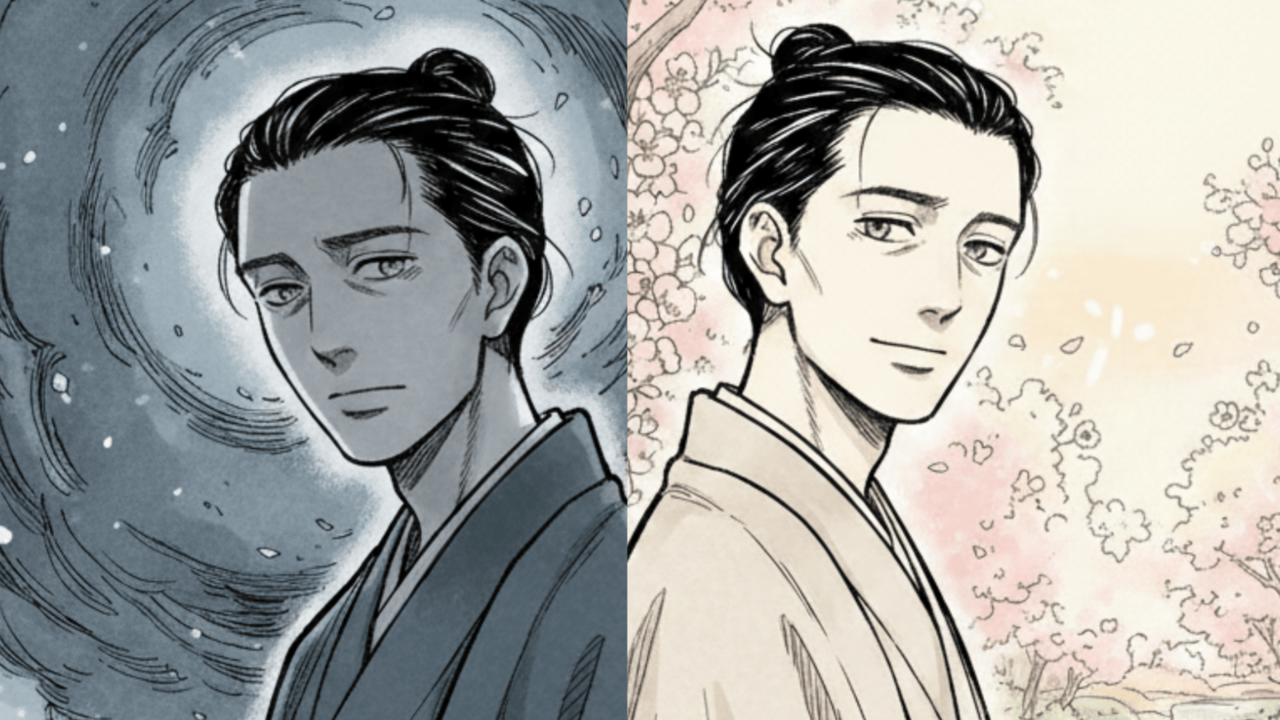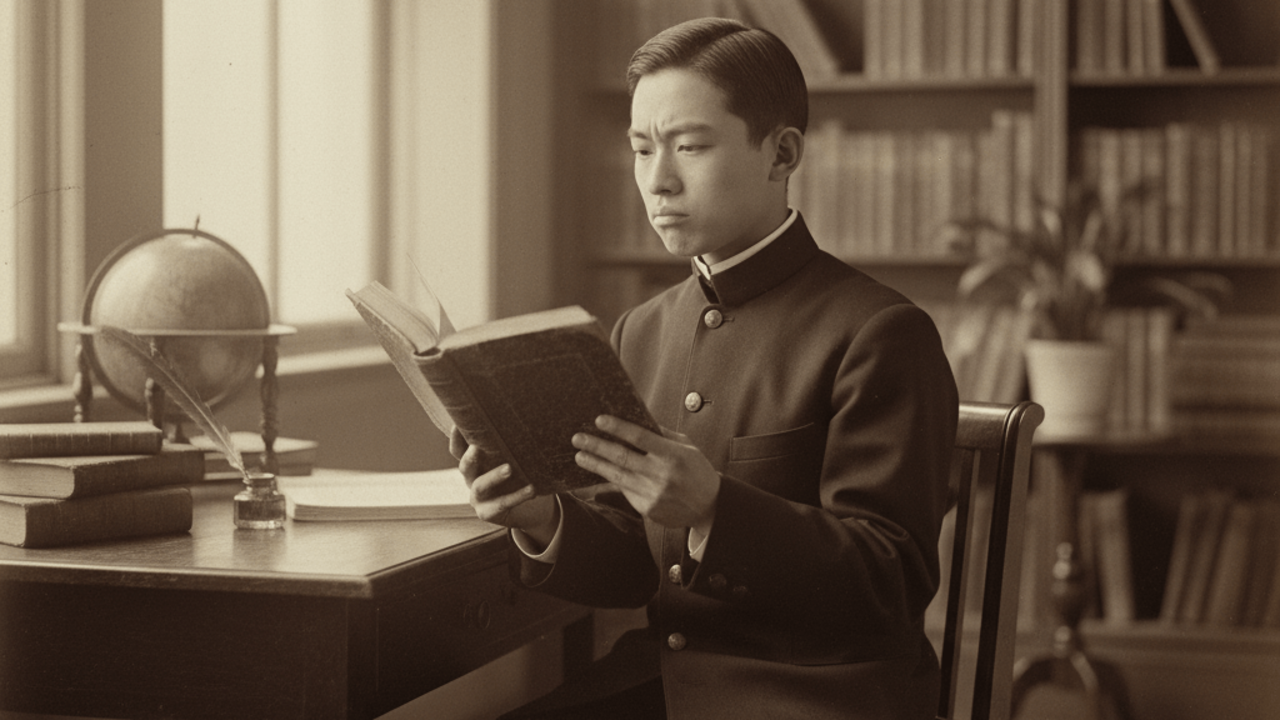「些(ちつ)とも分らなかつた」(『永日小品』「変化」)という回想があるとはいえ、文科大学に進んでは「図抜けた偉物」(関荘一郎「『道草』のモデルと語る記」、一九一七)と畏怖された漱石のこと※2、いつか深入りが進み、シェイクスピアは主要な研究対象となっていく。
熊本の第五高等学校時代は始業前の無償の講読を買って出るほどだったし、そこから渡航したロンドンでの二年の、少なくとも前半の研鑽はシェイクスピア学者、W・J・クレイグの家に毎週通って個人授業を受けることを主軸としていた。
一九〇三年の帰国後まもなく着任した東京帝大では、九月から〇七年三月の辞職までシェイクスピア講読が継続されたが、唯一出版された講義録である『「オセロ」評釈』を読みこめば、「シェイクスピアの影響」が「精神形成」云々より「技巧的」な側面に多くあったことはおのずと明らかになる。
出版物として残された講義録が『オセロー』のみであったことには、偶然的要因ばかりで片づけられない、なにがしかの縁があったのだろうか。五高で早朝講義を受講した、のちの物理学者で『猫』の「寒月君」のモデルといわれる寺田寅彦は、漱石追悼にあたってこんな短歌を詠んでいる。
春寒き午前七時の課外講義オセロを読みしその頃の君
(『寺田寅彦全集』〔岩波書店、一九九七〕第十一巻、四六八頁)
ともあれ、東京帝大でのシェイクスピア連続講義は盛況ぶりが伝えられており、皮切りとなった『マクベス』は「出席者廿番教室に充溢」し、十二月には「二人の西洋婦人参観に来る」※3という光栄に浴してもいた。
※1 この本は『続夏目漱石』(甲鳥書林、一九四三)の改版であり、のちに後掲の『夏目漱石』〔28頁〕との合本として講談社学術文庫版『夏目漱石』((一)~(三)、一九七〇)が編集・刊行される。
※2 詳細は漱石詳伝として最新のものである拙著『夏目漱石人間は電車ぢやありませんから』(ミネルヴァ書房、二〇一六)を参照されたい。
※3 金子三郎編著『記録 東京帝大一学生の聴講ノート』(リーブ企画、二〇〇二)に「付記」として収録された金子健二の日記による。
【イチオシ記事】「私、初めてです。こんなに気持ちがいいって…」――彼の顔を見るのが恥ずかしい。顔が赤くなっているのが自分でも分かった
【注目記事】「奥さん、この二年あまりで三千万円近くになりますよ。こんなになるまで気がつかなかったんですか?」と警官に呆れられたが…